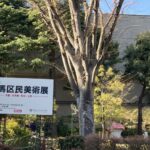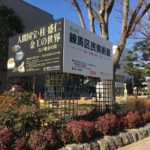■第55回練馬区民美術展の開催
第55回練馬区民美術展が開催されました。期間は2024年2月3日(土)から2月12日(月)まで、時間は午前10時から午後6時(最終日は午後2時終了)でした。美術館脇の公園には、第55回美術展の看板が掛けられていました。
館内に入ると、出品作品は、洋画1、洋画Ⅱ、日本画、彫刻・工芸のジャンルに分けて、展示されていました。
私は洋画Ⅰ(油絵)部門に出品しましたが、この部門の出品者は69名でした。その中から区長賞1名、教育委員会賞1名、美術館長賞1名、奨励賞3名、努力賞3名が選ばれています。
まず、私の作品が展示された、洋画1の部門のコーナーを見てみましょう。
真ん中に展示されているのが、私が出品した作品です。風景を背景としているので、カンヴァスはPサイズの20号を使いました。
昨年と同様、母をモチーフに描きました。もちろん、リアルな母ではなく、イメージの中の母を手掛かりに、晩年に差し掛かった頃の姿を作品化しています。
もうすぐ100歳になろうとする母は、認知症が悪化し、95歳ごろから施設のお世話になっています。今では、施設を訪れても、私のことを認識できず、言葉にならない音声を発することしかできなくなりました。
人としての形が徐々に崩れ始めているのですが、それでも、その表情や目つきには、かつての母の面影が残っていました。認識能力を失っているはずなのに、聡明で、孤高の面持ちが見られるのです。
母のことをいろいろと思い返しているうちに、ふと、80歳になった頃から、母が不思議な輝きを見せ始めたことを思い出しました。
母は、晩年に入ろうとしている頃から、全身からいぶし銀のような輝きを発しはじめました。その時は、深く考えもしなかったのですが、その後、さまざまな高齢者の姿を見るにつれ、なぜ、母にそのような変化が起きたのか、不思議でならなくなりました。
一時は、その理由を探りたいと思ったこともありました。ところが、母と離れて暮らすうちに、そのような気持ちもいつしか忘れ去っていました。
今回、母をモチーフに絵を描こうとしたとき、ふいに、その頃の気持ちが甦ってきました。記憶の底に深く沈んでいたその気持ちが、突如、浮上してきたのです。
そこで、当時の母をイメージしながら、その姿をカンヴァスに表現してみることにしました。母の不思議な輝きの源泉を見出すことができるかもしれません。
そう思った途端、反射的にタイトルが思い浮かびました。
《晩秋》です。
■《晩秋》
80歳になった母は、もちろん、見た目は年齢相応に老いていました。肌はくすみ、深く刻み込まれた皺は隠しようもなく、衰えが顔全体に広がっていました。ところが、ふとした拍子に見せる表情に、なんともいえない輝きがみられるようになりました。
それは、年齢に抗って放たれているように見える一方、年齢の積み重ねによって生み出されているようにも見えました。
80歳にならなければ、得られないような美しさであり、ひっそりとした輝きでした。誰もが気づくわけでもありません。母が生きてきたプロセスを知っている者しか、看取できない微妙な変化でした。
見た目の老いの背後から滲み出た内面の深みであり、母が本来、持ち合わせていた聡明さや孤高の精神と交じり合って生み出された風情や雅趣といえるようなものでした。
人生を四季に例えるなら、まさに、晩秋の輝きでした。
もうすぐ冬になろうとする時期、気温は下がり、木々の葉はさまざまに紅葉していきます。街路を見渡せば、イチョウ並木が黄色く輝き、塀越しに見える庭木は、橙色や黄色に色づき、遠く山を望めば、とりどりの暖色系の葉で覆われた木々が華やいで見えます。
晩秋ならではの、いっときの輝きです。
やがて、冷たい風が吹いて、木々は葉を落とし、いっさいの生命活動は鳴りを潜めてしまいます。晩秋から冬にかけてのほんの一時期、木々は紅葉した姿で、精一杯の輝きを見せるのです。
80歳頃からの母の輝きは、紅葉した木々の姿に重ね合わせることができるものだったような気がします。
紅葉の季節が過ぎれば、木の葉は一枚、一枚、散って落ち、瞬く間に、枝と幹だけになっていきます。人もまた80歳を過ぎれば、一年、一年、老いが目立つようになり、動作も反応も鈍くなっていきます。生命力が衰えていく過程が、そのような現象として現れるようになります。
母は80歳になっても、背を丸めて歩くようなことはなく、背筋をピンと張って歩いていました。思い返すと、母が不思議な輝きを見せていたのは、80歳からの10年間ほどでした。90歳になると、歩調は遅くなり、反応も鈍くなっていきました。さすがに心身ともに老いが際立つようになり、ひっそりとした輝きも老いの影に隠れてしまいました。
晩秋に思いきり輝き、やがて、散っていく木の葉のように、母は80歳からの10年間、いぶし銀のような輝きを見せ、そして、その後の10年間、人としての形が脆くも崩れていきました。
今回、カンヴァスに描きとどめようとしたのは、晩節に母が見せてくれた、ひっそりとした輝きです。
■母をどう描いたか
今回、私が出品した《晩秋》を見ていくことにしましょう。
こちら →
(油彩、カンヴァス、72.7×53㎝、2023年。図をクリックすると、拡大します)
写真では、会場のライトが額縁のアクリル面に反射しています。カンヴァスの画面がありのままに写し出されているとはいえませんが、私が表現したかったことはほぼ、この写真から伝わってくると思います。
描きたかったのは、老いてなお輝きを見せていた頃の母のイメージです。
当時、帰省するたびに見かけていたのが、もの思いに耽る母の姿です。台所で料理をしている時、庭で草むしりをしている時、床の間の花瓶に花を活けている時、ふとした拍子に、母は「心ここにあらず」の表情を見せることがありました。
もの思いに耽っているように見える時があれば、何か考え事をしているように見える時もありました。母の周囲には、人を寄せ付けない、孤高の雰囲気が漂っていたのです。気軽に話しかけることもできず、戸惑ったことを覚えています。
その時の光景を何度も思い返しているうちに、この孤高の雰囲気こそが、母が見せていた不思議な輝きの源泉なのかもしれないという気がしてきました。
孤高の雰囲気とそこから生み出される輝きを表現するには、どのような画面構成にすればいいのか、考えてみました。さらに、モチーフをどのような設定すればいいのか、背景をどうすればいいのか、いろいろとシミュレーションしてみました。
■逆光の中のメインモチーフ
まず、メインモチーフの母は、逆光を受けて佇む姿にしようと思いました。
晩節にさしかかった母を、明るく輝かしく描くのは不自然です。顔色は当然、暗く、鈍い色調でなければなりません。その反面、顔面にはいぶし銀のような輝きも必要です。そこで考えたのが、逆光の中でモチーフを描くという構図です。
こうすれば、メインモチーフに必要な二つの側面を表現できると考えたのです。
実は、このようなアイデアを思い付くキッカケとなったのが、ミレーの《晩鐘》でした。
こちら →
(油彩、カンヴァス、55.5 × 66 cm、1857-59年、オルセー美術館蔵。図をクリックすると、拡大します)
ミレー(Jean-François Millet、1814 – 1875)は、バルビゾン派を代表する画家といわれ、田園に取材した作品を数多く制作しました。この作品はそのうちの一つです。
画面には、農民夫婦が手を休めて祈りを捧げる様子が描かれています。逆光の中で手を合わせ、祈りを捧げる夫婦の姿が、静かな佇まいの中で捉えられているのが印象的です。タイトルからは、晩鐘が鳴り響くのを合図に、一日の平安を感謝する敬虔な気持ちが表現されていることがわかります。
この作品は、1865年2月にパリで展示されました。その時、ミレーは、次のように、祖母の思い出を描いた作品であることを述懐していたそうです。
********
かつて私の祖母が畑仕事をしている時、鐘の音を聞くと、いつもどのようにしていたか考えながら描いた作品です。彼女は必ず私たちの仕事の手を止めさせて、敬虔な仕草で、帽子を手に、「憐れむべき死者たちのために」と唱えさせました。
********(※ Wikipedia)
在りし日の祖母の姿を思い起こしながら、ミレーはこの作品を描いていたのです。そのような背景事情を私はまったく知りませんでしたが、美術の教科書でこの作品を見たとき、敬虔な農民の姿に強く心を動かされたことは、はっきりと覚えています。
当時、ヨーロッパでは風景画が注目を浴びるようになっていました。ところが、ミレーは、都会人が求めるような田園風景を描くのではなく、農民の生活を踏まえて風景を描いていたといわれています。
日本の紹介された作品、《種まく人》(1850年)や《落穂拾い》(1857年)などを見ると、確かに、ミレーが風景を、農民の生活と一体化させて捉えていることがわかります。農民の生活と真摯に向き合い、深く観察して作品化していったところに、ミレーの独自性があるといえるでしょう。
私がなぜ、この作品を思い出したかといえば、母の生きる姿勢に、この作品に見られる敬虔な要素があったからでした。母は「徳子」という名前でしたが、その名の通り、「徳を積む」ことをひっそりと実践してきた人生でした。私がミレーのこの作品をまっさきに思い出したのは、おそらく、農民夫婦の敬虔な光景に、母の生き方との親和性が見られたからでした。作品から受ける敬虔な印象が、母を思い起こさせたのです。
もっとも、この作品には、私が求めるいぶし銀のような輝きは見られません。確かに、穏やかさ、落ち着き、敬虔さは画面から伝わってきますが、輝きが足りません。陽が落ちた残照では、命のラストステージを煌めかせる熱量が不足しているのです。
メインモチーフである母に、いぶし銀の要素を添えるには、もう少し、きらびやかな要素が必要でした。
そこで、さらにミレーの作品を渉猟してみました。すると、次のような作品が見つかりました。
こちら →
(油彩、カンヴァス、100.7×81.9㎝、1870-72年、ニューヨーク フリック・コレクション。図をクリックすると、拡大します)
タイトルは《ランプの明かりで縫物をする女性》(Woman Sewing by Lamplight)です。初めて見る作品です。
ミレーは1875年1月20日に亡くなっていますから、制作年からいえば、晩節の作品といっていいでしょう。
《晩鐘》とは違って、メインモチーフのすぐ近くにあるランプが光源になっています。画面中央辺りが明るい色調、そこから遠ざかるにつれ画面が暗くなるという色構成です。モチーフがランプの光で、明るく浮き彫りにされているのが印象的です。
画面全体から、暖かな家庭の温もりが感じられます。
ランプから放たれた穏やかで暖か味のある光が、女性を照らし出しています。横顔、肩、手を柔らかい光で包み込み、縫物をする女性を優しく捉えています。よく見ると、ライトの下では、赤ん坊が眠っています。俯き加減に針を運ぶ女性は、おそらく、母親なのでしょう。
ランプを光源とする穏やかな光線が、周辺に柔らかな陰影を作り出し、作品に落ち着きと暖かさを添えています。黄色、橙色など暖色系を中心とした色構成の中に、農民の生きる力とひっそりとした輝きが感じられます。
この色合いを、メインモチーフを支える背景色に使ってみようと考えました。
次に、考えたのが背景です。
■背景としての湖畔、差し色としての白
晩節の母を描くのですから、私は、背景として、晩秋の風景しか思いつきませんでした。もちろん、一口に晩秋といっても、さまざまな風景があります。紅葉した街路樹もあれば、紅葉した山、あるいは、すっかり葉を落とした木々など、どのような景色を選べば母のイメージに相応しいのか、悩み、いろいろとシミュレーションしてみました。
その結果、晩秋の湖畔を、背景として取り上げることにしました。
湖畔なら、紅葉した木々、すっかり葉を落とした木々など、晩秋を象徴する一切合切を、一つの景色の中に収めることができます。それらの要素を、ごく自然に画面に持ち込むには、湖畔がもっとも適していると思ったのです。
さらに、背景を湖畔に設定すれば、メインモチーフとの間に、ちょっとした空間を生み出すことができます。この空間を活かす恰好で、湖の際に枯れ木、湖辺に紅葉した木々を描けば、画面に奥行きや深みを生み出し、興趣を感じさせることができると考えました。
こうして、枯れ木や紅葉した木々を配した湖畔を背景に、逆光を受けて佇む母の姿をイメージして描いたのが、先ほどご紹介した《晩秋》です。
メインモチーフと背景との組み合わせとバランスで構成を考え、ラフに仕上げてみましたが、何かが足りません。何度も画面を見返してみましたが、決定的要素が足りないような気がしてならないのです。
老いてなお、背筋をピンと伸ばして暮らしていた、あの母のイメージを表現しきれていませんでした。凛とした佇まいは、母が80歳を過ぎて、放ち始めたいぶし銀のような輝きを支えるものでした。それが画面から滲み出ていなかったのです。
凛とした母の佇まいを表現するにはどうすればいいのか・・・、再び、画面を見つめ、シミュにレーションを繰り返した結果、要所要所に、白を散らしてみることにしました。
晩秋の湖畔の空気には、肌を刺すような厳しい冷たさがあります。その厳しい冷たさは、凛とした佇まいに通じるものがあり、晩節の象徴でもあるように思えました。それは白によってしか表現できないもののように思えました。
試みに、髪の際や逆光の粒子の中に、白を差し色として置いてみました。思いのほか、画面に輝きが生まれたことに驚きました。まさに、いぶし銀のような輝きです。これでようやく、納得できる画面になったような気がします。
気をよくして、さらに、顔や首の縁、その背後で煌めく残照の中に、そっと白を置いてみました。そうすると、不思議なほど見事に、晩節の母の輝きを表現することができました。予想以上の白の効果でした。
差し色として白を使うことによって、晩秋の冷たい空気の感触、母の凛とした生き方、いぶし銀のような輝きを表現することができたのです。
それにしても母はなぜ、80歳を過ぎた頃から、輝き始めたのでしょうか。カンヴァスに母のイメージを描いて見てようやく、なぜ、母が輝き始めたように見えたのか、多少、わかってきたような気がしました。
■母はなぜ、輝いて見えるようになったのか
80歳ともなれば、心身ともに衰えが目立つようになります。動きが鈍くなったり、物忘れがひどくなったり、老化に伴うさまざまな衰えが、心身に現れるようになります。輝きとは無縁になるのが一般的です。
それまでの自己肯定感を失い、アイデンティティ・クライシスに陥る人も多々、いると思います。
ところが、母の場合、80歳を過ぎてから、ひっそりとした輝きを見せるようになっていたのです。それが不思議でなりませんでしたが、今回、絵を描くために、当時の母を何度も思い返すうちに、その原因がなんとなくわかってきたような気がしました。
母の不思議な輝きは、おそらく、孤独感を昇華させることができ、新しいアイデンティティを獲得したから得られたものではないでしょうか。その頃、時折、母が見せていた孤高の佇まいを思い出します。
父が83歳で亡くなった時、母は75歳でした。その後、母はそのまま、大きな家で一人暮らしを続けていました。同じ敷地内に弟の家族が住んでおり、日常的に行き来があったので、私は心配していませんでしたが、アイデンティティが大きく揺らいでいたことは確かでしょう。
専業主婦として生き、外で働いた経験もない母は、家庭こそがアイデンティティの基盤でした。父の死後、その基盤が崩れてしまいました。子どもたちはとっくの昔に巣立って、それぞれの家庭を築き、残されたのが妻という役割でしたが、それも父の他界によって、喪失してしまいました。
世話をしてきた対象をすべて失ってしまったのです。
父を失った喪失感を、母はどのようにして補っていたのでしょうか。あるいは、大きな家で一人暮らしをするようになって、寂寥感をどのように紛らわせていたのでしょうか。当時、私は仕事に忙しく、慮る余裕がありませんでしたが、母はアイデンティティ・クライシスに陥っていたのではないかと思います。
ちょうど80歳を過ぎた頃から、母は、私が帰省するたびに、「お母さんが、この家を守る」と言うようになりました。確かに、長い廊下はそれまで以上に磨き込まれるようになっていましたし、いくつかある床の間にはいつも、何かしら花が活けられ、それに合わせて、掛け軸も取り替えられていました。
数年に亘るアイデンティティ動揺期を経て、母は、「家を守る」ことに、新たなアイデンティの基盤を見つけたように見えました。
日々、部屋を掃除し、庭を手入れし、仏壇に御仏飯や花を供えて、「家」の世話をすることに生き甲斐を感じるようになっていたのです。「家を守る」ことにアイデンティティの基盤を置くことによって、母はようやく、自分の居場所を見つけたのでしょう。
その頃から、母は不思議な輝きを見せるようになりました。
「家を守る」ということは、単に家を整え、綺麗にするということだけではありませんでした。家の対面を守り、先祖を守るという決意の表れでもありました。母にとってはむしろ、こちらの意味合いの方が強かったのかもしれません。
生身の人間との関わりが薄れても、母は日々、気持ちを通わせ、生きていることの意味を感じさせてくれる対象を見つけたのです。私は、母がついに孤独感を昇華し、孤高の精神へと変貌させていった感情と思考のプロセスを感じました。
思い返せば、ちょうどこの頃から、母がいぶし銀のように輝いて見えるようになったような気がします。
当時の母をイメージし、今回、作品化してみました。改めて画面を見て、思いのほか、的確に表現できたのではないかという気がしています。(2024/2/19 香取淳子)