2021年8月6日、近くのユナイティッドシネマで、『イン・ザ・ハイツ』を見てきました。その日も朝からうだるように暑く、うんざりするような気分でした。コロナ禍で外出もできず、適当な憂さ晴らしもできません。気だるく、何をする気にもならないでいるとき、ふと、夕刊で見た映画評の「熱いリズム」という言葉が脳裡をかすめました。
ずいぶん前に読んだはずですが、その言葉と写真だけは妙に鮮明に記憶に残っていたのです。タイトルと写真を見ただけで、記事を読んではいませんでした。確認してみると、その記事では、2021年7月30日、封切されたばかりの映画“イン・ザ・ハイツ”が紹介されていました。

(2021年7月30日、日経新聞より)
暑いさ中でも、人々は楽しそうでした。写真を見ているうちに、ミュージカル映画を見るのも悪くないなという気になってきました。映画館の大画面で、ノリのいい音楽とキレキレのダンスを見れば、きっと、暑気払い、コロナ払いもできるでしょう。
さっそく、ネットで座席をチェックすると、まだ相当、余裕がありました。朝1番のチケットをオンラインで購入すると、ようやく気持ちが落ち着きました。これで一安心、開始直前に映画館に着いても大丈夫です。
朝10時5分、映画は始まりました。
男が子どもたちを前に、「昔あるところに・・・」と話しだす冒頭シーンを見た瞬間、2年ほど前に見たミュージカル映画『アラジン』を思い出しました。この映画も、男が子どもたちに話しかけるシーンで始まっていたのです。それが、ちょっと気になりました。ミュージカルにお定まりのオープニングなのでしょうか?
そういえば、観客は日常生活を引きずったまま映画館にやって来ます。その観客の意識を手っ取り早く切り替え、現実世界から物語の世界へ誘導するための入り口なのかもしれません。音楽を積み重ね、繋いでいくミュージカルでは境界を設定しにくく、明らかにトーンの異なった導入部が必要なのかもしれません。
『アラジン』と同様、この映画も、エンディングとオープニングが対応したシーンで編集されていました。子どもたちに語りかけながら、主人公が過去の出来事を振り返り、現在の自分たちを語るという形式になっていたのです。
さて、子どもに語りかけるシーンから、場面は一転して、この物語が展開されるワシントンハイツに移ります。アップテンポの音楽を背景に、リズミカルなカット割りで構成されているので、観客はすぐにも作品世界に引き込まれていきます。
テンポの速いラップとキレの画面を見ているうちに、画面に合わせて身体を揺すり、リズムを取っているのに気づきました。私もいつの間にか、ラテンの「熱いリズム」に感染していたのです。コロナ鬱も暑気疲れもたちまち、どこかに吹き飛んでしまいました。
それでは、『イン・ザ・ハイツ』がどのような映画なのか、見ていくことにしましょう。
まずは、2分25秒のUS版予告映像(日本語字幕付き)をご紹介しましょう。
こちら → https://youtu.be/CxaMDJTbjKs
よく出来た予告映像です。ラップとヒップホップに絡め、映画の概要やエッセンスが的確に表現されています。この予告映像の展開に沿って、映画の概要やコンセプトを見ていくことにしましょう。
■映画の概要
たとえば、冒頭のシーン。主人公が子どもたちに向かって、「ある所にワシントンハイツという場所があった」と話し始めます。次いで、「ワシントンハイツの一日が始まる」という字幕とともにラップが流れ、主人公のウスナビが暮らす日常のエピソードが映像で綴られます。
消火栓の安全ピンを抜き、立ち上る水しぶきを浴びて大騒ぎする子どもたち、シャッターに落書きをする若者、追いかける主人公のウスナビ(コンビニ店主)など、住民の朝のルーティーンが短いショットで重ねられます。物語が展開されるワシントンハイツの日常が、断片的な映像を積み重ねて紹介されるのです。やがて文字だけの静止画になります。
「ミュージカルの金字塔「ハミルトン」の製作者がおくる」
『ハミルトン』とは、2016年に空前の大ヒットを飛ばしたミュージカル映画です。トミー賞、グラミー賞、ローレンス・オリヴィエ賞、ピューリッツア賞など、さまざまな賞を受賞しています。
この大ヒット作『ハミルトン』で、製作・脚本・音楽・作詞などを務めたリン・マニュエル・ミランダ(Lin-Manuel Miranda)が、この映画では原作・製作・音楽を担当していました。(※ https://theriver.jp/hamilton-release/)
だから、「ミュージカルの金字塔「ハミルトン」の製作者がおくる」なのです。最初にアピールすべきポイントだと担当者は考えたのでしょう。この文字だけの静止画の後、かき氷を載せた手押し車を引く男が現れます。
その映像に、「冷たい、かき氷はいかが」という字幕がかぶります。このかき氷売りに扮した男こそ、原作者のリン・マニュエル・ミランダです。

(ユーチューブ映像より)
再び、文字だけの静止画になります。
「傑作ミュージカルの映画化」
『イン・ザ・ハイツ』は、2005年に初演されたブロードウェイミュージカルで、リン・マニュエル・ミランダの出世作でした。当時、新境地を開拓した作品として、大きな話題を呼びましたが、なかなか映画化することができませんでした。それが今回、ようやく映画化されたのです。まさに、待望の「傑作ミュージカルの映画化」なのです。
もちろん、物語が展開されるワシントンハイツや登場人物なども、ラップとヒップホップに乗せて、生き生きと紹介されています。
■物語が展開する場所、主要な登場人物
いきなり、女性の足元をローアングルで捉えたショットが現れ、驚きましたが、美容院の経営者ダニエラ、そこで働くカルラ、クカなど3人の女性たちでした。
このショットに、「これは消えかけていたワシントンハイツの物語」という字幕がかぶります。
彼女たちは、ワシントンハイツの一角にあるウスナビの経営するコンビニに行く途中でした。毎朝、店に立ち寄り、ゴシップやちょっとした冗談を交わすのが、彼女たちの朝のルーティーンでした。

(ユーチューブ映像より)
次いで、コンビニの外側では、バネッサがニーナを見つけ、「天才のお帰りよ」と叫び、再会を喜びあう姿が映し出されます。
「天才」という言葉を聞いた時、一瞬、違和感を覚えました、映画では後になって説明されますが、ニーナは子どもの頃から成績がよく、この地区から始めて大学に進学した女性でした。地元の人々は誰もが彼女を誇りに思っていました。だから、バネッサも皮肉ではなく真心で、つい、「天才」と呼びかけてしまったのでしょう。
そのバネッサはケータイで不動産屋と話しながら、コンビニに入ってきます。それを見たベニー(タクシー会社の社員)とソニー(コンビニを手伝う従弟)は、ラップに乗って、軽快にやり取りしながら、ウスナビにバネッサにアタックしろとけしかけます。

(ユーチューブ映像より)
彼らに押されるように、ウスナビはおずおずと彼女に、「引っ越すの?」と話しかけます。バネッサは「審査が通れば、ダウンタウンへ」と答え、ちょっと誇らしげな表情を浮かべます。

(ユーチューブ映像より)
バネッサは意気揚々と、店から出て行ってしまいます。ウスナビは悄然とし、ベニーとソニーは手をたたいて笑い転げます。
このように、ウスナビが朝、店を開けた途端、待ちかねていたかのように、地元の人々がやってきます。買うのはたいてい、ペットボトルかコーヒー、新聞ですが、誰もが決まって買っているのが宝くじでした。
ウスナビにとっては母親代わりのアブエラも、店が開けば早々にやってきて、コーヒーを頼み、宝クジを買っていきます。彼女の口癖は「忍耐と信仰!」です。「毎日まじめに働いていれば」と、ウスナビや地元の人々を暖かく見守り、母親代わりとしてワシントンハイツになくてはならない存在になっていました。
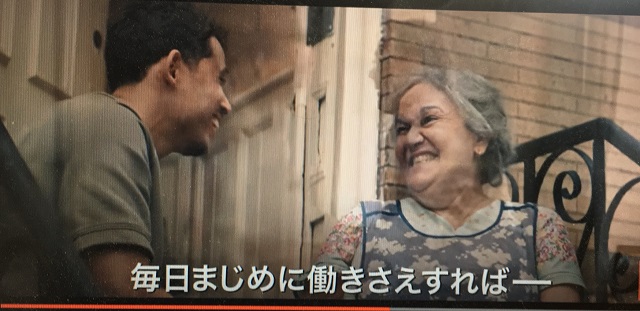
(ユーチューブ映像より)
慌てて駆け込んできたのが、ニーナの父親ケヴィン(タクシー会社の社長)です。彼はこの朝、普段よりも多く、20ドル分もの宝クジを買いました。

(ユーチューブ映像より)
これが彼らの日常なのです。こうして主要な登場人物たちの顔見せが終わったかと思うと、再び、文字だけの静止画になります。
「そこは“夢”が集う場所 N.Y.」
ニューヨーク市のワシントンハイツ地区には、ラテン諸国からの移民がコミュニティを形成していました。彼らはそれぞれ、大きな夢であれ、小さな夢であれ、さまざまな夢を抱いて暮らしています。遠路はるばるやって来たニューヨークは、彼らにとって、まさに“夢”が集う場所なのです。
■作品コンセプト
この作品のコンセプトの一つは、「夢」でした。登場人物たちはそれぞれ、何らかの夢を抱いていました。
たとえば、バネッサは美容院でネイリストとして働きながら、デザイナーになる夢を抱いていました。日々、デッサンをし、作品制作に挑んでいます。
こちら → https://youtu.be/r2AcTFu3rOs
(広告はスキップするか、×印を押して消してください)
お金に余裕のないバネッサは、ゴミ箱に捨てられた布切れを拾い集めては、嬉しそうな表情を見せます。この布切れがあれば、ミシンで縫ってアイデアを形にし、ファッションの勉強に役立てることができます。お金がないなりに、彼女は知恵と工夫で、しっかりと勉強を続けていたのです。
色とりどりの大きな布が次々と、ビルの屋上から垂れ下がってくるシーンでは、目を輝かせて見上げるバネッサのクローズアップが印象的でした。
そこに、「誰にも小さな夢がある」という字幕がかぶります。
ワシントンハイツの住民のほとんどは、ラテン諸国からの移民でした。彼らは故郷では暮らしていくことができず、生きていくためにニューヨークにやってきたのです。営々と働き、ラテン系コミュニティを築き上げ、貧しいながらも助け合って暮らしてきました。そんな彼らが貧困と差別の中で生き伸びていくには、心の支えとして夢が必要だったのです。
ニーナが帰って来たのを祝って開催されたパーティのさ中、突然、ワシントンハイツが停電してしまいます。暗闇の中で人々はパニックになり、ケータイを片手に、右往左往しながら街頭に出ます。

(ユーチューブ映像より)
大勢の人々が次々とビルから街頭に出てきます。すると、まるで人々の不安を打ち消すかのように、夜空に高く、花火があがります。
華麗に夜空を飾ったかと思うと、あっけなく消えてしまいます。そんな花火の儚さは、夢を抱きながらも、叶えられることのないラテン系コミュニティの住民を象徴しているように思えました。
こちら → https://youtu.be/aaFXc7SN8Ak
(広告はスキップするか、×印を押して消してください)
闇夜で花火を見上げる人々を捉えたショットには、「(夢を)叶えるには」という字幕が表示されます。
そして、美容院での光景、アブエラ(ウスナビの母親代わり)の後ろ姿を捉えたショットが続き、それらの画面に、「お金が必要だ」という字幕がかぶります。アブエラの声でした。
夢を抱いてニューヨークにやってきても、それを叶えるには、資金が必要でした。アブエラは長年、この街で暮らし、母親代わりとして、住民のさまざまな夢につきあって生きてきました。だからこそ、夢を実現するには、お金が必要だということがわかっていたのです。
アブエラは口癖のように、「忍耐と信仰」といいながら、毎日、ウスナビの店で宝クジを買っていました。
そのアブエラが停電の日、パーティのさ中に倒れてしまいました。異変に気づいたウスナビが枕元で「大丈夫?」と心配すると、「今日は一人じゃない、皆がいる」と穏やかに言い、「忍耐と信仰」といつもの言葉を口にしました。そして、そのまま、「暑い、暑い、燃えるよう」と言いながら、亡くなってしまいました。停電でエアコンも止まっていたのです。
停電はコミュニティにとって、いっときの危機でしたが、もう一つ、住民たちは大きな選択を迫られる危機に直面していました。ワシントンハイツが再開発の対象になっており、低所得層の彼らはやがて住めなくなるという危機に瀕していたのです。
夢を描き、未来に期待する一方で、彼らは差別と貧困という現実に曝されていました。個人では乗り越えることが難しい障壁でした。
■物語の背景
ワシントンハイツでは最近、再開発の動きがあり、不法移民の住民が強制退去させられそうになっていました。都市を効率よく活用するため、行政はこの地区に付加価値をつけ、新たに高級住宅地として生まれ変わらせようとしていたのです。
いわゆるジェントリフィケーション(gentrification:都市の再開発による居住空間の高度化)によって、ワシントンハイツの物価は高騰し、家賃は上がり、低所得層は暮らしにくくなっていました。
近所の商店は次々と店を閉じ、主人公のウスナビも、故国ドミニカに戻って父の遺した店を再開しようと考えるようになっていました。母親代わりのアブエラと従弟のソニーと共に、その夢を実現できればと、二人にはその思いを告げていました。故国に戻れば、貧しくても威厳を持って生きていくことができるはずです。
ところが、停電した日、あまりの暑さで高齢のアブエラが亡くなってしまいました。一方、生まれた時にここに移住してきたソニーは、自分の故郷はこのワシントンハイツだと言い張り、ドミニカには行きたくないと拒絶します。
ウスナビはにっちもさっちもいかなくなっていました。
コンビニの中から街頭を見るウスナビの目に、熱狂的に踊る住民たちの姿が映ります。窓ガラスに反映されたそのショットが見事でした。窓ガラス越しに街頭を見るウスナビの顔の周囲に、激しく踊る住民たちの姿が反射して映り込んでいるのです。そのショットに、「世界が回っているのに」という字幕がかぶります。
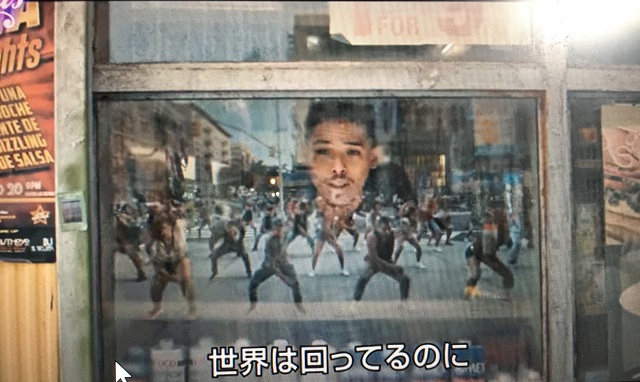
(ユーチューブ映像より)
ウスナビはすぐさま店から出て、街頭で集う人々の間に飛び入り、「僕たちがこの街で共に過ごせるのは」とラップで歌います。すると、ウスナビを捉えたショットに、「今夜が最後になるだろう」という字幕がかぶります。
熱情的に踊る人々を捉えたショットに、「僕たちを追い出すつもりだ」というウスナビのセリフ。次いで、ソニーがニーナに「僕たちも立ち上がろう」という場面になり、そして、熱狂的な群衆のダンスシーンが展開されます。
こちら → https://youtu.be/8YCC2kDsQ2w
(広告はスキップするか、×印を押して消してください)
ダンスシーンでは、誰もが生き生きとしています。まるで陶酔しているかのように、それぞれが身体をくねらせ、踊りに熱中しています。そのシーンの背後で、「威厳を持って生きるのよ」というセリフが流れます。アブエラの声でした。さらに、「世界に知ってもらうのよ」、「私たちのことを」というセリフが続きます。
ここに、この作品のもう一つのコンセプトが凝縮して表現されています。移民2世たちが抱く夢とその実現の間には、大きな乖離があります。それこそが現実で、ほとんどの場合、夢を果たすことができず、挫折してしまいます。それでも、威厳だけは持ち続けなければならないという年長者からの教えでした。
このシーンでは、ワシントンハイツの住民に迫る危機について説明される一方、ラテン系住民へのメッセージが込められていたのです。
まるで亡くなったアブエラが甦り、熱狂的に踊る彼らを励まし、諫め、そして、その巨大なエネルギーを方向づけようとしているかのようでした。
再び、文字だけの静止画になります。
「クレイジー・リッチ」監督ジョン・M・チュウ
■監督
この映画の監督は、台湾系アメリカ人ジョン・M・チュウでした。
彼は2018年に『クレイジー・リッチ』を製作し、アジア人をキャストにした映画ではじめて、大ヒットを記録しました(※ https://www.hollywoodreporter.com/movies/movie-news/weekend-box-office-crazy-rich-asians-wins-265m-1135824/)
ジョン・M・チュウは1979年にカリフォルニア州で生まれ、2008年、『ステップ・アップ2:ザ・ストリート』で長編映画の監督デビューを果たしました。以後、順調に製作経験を積み重ね、9本目となるこの作品も手堅くまとめられています。
興味深いのは、2011年に“Justin Biever : Never Say Never”、そして、2013年に”Justin Biever’s Believe”を製作していることでした。ヒップホップのカナダ人シンガーソングライターを題材に映画を製作していたのです。
試みに、“Justin Biever : Never Say Never”の予告映像を見てみることにしましょう。
こちら → https://youtu.be/4Bg8EuLT1ew
(広告はスキップするか、×印を押して消してください)
この動画からは、ジョン・M・チュウ監督がヒップホップに造詣が深く、ジャスティン・ビーヴァーの素晴らしさを的確に捉えて表現していることがわかります。その他の作品を見ても、作品が全般にリズミカルで、ハギレのいいカット割りで構成されているのが印象的です。
こちら → https://www.imdb.com/video/vi2816851993?playlistId=tt1702443&ref_=vp_rv_0
画面を見ると、映像と音楽、音響、パフォーマンスがそれぞれ絶妙にマッチしており、ラップやヒップホップでしか表現できない現代社会の深層を捉えることができていました。その手腕はこの映画でも存分に発揮されているといっていいでしょう。
さて、わずか2分25秒の予告映像でしたが、これまでご紹介してきたように、『イン・ザ・ハイツ』のエッセンスが凝縮して表現されていました。
ところが、残念なことに、この予告映像では、脚本家、そして、振付師については触れられていません。そこで、脚本家や振付師の考えがわかるようなインタビュー記事あるいは動画をネットで探してみました。
ようやく関連情報をいくつか見つけました。これらのインタビュー記事あるいは動画を通して、作品作りに際し、彼らがどのような点に気をつけたのかを把握していきたいと思います。
■脚本家
原作者のミランダは映画化に際し、脚本家のキアラ・アレグラ・ヒュデス(Quiara Alegría Hudes)のアイデアを取り入れたといいます。
彼女は、ラテン系コミュニティで常に話題になる「ドリーマー」と呼ばれる不法移民の若者問題を取り上げ、映画版では移民問題全般を強調しました。その一方で、都市再開発による低所得層の暮らしにくさにも踏み込んでいます。全般に、社会問題をベースにした作品構成になっています。
ヒュデスはインタビューに答え、次のように語っています。
こちら → https://ew.com/movies/in-the-heights-writer-quiara-alegria-hudes/
ヒュデス自身もミランダと同様、移民2世です。両親はプエルトリコから移民し、ニューヨークにラテン系コミュニティを築き上げた世代でした。意気投合した二人は2004年、共同でラテン系コミュニティをテーマにミュージカル脚本を執筆し始めました。それが、ブロードウェイミュージカル『イン・ザ・ハイツ』でした。
ヒュデスは登場人物の中ではとくに、ニーナやソニーに感情移入できるといいます。というのも、ヒュデスもニーナと同様、子どもの頃から勉学に励み、ラテン系コミュニティからはじめて大学教育を受けた世代だったからです。
しかも、ニーナと同様、名門大学を卒業しています。ニーナはスタンフォード大学という設定でしたが、ヒュデスはイエール大学で学士号を取得し、ブラウン大学で芸術学修士号を取得しています。
(※ https://en.wikipedia.org/wiki/Quiara_Alegr%C3%ADa_Hudes)
しっかりとしたストーリー構成にするため、ヒュデスは、映画版ではラテン系アメリカ人エリートであることを強調して、ニーナの役割設定をしたと語っています(※ 前掲インタビューURL)。
授業料の支払で親に経済的負担をかけることに悩むニーナは、追い打ちをかけられるように、学内でいくつか差別的待遇を受けます。ラテン系コミュニティからただ一人、名門大学に入学できたとはいえ、出自がラテン系コミュニティだということに変わりはありませんでした。入学早々、ニーナは厳しい現実を悟らされ、逡巡したあげく、退学を決意して帰郷していたのです。
興味深いのは、ニーナがワシントンハイツに戻ってくるなり、ダニエラの美容院に行って、ストレートヘアから生まれつきのカーリーヘアに戻したことでした。
こちら → https://youtu.be/UrFH772ytzM
(広告はスキップするか、×印を押して消してください)
ニーナはスタンフォード大学ではアイロンで伸ばしたストレートヘアにしていました。おそらく、ラテン系であることを隠そうとする心理が働いていたのでしょう。その抑圧された感情を晴らすかのように、ワシントンハイツに戻ってくると、彼女は早々に美容院に行って、元のカーリーヘアに戻します。ありのままの自分に戻したのです。
カーリーヘアになって自分を取り戻したニーナは、ダニエラたちに退学すると告げます。驚く彼女たちを後目にニーナは、なんとも爽やかな表情を見せて美容院を出ていきました。
一方、父親はニーナの学費を捻出するため、経営しているタクシー会社を売ろうとしていました。それを知ったとき、私の学費のためにこれまでやってきたことすべてを捨ててしまうの?と、ニーナは父親を厳しく問い詰めます。当然のことでした。
コミュニティの期待を一身に集めてきたニーナでしたが、念願の名門大学に入学すると、自分の居場所がわからなくなり、威厳さえも失いそうになっていました。そんな時、大きく浮上してきたのがウスナビの従弟ソニーでした。
ソニーといえば、ウスナビが故国ドミニカに戻って一緒に仕事を始めようと選んだ相手です。
ヒュデスは、そのソニーが、ウスナビがいつも故郷を懐かしんでいるといってなじるシーンを付け加えました。そして、僕はドミニカなんかに行きたくないよ、ここにいたい。このニューヨークこそ僕の故郷で、僕の居場所なんだからとソニーに言わせたのです。
さらに、‘96,000’の歌のシーンで、ソニーは、もし宝くじに当たって96,000ドルが手に入ったら、僕は自分のためには使わず、この近隣のインフラを改善し、よりよいWi-Fiを使えるようにしたいと宣言しています。つまり、ソニーはお金を手にしたら、自分たちのコミュニティに投資をし、生活環境の向上を図りたいといっているのです。
これらのシーンを加えることによって、ヒュデスは、しきりに故郷を懐かしむウスナビとは違って、不法移民とはいえ、ソニーの意識はアメリカ人なのだということを示します。
これは重要なポイントでした。
一口にラテン系アメリカ人といっても、プエルトリコ系、ドミニカ系、メキシコ系が混在しています。彼らの母語は英語かスペイン語かに分かれるのです。当然、アメリカへの思いも異なるでしょう。さらに、いつアメリカに移住したのかによっても、アメリカへの思いは異なります。そのような点を踏まえ、ヒュデスは、より現実に沿ったストーリー構成を考えたのだと思います。
プエルトリコ系移民2世であるヒュデスは、ラテン系の中ではいち早くアメリカに移住し、英語を使って暮らしていました。それだけに、そのプエルトリコ系と、いまだに故郷を懐かしみ、スペイン語を捨てきれないドミニカ系との違いに敏感でした。その差異を描かなければ、この作品のリアリティは欠けると思っていたのです。
もちろん、白人社会に対する移民の気持ちにも敏感でした。ヒュデスは諸々の微妙な文化の差異にこだわって製作に臨みました。
たとえば、ラテン系の映画評論家が、『イン・ザ・ハイツ』を取り上げた際、ニーナが帰郷した際はストレートヘアだったのに、すぐ元のカーリーヘアに戻したことに言及していました。それを知って、とても嬉しかったとヒュデスは語っています(※ 前掲インタビューURL)。
ニーナの髪の毛をどうするか、ヒュデスたちは時間をかけて検討したといいます。観客がどれほど気にするかわからないようなことでしたが、ヘアスタイルの変化は、ニーナの気持ちの変化、気持ちの立て直しをはっきりと示すシンボリックな表現だったのです。
脚本家がリアリティにこだわり、細部にまで真剣にチェックを入れたのと同様、振付師もリアリティにこだわっていました。
■振付師
振付師のクリス( Christopher Scott )が『イン・ザ・ハイツ』のダンスについて語っている7分30秒の動画があります。
こちら → https://youtu.be/KZJqV09DgcU
(広告はスキップするか、×で消してください)
興味深いことに、この映画はダンスと一体だとクリスは言っています。
たとえば、サルサはニューヨーク風のストリートなサルサを、ストリートダンスは、ライト・フィート、フレキシング、ポッピング、ブレイクダンスなど、それぞれの文化を表現しているさまざまな要素を取り入れたというのです。
さらに、ラテンといえば、サルサだけども、ブレイクダンスはアフリカ系だけではなく、プエルトリコ系やドミニカ系もあるといいます。抑圧された人々が、その気持ちをダンスに込めて表現していることを考えれば、ワシントンハイツの住民がライト・フィートを取り入れたように、映画にも新しいダンスを取り入れる必要があるというのです。
動画で見ると、ライト・フィートはヒップホップのようなものでした。
こちら → https://youtu.be/H9jC18XYXjQ
(広告はスキップするか、×で消してください)
クリスは、その種の文化の違いを理解しなければ、振付にも違和感が出てしまうといいます。監督もおそらく、同じような思いで製作に臨んだのでしょう。
彼はまず、監督が「ダンスからシーンを考えていった」と語っています。振付を撮影して監督に送ると、意見が戻ってきて、監督が音楽付きのストリートボードを作るのだそうです。だから、「どんなシーンになるか想像しやすい」とクリスはいいます。
なぜそうするのかについて、監督自身、「ダンスを通して物語が伝わるから」と理由を述べています。
クリスはジョン・チュウ監督とは約12年間仕事を共にしてきました。二人はおそらく、阿吽の呼吸で理解しあえる関係なのでしょう。
クリスは若い頃は振付のことだけを考えていたが、ジョン・チュウ監督がカメラにどう映るかを考えなければならないと教えてくれたといいます。お互いに影響し合い、領域を超えて、そのスキルを磨いてきたのでしょう。
一方、脚本家のヒュデスは、ダンスの「オーディションを見て、ラテン系の才能が集まっていて、誇らしかった」と述べています。クリスがスキルだけではなく、文化の理解、表現の幅などを考え、人集めをしたからでしょう。クリス自身、「世界のトップダンサーがNYスタイルのサルサを踊った」と言っているほどです。
実際、ダンスシーンのすべてが最高の出来栄えでした。
この映画では、才能溢れた振付チームの下、素晴らしい才能とテクニックを持ったダンサーたちが練習を重ね、渾身のパフォーマンスを見せてくれたのです。振付師のクリスがいろんなジャンルの最高のダンサーを集め、振付チームを結成して、指導してきたことの成果でした。
圧巻は、『Canaval Del Barrio』でした。下記の4分48秒の映像のうち、冒頭から2分23秒までがダンスシーンです。
こちら → https://youtu.be/ZDOVLEjbN4o
(冒頭から2分23秒まで。広告はスキップするか、×で消してください)
クリスは、このダンスシーンでは、ドミニカ系、メキシコ系、コロンビア系がそれぞれ違うスタイルで踊るよう振付をしたといいます。ですから、『Canaval Del Barrio』はラテン系それぞれの文化を象徴したダンスシーンといえるでしょう。
このシーンには、ラテン系コミュニティが一体となって立ち上がり、「世界にそのビートを響かせろ!」と訴えるウスナビの思いが凝縮されて表現されていました。
ラテン音楽やダンスは、スペイン人に征服された奴隷たちが、チャチャチャ、マンボ、ソンなどのリズムを生み出したという経緯があります。ですから、そのような歴史を踏まえたうえで、現在のラップやヒップホップ、ライト・フィートなどを取り入れ、クリスは慎重に、さまざまなダンスシーンを創っていったのです。
振付師クリスが求めていたのは、ジョン・チュウ監督、そして、脚本家キアラ・アングラ・ヒュデスと同様、リアリティでした。
それでは、『Canaval Del Barrio』の一端を見てみることにしましょう。
■『Canaval Del Barrio』
『Canaval Del Barrio』の迫力あるダンスシーンの中で、とくに引きつけられたのは、「旗を掲げろ」と名付けられた箇所です。主要登場人物たちの姿を画面のあちこちで見ることができます。ワシントンハイツの住民とともに立ち上がったのです。
こちら → https://youtu.be/bU3luTqDJeE
(広告はスキップするか、×で消してください)
ウスナビはソニーに向かって、「お前の言う通り、ここは無力な移民ばかり」と語りかけ、「街は消える運命で、今夜が集まれる最後かも」と続けます。画面にはニーナ、カルラの姿が見えます。
ウスナビはさらに、「でも、このまま引き下がるのか?」と問いかけ、「現実を嘆くより、俺は旗を掲げたい」と意思表示します。
この時、カメラは佇んでウスナビを見つめるバネッサをバストショットで捉え、次いで、ソニーに語りかけるウスナビ、そして、国旗を差し出す子どもの姿を捉えます。

(ユーチューブ映像より)
子どもたちが真剣な表情でウスナビを見守っています。ウスナビは、子どもの手から国旗を受け取ると、すぐさま、「旗を掲げろ!」と呼びかけます。音楽は次第に大きく、クレッシェンドで表現されます。この時、パフォーマンス、音楽のテンポとリズムで醸し出された画面の熱気が、観客にも直に伝わってきます。
建物と建物の間には、洗濯物と共に多くの国旗が吊るされています。故国への思いが人々の生活の中にしっかりと組み込まれていることがわかります。
「今夜こそ、声をあげるんだ!」とウスナビは続けます。画面にはバネッサの顔、ソニーの顔が見え、ウスナビを取り囲む輪が次第に大きくなっていくのがわかります。ウスナビはさらに高く国旗を振り上げ、「歌え、世界まで響かせろ」と皆をたきつけます。

(ユーチューブ映像より)
ウスナビの傍らにはいつの間にか、カビエラ、カルラ、クカがいて、激しく踊っています。周囲の皆も両手を振り上げ、ジャンプし、感極まった様子です。「皆の旗に魂を込めて」というセリフの下、人々を捉えた映像が流れます。ウスナビの言葉に陶酔したような表情で、大勢の住民が両手を上げ、身体を震わせ、激しく踊っています。

(ユーチューブ映像より)
この時、ワシントンハイツの住民は老いも若きも気持ちを通わせ、一体となっていたのでしょう。巨大な心のエネルギーが一気に爆発したような感じです。「あの橋を越え、世界へ、どこまでもビートは響く」というウスナビの言葉が力強く、リアリティを帯びて響き渡っています。
まさに、クライマックス。皆の気持ちが一つになった瞬間でした。
次いで、「この前のことは忘れて、最後に踊ってくれ」とウスナビはバネッサの手を取ると、曲は転調し、二人は静かに踊りだします。これが、冒頭で紹介した日経新聞の夕刊で見た写真のショットです。周囲の人々は暖かく二人を見守りながらも、陽気にはやし立てます。
■米国ラテン系コミュニティにみる格差社会の縮図
わずか1分31秒のこの動画からは、ラテン系コミュニティの住民がこれまで大きく声をあげることなく暮らしていたことがわかります。差別に悩み、貧困にあえぎながらも、彼らは大規模な抗議行動をすることもなく、ダンスや音楽で積もる思いを発散させながら生きてきたのです。
それが、今、ウスナビの旗振りの下、大勢が集まり、それに大きく呼応したのです。歌って、踊って、故国の旗を掲げ、自分たちの存在を世界に知らせようとしはじめたのです。
再開発で追い詰められてようやく、ワシントンハイツの住民は声をあげようとし始めました。それもラテン系の人々らしく、音楽とダンスに乗せて、陽気に楽しく、自分たちの存在を世界に知らせようとし始めたのです。
見ていて、思わず、涙が流れそうになりました。
この映画で語られていることは、何もラテン系コミュニティに限ったことではありません。あらゆる社会に通じます。いってみれば、現代社会の課題とでもいえるようなものが、ラップやヒップホップ、ライト・フィートに乗せて、明るく陽気に提起されていました。
かつては地域に根付いた独自文化の下で、人々は身の丈に合った豊かさを享受しながら生きていました。ところが、グローバル化の進行によって、いつの間にか、富める者はますます富み、貧しい者はますます貧しくなるという構図が定着してしまいました。
生産性の低い国や地域の住民は生きていけなくなり、故国を捨て、故郷を捨て、豊かな国や都市に移住せざるをえなくなっているのが現状です。その結果、地域との絆が途絶え、人との関係も途切れ、現代社会の人々は誰もが、一粒の砂のように、孤立し、無力になっています。
この映画で取り上げられたラテン系コミュニティを取り巻く諸問題は、現代社会が抱える構造的な問題だといっていいでしょう。
人と人を繋ぎとめるものがなくなりつつある一方、アブエラがいうように、何をするにも、「お金が必要」になってきています。その結果、マネタイズできるものが価値を持ち、そうではないものが価値をもたないという仕組みがあらゆる領域に浸透しています。
果たしてこれでいいのでしょうか。
『イン・ザ・ハイツ』では、ダンス、音楽、ストーリー、映像、それぞれが見事に絡まり合い、ラテン系コミュニティが抱える問題が的確に捉えられていました。格差社会の縮図ともいえるワシントンハイツを舞台に、カリビアン・ディアスポラの魂が見事に表現されていたといえるでしょう。それだけに、その背後に流れる重い課題を受け止めざるをえませんでした。
この作品のキーワードは、夢、都市再開発、移民、宝クジ、エリート、差別と貧困、故郷などです。ところが、今回、それらを十分に組み込んで表現することができませんでした。とくにストーリーとダンスシーンとの関係については不十分なまま、書き終えてしまいました。改めて、書いてみたいと思っています。(2021年8月30日 香取淳子)