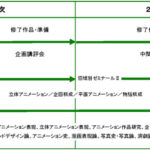■Yoo Youngkuk氏の「生誕100年記念展」
昨年末、用事があって、ソウルに出かけました。ついでに美術館に立ち寄ってみようと思い、ネットで検索すると、ソウルの国立現代美術館で、Yoo Youngkuk氏の生誕100年記念展が開催されていました。開催期間は2016年11月4日から2017年3月1日までです。
ずいぶん長い開催期間ですが、Yoo Youngkuk氏の作品をまとめて見ることができる貴重な機会かもしれません。Youngkuk氏のことを知っていたわけではありませんが、たまたまその時、展覧会が開催されていたので、訪れてみたのです。
当時、ソウルは反朴デモが激しく、光化門広場にはデモ隊のテントが多数、並び、朴大統領、サムソン副会長、KIA会長らの像が攻撃の的になっていました。曇天の下、栄誉をきわめたヒトたちの末路が哀れでした。
いま、韓国の政治状況はさらに混沌とし、朝鮮半島全体が不穏な状況に陥っています。日々、報道されるニュースを見ていると、昨年末のソウルの状況を思い出し、ヒトの世の移り変わりの激しさに無常を感じてしまいます。
あれからだいぶん時間が経ってしまいました。ようやくいま、Yoo Youngkuk氏の生誕100年記念展を振り返ってみる時間の余裕ができました。当時を思い起こしながら、作品紹介をしていきたいと思います。
さて、ソウル国立現代美術館はなかなか風情のある建物でした。それもそのはず、この美術館は1938年に韓国で初めて建築された石造りの建物・徳寿宮石造殿の中にありました。徳寿宮に入り、石造殿に向かって庭園を歩いていると、知らず知らずのうちに、都心の喧騒から離れ、静かで落ち着いた気持ちになっていきます。
会場に入ると、案内リーフレットがハングル表記でしたので、残念ながら、言葉から作品理解の手がかりを得ることができませんでした。しかも、具象画ではなく抽象画です。それこそ、何の手がかりもなく、色彩と形、質感といった非言語的要素と直に向き合うことになりました。
もっとも、それだけに、Youngkuk氏の作品の本質を鑑賞することができたといえるかもしれません。これまで抽象画はこれまでよくわからなかったのですが、ある時期のYoungkuk氏の作品には強く心に訴えかけるものがあったのです。
実は、Youngkuk氏が抽象画家だということも知らないまま、たまたまその時期開催されていたので、展覧会に出かけたのでした。帰国してからネットで検索すると、日本語でこの展覧会が紹介されていることがわかりました。
私が見た展覧会のタイトルは「絶対と自由」であること、「Yoo Youngkuk」は漢字で「劉永国」と表記されることをこのサイトで知りました。
こちら →
https://www.mmca.go.kr/jpn/exhibitions/exhibitionsDetail.do?menuId=1010000000&exhId=201611090000504
■Youngkuk氏と日本の抽象画家
1916年に韓国で生まれたYoungkuk氏は1935年、東京の文化学院に入学して絵画を学んだそうです。その後、1938年には第2回自由美術家協会展で協会賞を受賞し、その会友になったといいます。いずれも上記のサイトで知りました。
さらに、ここではYoungkuk氏が長谷川三郎氏や村井正誠氏などとともに、当時、抽象絵画の領域でリーダー的存在であったと記されています。長谷川三郎氏といえば、現代抽象絵画の先駆者といわれている画家です。そして、村井正誠氏もまた抽象絵画の草分けの一人とされています。はたして、そのようなことがあるのでしょうか。Youngkuk氏は当時、まだ22歳ごろです。
そこで、興味半分に、長谷川三郎氏や村井正誠氏の側からYoungkuk氏について調べてみました。その結果、両画家のいずれのプロフィール記事にもYoungkuk氏について記載されていませんでした。ただ、Youngkuk氏との関連を示す事柄がまったくなかったということもできません。ひょっとしたら、関連はあったかもしれないと推測できる程度の事実は多少、記されていました。
たとえば、長谷川三郎氏については、村井正誠氏らとともに1937年、自由美術家協会を結成したこと、抽象主義絵画の発展に尽力したことがわかりました。
こちら →http://www.tobunken.go.jp/materials/bukko/8921.html
また、村井正誠氏については、長谷川氏とともに自由美術家協会の結成に参加したこと、1938年に文化学院の講師になったことなどがわかりました。
こちら →http://www.tobunken.go.jp/materials/bukko/28143.html
いずれもYoungkuk氏のことは書かれていませんが、これらの情報をつなぎ合わせると、当時、文化学院で学んでいたYoungkuk氏と、そこで教えていた村井氏との接点はあったと考えられます。つまり、Youngkuk氏は文化学院で村井氏に学び、抽象画の世界に親しんでいったのでしょう。
一方、長谷川氏は欧米で3年間、絵画を学んで帰国した後、積極的な創作活動を展開していました。村井氏もまたフランスで4年間学んだ後、日本で新しい時代の美術活動を展開していました。両氏とも欧米の新しい絵画動向に触れ、さまざまな刺激を受けて作品を発表していたのです。両者が意気投合し、新しい芸術活動を展開していくとき、村井氏が学生であったYoungkuk氏を伴っていた可能性が考えられます。
彼らが当時、何歳であったかというと、Youngkuk氏が受賞した1938年、村井氏は33歳、長谷川氏は32歳、そして、Youngkuk氏は22歳でした。ですから、年齢の面からみても、彼が当時、日本で抽象画のリーダー的存在であったとは考えられません。師としての村井氏や長谷川氏に従って、彼らが展開する新しい芸術活動に参画していたという程度のことでしょう。ですから、先ほどのサイトの記事は明らかに、Youngkuk氏の箔付けのための誇大表現といえます。
ただ、実際にYoungkuk氏の作品を見てみると、どれも素晴らしいものばかりでした。とてもピュアで、時代を経ても色あせない、モダンな美しさに満ちていました。とくに、色彩の取り合わせが巧みで、強く印象付けられました。
■第2コーナーで見た印象深い作品
会場では作品が年代別に、4つのコーナーに分けて展示されていました。おかげで、Youngkuk氏の創作活動の変遷過程をつぶさに追うことができました。山をモチーフにした作品が多かったのですが、その捉え方、描き方の変容から、Youngkuk氏の創作活動の推移を見ることができました。
私がもっとも惹きつけられたのは、第2コーナーに展示されていた作品です。ここでは1960年から1964年に制作された作品が展示されていました。
たとえば、1960年に制作された「山」という作品があります。
こちら →
(油彩、136×211㎝、1960年、図をクリックすると、拡大します。)
抽象的な画面構成でありながら、木々のリアルな実在が感じられます。さまざまな種類の木々、岩石、草木、生態系としての山が色鮮やかに描かれています。遠景には白い木々、中景にはカーブを描くように散らされた鮮やかな赤、そして、近景に配置されたのが、左下の緑と、右下の茶です。それらの色が暗い画面の中で、快い緊張関係を保ちながら、配置されています。その緊張関係がシャープで、とても都会的で、洗練された絵柄になっています。
同じ時期に描かれた、やはり、「山」というタイトルの作品があります。
こちら →
(油彩、キャンバス、136×194㎝、1961年、図をクリックすると拡大します。)
この作品は、上の絵と同様の発想で描かれています。ところが、こちらは白の部分が多く、画面のほぼ半分を占めています。その結果、同じ「山」でも表情がやや異なってきます。白い木々を支えている白い基層部分が大きく描かれているせいか、上の「山」よりも、さらに山肌に近づいている印象があります。
この作品もやはり、抽象的な画面構成でありながら、山の息吹すら感じられるリアリティがあります。さらに、この作品は、洗練された印象を損なわないまま、どっしりとした山の土臭さ、力強さを感じさせます。不思議なことに、この絵には、洗練と土着という相反する要素が混在しているのです。
それにしても、なぜ、私はこの絵に相反する要素があると思ってしまったのでしょうか。ひょっとしたら、それは、この画面で大きな比重を占める白の使い方が繊細で、微妙なリズムがあり、それが岩山の鼓動すら感じさせてくれているからかもしれません。繊細さと無骨さが感じられるからこそ、そのような相反性を察知してしまったのでしょう。とても魅力的な作品です。
さて、同じ第2コーナーに「作品」というタイトルの絵があります。
こちら→
(油彩、キャンバス、130×194㎝、1964年、図をクリックすると、拡大します。)
会場で見たとき、鮮やかな赤が印象的でした。よく見ると、赤の補色である緑が効果的に使われています。赤い半球のようなもの(りんご?)の横には緑の葉が散るように描かれ、画面に流れを作っています。
そして、赤の半球の上にも暗い緑の葉のようなものが配され、上方には明るい緑色の帯が太く横一線に描かれています。緑がかった暗い画面の中で、半分のリンゴが逆さまになっている形状の赤が、いっそう際立っています。
この作品にも、色彩の取り合わせの妙味があって、惹きつけられます。赤と緑、オレンジといった具合に、使われている色数が少なく、それだけに、それらの色をきめ細かく使いわけながら、画面構成、モチーフの配置を考えられたのでしょう。色彩を制限する中で究極の美しさが追求されていることがわかります。
このコーナーの作品にはいずれも華やかさがあって、強く印象付けられます。
■いまなお新鮮なYoungkuk氏の世界
思えば、この展覧会はYoungkuk氏の生誕100年を記念して開催されたものでした。それなのに、どの作品をみても決して古びていません。いまなお新鮮な輝きを放っているのが、不思議でした。
たとえば、第1コーナーで展示されていた作品に、「山」というタイトルの絵があります。
こちら →
(油彩、100×81㎝、1957年、図をクリックすると、拡大します。)
緑と青、黒を基調にした画面に、太い黒の線で一筆画きのような、シンプルな形状がいくつも描かれています。山を構成する木々、草木、岩石などが表現されているのでしょう。シンプルで平面的な構成の中にモダンなテイストが感じられます。下方には、さり気なく、明るい緑の上にオレンジの線が描かれており、アクセントとして効いています。
第3コーナーにも、やはり、「山」というタイトルの作品が展示されていました。
こちら →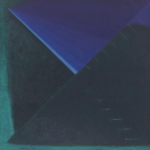
(油彩、135×135㎝、1968年、図をクリックすると、拡大します。)
この作品では、線によって形状を表現するのではなく、三角の組み合わせで「山」が表現されています。線を使わず色彩で形状が表現されていますから、境界線の色遣いが重要になってきます。その観点からこの絵を見ていくと、左側の三角の境界線が水色で描かれ、その先は紫のグラデーションで塗られています。まるで、夜空の下での山並みが目の前に浮かんでくるようです。
一方、その同じ三角の左側の境界線は緑色のやや太く描かれています。ですから、夜空とはいえ、もう明け方に近いのでしょう、うっすらと木々の色が浮き上がってきているようです。
Youngkuk氏の作品はいずれもこのように、抽象画といいながら、このように見る者の想像力を刺激し、リアルな実在を感じさせるところに妙味があるのではないかと思いました。この作品もまた、平面的な構成でありながら、奥行きを感じさせ、快いリズムを感じさせてくれます。
私はこれまで抽象画はあまり見たことがなかったのですが、今回、ソウルではじめて、Youngkuk氏の作品を見て、抽象画ならではの永遠性、洗練されたモダンを感じました。私が好きなのは第2コーナーに展示されていた諸作品ですが、この時期の作品にはどれも、洗練された華やかさがあります。
なぜなのでしょうか。
そこで、手がかりを得るため、Youngkuk氏の展覧会を案内するサイト(前掲)から、彼の来歴を見ると、この時期、Youngkuk氏は韓国で現代美術を志向する若手の画家たちから尊敬されていたようです。だから、半ば、求められるように、彼は、若手を牽引し、抽象と前衛を標榜した運動を積極的に展開していたのでしょう。
そのような事実を知ると、あの時期の作品に感じられる溢れるような才気とエネルギーは、Youngkuk氏が未来を思考する若い人々に囲まれ、現代美術の理論と実践を追求していたからではないかと思えてきました。
第2コーナーに展示されている諸作品には、独りで創作している際には生まれるはずのない、他人を意識した煌めきのようなものがあったのです。私はそこに惹かれたのでした。
その後、彼はグループ活動をやめ、一人で籠って、創作活動に専念するようになります。当然のことながら、作品の雰囲気も変化していきます。第3コーナー、第4コーナーの作品には、第2コーナーのような煌めきは見られませんでした。もちろん、第1コーナーの作品にもありません。
こうしてみてくると、単独で行っているはずの創作活動にも、実は他人の影響が及んでいるということを思わないわけにいきません。このこともまた、Youngkuk氏の展覧会を見て得ることができた発見の一つといえるでしょう。(2017/4/17 香取淳子)