■「わが青春の上杜会」開催
神戸市立小磯記念美術館で、いま、「わが青春の上杜会」展が開催されています。開催期間は2020年10月3日から12月13日までなので、関西に出かけたついでに立ち寄ってみました。
阪神電車の魚崎駅で六甲ライナーに乗り換え、アイランド北口駅で下車すると、すぐでした。六甲アイランド公園を神戸市立小磯記念美術館に向かって歩いていると、「わが青春の上杜会」展のポスターが掲示されていました。

下っていくと、右側に瀟洒な建物が現れてきました。これが小磯記念美術館です。

この美術館は、神戸で生まれ、神戸で制作を続けた画家・小磯良平氏を記念し、神戸市が1992年に設立したものです。
小磯氏は1988年12月に亡くなりましたが、その翌年、遺族から、油彩・素描・版画などの約2000点の作品とともに、アトリエや蔵書、諸資料が神戸市に寄贈されたといいます。神戸市はそれらの作品をただ保存するだけではなく、さらに作品の収集に努め、現在、約3200点もの作品を所蔵します。そのような経緯を知ると、この美術館が、「神戸市立小磯記念美術館」と命名された理由がわかります。

美術館の中庭にはアトリエが移築されていますから、そこで、小磯氏の制作情景を偲ぶことができます。作品を鑑賞するだけではなく、作品を生み出した場所を見て、作品化の過程を追うことができるのです。芸術を鑑賞する醍醐味を徹底的に味わうことができるのです。
美術館は年に数回、展覧会を開催して、作品の入れ替えを行っています。その上、小磯良平氏に関する特別展も開催しています。今回の展覧会「わが青春の上杜会」はその特別展の一環でした。
それにしても、「上杜会」というのは、どういう意味なのでしょうか。最初、聞きなれない言葉に戸惑いました。サブタイトルが「昭和を生きて洋画家たち」となっていますから、昭和に活躍した洋画家たちの作品が展示されるのだろうということはわかりますが、それ以外は皆目わかりません。
パンフレットを見ると、「上杜会(じょうとかい)は、東京美術学校始まって以来の“秀才揃い”と称された1927年卒業生が、若き情熱を持って結成した美術団体です」と書かれています。これで、「上杜会」が美術団体の名前だということがわかりました。
■上杜会とは
その後の説明を読み、「上杜」が、東京美術学校(現在;東京芸術大学)のあった「上野の杜(森)」にちなんで名づけられたことがわかりました。つまり、東京美術大学西洋画科を1927年に卒業した人たちのグループ名だったのです。
パンフレットには、「東京美術学校始まって以来の“秀才揃い”」と書かれています。どうやら、その秀才たちが互いに刺激し合い、しのぎを削り合って、力を向上させていったようです。
神戸市立小磯記念美術館の高橋佳苗氏は、小磯良平氏の次のような言葉を紹介しています。
「油絵(科)はよう勉強した。好きで好きでしょうない連中ばっかりや。自分の技術は生半可なくせして、理想が高いからお互いに容赦せん。なんちゅうたかて、友だちの影響は大きい」(図録『わが青春の上杜会』、p.24)
小磯氏が懐古していたように、当時、西洋画科の学生たちは、とてもよく勉強したようです。絵が好きでしょうがないから、制作技法にしろ、題材にしろ、議論し合い、遮二無二勉強したのでしょう。
小磯氏の言葉からは、秀でた能力を持つ若者たちが理想を高くかかげ、切磋琢磨し合いながら、創作に励んでいた様子がうかがえます。
小磯氏が「友だちの影響は大きい」と指摘していたように、優秀な学生たちは容赦なく相手の作品を批判しました。批判された側は、それに発奮してさらに努力するといった具合で、制作のための好循環が生まれ、メンバーの能力が飛躍的に向上していったのでしょう。
それを証左する事例があります。
東京美術学校に1922年に入学した学生たちは、当時もっとも権威のあった「帝国美術院美術展覧会(帝展)」に、次々と出品していました。
たとえば、小磯氏は、先に帝展に入選した同級生たちから刺激を受け、1925年の第6回帝展で初入選し、1926年の第7回帝展で特選を獲得しました。その小磯氏の刺激を受けて、第7回帝展に猪熊弦一郎氏、矢田清四郎は入選といった具合でした。
このように華々しい活躍を展開する同級生たちは、互いのつながりこそが創作の源泉になることがわかっていたのでしょう、卒業の一年前に、美校中退者や留学生を含め44人の同級生によって「上杜会」が結成されました。
青春の真っ只中で結成されたクリエイティブ集団でした。入学した1922年から卒業の1927年までの間、彼らは相互に刺激を受け合いながら学び、創作家としての孵化期間を過ごしていたのです。
■展覧会の構成
展覧会は、「上杜会」の結成を序とし、その後のメンバーの活躍を、①昭和2年から昭和11年(1927-1936)、②昭和12年から昭和20年(1937-1945)、③昭和21年から平成6年(1946-1994)の三部構成で組み立てられていました。
同窓で切磋琢磨し合った若者たちが、上杜会を結成しました。メンバーがその後、どのように才能に磨きをかけ、それぞれの人生を切り開いていったのか、折々にどのような作品を残していったのか等々、長いスパンで画家の人生と作品を把握できる構成になっていました。
上杜会のメンバーが、どのような人生行路を歩んできたのか、大きな時代の節目で創作家としてどう対処し、どのような作風を築き上げていったのか、同窓という観点から構成されていたので、作品をさまざまな観点から、立体的に鑑賞することができ、とても興味深い企画でした。
展示作品を一覧して、惹かれたのは、小磯良平氏、猪熊弦一郎氏、犬丸順衛氏、牛島憲之氏、高野三三男氏、岡田謙三氏、矢田清四郎氏などの作品でした。このうち、最も若くして亡くなったのが、犬丸順衛氏(1903-1939)で享年35歳でした。最も長寿だったのが、牛島憲之氏(1900-1997)で97歳です。
同窓でありながら、寿命という点では60年以上の開きがあるのです。
興味深いことに、美校在籍時は両者とも、岡田三郎助教室に所属していました。青春の一時期、共に濃密な時を過ごしたというのに、一方は早く世を去り、他方は東京芸術大学で後進を指導したばかりか、1983年には文化勲章まで受章しています。運命を感じずにはいられません。
まず、この両者の作品から見ていくことにしましょう。
■犬丸順衛:「永眠―父市郎次」
会場でこの作品を見たとき、とても印象深く、しばらく佇んで見ていました。死に顔が描かれているというのに、不思議なほど穏やかに、しかも、尊厳を持って描かれているように思えたからでした。

(油彩、カンヴァス、50.5×60.4㎝、1926年)
目を閉じた顔になんら迷いはなく、苦しみも感じられず、ひたすら静謐感が漂っています。しかも、額と顔の右側が明るく描かれているせいか、光に包まれて、安らかに昇天している途中のようにも見えます。柔らかな光の下、威厳を失わず、ただ眠っているだけのように描かれているところに、父を慕い、敬う犬丸氏の気持ちが透けて見えます。
父が旅立ったのは、犬丸順衛氏が23歳、美校の最終学年を迎える年でした。
絵筆を走らせながらも、静かに永遠の別れを受け入れようとしていたのでしょう。この作品には、悲しみを乗り越えようとする犬丸氏の悟り、あるいは、達観といったようなものが感じられます。心の奥深く語りかけてくるような作品でした。
■牛島憲之:「炎昼」
会場でこの作品を見たとき、対象の捉え方になんともいえない斬新さを感じました。

(油彩、カンヴァス、121.0×60.5㎝、1946年)
モチーフすべての境界が曖昧で、朦朧としており、捉えどころがありません。画面いっぱいに描かれた蔓性の植物がいったいどこから生えてきて、どこまで伸びているのかもわかりません。ぶら下がった白い実も同様、まるで周囲の空気に溶け込んでいるかのようにぼんやりと描かれています。
一方、後ろの方に見える電柱は淡い色彩で描かれていますが、境界がはっきりしているので、小さくても存在感があります。遠方の小さな電柱が、大きく描かれた蔓性の葉と実と拮抗するパワーを持っているのです。
この作品では全般に、近景のモチーフは大きく描かれているのですが、境界が曖昧で、色彩のコントラストも低く、存在感は希薄です。遠景のモチーフも周囲との色彩のコントラストは決して高いとはいえません。
ところが、境界がはっきりと描かれているので、視認性が高く、存在感があります。そのせいか、なんの変哲もないモチーフなのに、ストーリー性が感じられます。全体にぼんやりとした色調の中で、近景と遠景のモチーフの描き分けに妙味があります。
これは1946年、牛島氏が46歳の時の作品です。色合いといい、構図といい、なんともいえない魅力があって、長く見続けていても飽きることがありませんでした。見たものをそのまま描くのではなく、いったん内省化し、改めて作者の観点から組み立て直して、表現しているところに創意が感じられるからでしょう。
細い線を部分的に取り入れることによって、独特の雰囲気を醸し出している作品がありました。洗練された雰囲気に惹かれました。岡田謙三氏の作品です。
■岡田謙三:「窓辺(ノクターン)」
窓辺で女性が二人、座っています。左側の女性は目を閉じ、肩ひじを窓枠に乗せ、何かに聞き入っているようです。ノクターン(夜想曲)でも聞いているのでしょうか。右側の女性は今にも立ち上がって、踊りだしそうです。
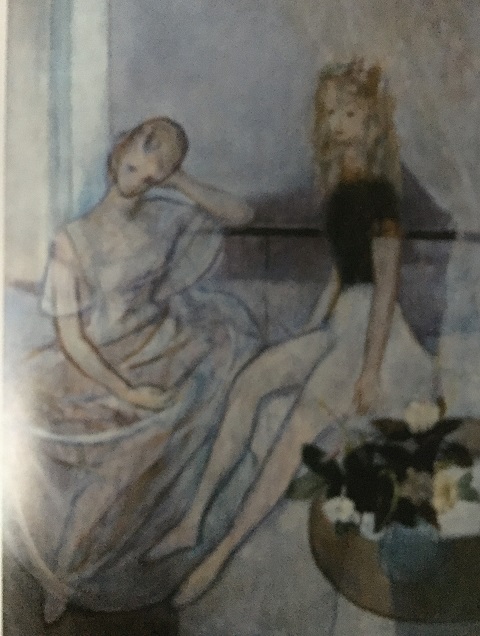
(油彩、カンヴァス、193.8×145.5㎝、1948年)
この作品を見て、まず気づくのは、随所に細い線を書き込み、モチーフに動きと表情を加えていることです。
左側の女性の傾いた頭部、そして、右側の女性の片側のフェイスライン、細い線を描き込んだだけで、その場の状況や顔の表情、感情までも表現できています。衣服や身体についても同様、細い線を要所、要所に描き込むだけで、身体の動きや構造、衣服の質感を表現することができています。
不透明な淡い色調の画面からは、二人の女性が窓辺で過ごす午後のけだるさが伝わってきます。都会的な物憂さと繊細さが表現されています。
これは1948年、岡田謙三氏が46歳の時の作品です。
岡田氏は東京美学校を中退し、パリで学んでいます。そう言われて見ると、画面の色調といい、モチーフといい、いかにもフランス的なシャレた感覚が画面全体に満ち溢れています。
この岡田氏を誘って1924年、共に中退してパリに遊学したのが高野三三男氏でした。彼もまた日本人画家には見られない作風の作品を手掛けています。
■高野三三男:「人形を持ったパリジェンヌ」
金髪の女性が目を閉じ、赤いマニキュアを塗った指で人形を軽くつかんでいる様子が描かれています。いかにもパリジェンヌといった感じの、優雅でオシャレな女性です。

(油彩、カンヴァス、65.5×4.5㎝、1924-50年)
全体に淡い色調でまとめられている中で、女性の真っ赤な口紅、金髪の巻き毛がひときわ目立ちます。典型的な西洋の女性美が描かれているのです。1924年から40年にかけて制作されたことになっていますが、おそらく、パリに出かけたときに描き始め、完成させたのが、その十数年後ということになるのでしょう。
なぜ、そう思うのかといえば、高野氏が1937年に制作した「ヴァイオリンのある静物」の中で描かれた女性が、この「人形を持ったパリジェンヌ」で描かれた女性とそっくりなのです。金髪巻き毛の様子、真っ赤な唇、長いまつげ、透明感のある肌といった要素が驚くほど似ています。ということからは、高野氏がパリジェンヌという女性像をこのころに完成させたことが示されています。
この作品で描かれているのは、都会的で、ちょっと傲慢なところがある一方で、完璧な美しさを心掛けるという女性の類型です。「人形を持ったパリジェンヌ」は、画面全体が淡い色調で収められているせいか、都会的で、洗練された優雅さが感じられ、惹かれます。
パリに長く滞在していなければ、決して、このような作品を描くことはできないでしょう。この作品から浮き立ってくるのが、典型的な西洋の女性美の一つでした。
一方、昭和初期の日本の女性美を過不足なく描いたのが小磯良平氏でした。
■小磯良平:「T嬢の像」
第7回帝展で小磯氏が特選を獲得したのが、「T嬢の像」でした。

(油彩、カンヴァス、116.8×91.0㎝、1926年)
着物を着た女性が手を組み、椅子に座っています。視線は窓の外に向けられ、何かに思いを馳せているように見えます。肌の艶、手指の繊細な表現、着物の質感など、見事な表現力です。華奢な女性が醸し出す嫋やかな風情、憂いを含んだちょっと寂し気な表情などが丁寧に捉えられています。日本の女性美の典型の一つといえるでしょう。
これは小磯氏が23歳の時の作品です。上杜会のメンバーで、最も早く帝展に入選したのは永田一脩と中西利雄でした。小磯氏は彼らの刺激を受けて発奮し、第6回帝展で入選しました。ですから、入選した翌年に特選を受賞したことになります。小磯氏は、藤島武二教室に所属していました。
小磯氏が特選を受賞した1926年に帝展に初入選したのが、猪熊弦一郎氏の「婦人像」と矢田清四郎氏の「足拭く女」でした。藤島武二教室の猪熊弦一郎氏が24歳、岡田三郎助教室の矢田清四郎氏は26歳でした。上杜会のメンバーが次々と入選していたのです。
それでは、両者の作品を見ていくことにしましょう。
■矢田清四郎:「足拭く女」
珍しく、裸婦像です。一見、模写かと思いました。

(油彩、カンヴァス、116.7×90.9㎝、1926年)
それほど当時の日本人女性には珍しく均整の取れた体つきでした。そのポーズも日本人らしくありません。
左腕を椅子の縁に置いて身体を支え、右手で足裏を拭いています。日常生活で見かける光景ですが、そこに意図しない美しさがにじみ出ています。足裏を掴んだ腕と身体の側面が三角形を型作り、安定感と適度な揺らぎのある構図になっています。
左上の壁には小さな鏡が掛けられており、女性の後頭部と肩の一部が映っています。こもモチーフを加えることによって、空間の広がりと奥行きを感じさせるだけではなく、メインモチーフを生活実態のある女性像に仕上げる効果を生んでいます。
背後に鏡を設定することによって、うつむき加減の女性の表情が、ことさらに印象づけられるからでしょう。そして、想像力がかきたてられます。バランスの取れた構図で品よくまとまっており、ありふれたものの中に見出された美しさとでもいえるようなものが感じられました。
■猪熊弦一郎:「馬と裸婦」
猪熊弦一郎も1926年、「婦人像」で帝展に入選しました。ところが、その作品は今回の展覧会で展示されていませんでした。ネットで見ると、どうやら裸婦像のようです。そこで、展示作品の中から猪熊氏の裸婦像を見てみることにしましょう。

(油彩、カンヴァス、182.3×291.5㎝、1936年)
これは、猪熊氏が最初に帝展に入選してから、10年後の作品になります。ネットで見た「婦人像」とは肌の色合いもポーズも異なりますが、リアリズムではない点で、作品の雰囲気は似ています。
猪熊氏は藤島武二教室に所属していましたが、入学して早々に、肋膜を患い、休学をしていました。1926年に第7回帝展に初入選を果たしますが、その後、再び病状が悪化し、1927年には中退しています。
それでは、「馬と裸婦」を見てみましょう。
立っている裸婦と横たわっている裸婦が二人、前景に描かれています。身体に明るいサーモンピックがあしらわれているせいか、若々しく見えます。その背後には、馬が2頭、こちらに顔を向けているものとお尻を見せているものが描かれています。いずれもデフォルメされており、猪熊氏独特のフィルターを通した造形になっています。
この作品を見てまず、目につくのは、立っている裸婦です。大きな乳房の片方は垂れ下がり、脛よりも長い太腿は太く、がっしりとしています。体形からいえば、日本人女性に見えます。
黒い髪のおかっぱ頭で、意思の強そうな顔つきです。両手を腰に添え、恥じることなく堂々と裸体を曝して遠方を見据える姿からは、新時代の女性像を象徴しているように見えます。
先ほどもいいましたように、猪熊氏は藤島武二教室の所属していました。ところが、上記の猪熊氏の作品は藤島武二氏の画風とは大幅に異なります。なぜなのか、ふと、気になり出しました。
図録を読んでいると、関連する記述がありました。豊田市美術館の成瀬美幸氏が資料に基づき、次のように書いていたのです。
「デッサンが悪い、デッサンが悪いと言ってすーっと帰られる。(中略)教えないけど教えるような教育、心の教育を、昔の教授はしっかりと持っていました」
(図録『わが青春の上杜会』、p.16)
どうやら、藤島氏はほとんど指導しなかったようです。これを読むと、藤島氏はおそらく、具体的な制作指導をせず、デッサンや作品との向き合い方など制作にかかわる心構えのようなものだけを伝授していたのでしょう。
猪熊氏の場合、美術学校を中退していますし、この時点ではどこかに留学した様子もありません。おそらく、インパクトの強いこの画風は、猪熊氏が独自に開発したものなのでしょう。とても引き付けられます。
■同窓の力
上杜会のメンバーは44名でしたが、ここでは、たまたま私が興味を覚えた7作品をご紹介しました。いずれも初期の作品を取り上げました。
作品をご紹介していく中で気づいたことがいくつかあります。
たとえば、上杜会の、家族のような支援機能です。
最初にご紹介した犬丸順衛氏は、35歳で亡くなっていますが、結核性脊椎カリエスのため郷里に引きこもっていました。そのような順衛に対し、多くの上杜会のメンバーがハガキを随時、書き送っています。親族の犬丸哲朗氏によると、それに刺激され、順衛もいつかはパリに行こうとフランス語の勉強をしていたといいます。
とくに猪熊弦一郎、小磯良平などは頻繁に順衛にハガキを出していました。病床に伏せながらも、どれだけ心慰められていたことでしょう。順衛は卒業後10年余、養生しながらも絵筆を握って風景などを描いていました。絶筆は水仙を描いた色紙だといいますが、上杜会のメンバーとつながっているという意識が大きな心の支えになっていたに違いありません。
親族の犬丸哲朗氏は、「順衛は妻帯もせず早逝してしまったが、決して不幸ではなかったよと教えてあげたい」と書いています。(図録『わが青春の上杜会』p.64-66)
また、上杜会は美術情報の共有、外国生活での便宜供与など、画家として活躍するうえでの支援装置としても機能していたようです。
たとえば、病気がちだった猪熊弦一郎氏は美術学校を中退します。その後も制作活動を続けていましたが、支えになり、刺激になっていたのは上杜会のメンバーとの交流でした。念願かなって35歳のとき、渡仏し、パリにアトリエを構えることができました。そのときも、頼りになったのが、上杜会のメンバーでした。
実際、留学経験のある小堀四郎氏は、猪熊氏がパリで学ぶことを知ると、現地での生活の方法、美術館情報など事細かに描いて猪熊氏に送っています。また、パリに着いてから、猪熊氏は、現地で生活していた萩須高徳氏、高野三三男氏などと親しく行き来し、生活の便宜を図ってもらい、美術情報等を得ています。
おかげで猪熊氏は、憧れのパリで数多くの名画に学ぶことができ、貪欲に制作に励むことができました。そればかりか、戦争の気運が高まる中、藤田嗣治氏に誘われ、早々に疎開し、難を逃れることができました。上杜会のメンバーの伝手で藤田氏とも親交を結んでいたおかげでした。
戦況が悪化し、疎開しなければならなくなると、メンバーは互いに便宜を図り合いました。そして戦後、様々な苦難を乗り越えてきた彼らに待ち受けていたのは、美術の潮流の大きな変化でした。
こうしてみてくると、上杜会のメンバーは、卒業してもその繋がりのおかげで励まされ、苦難を乗り越えてこられたのだということを実感させられます。上杜会のメンバーは東京美術学校の中でもきわめて優秀な人材が集まったといわれていますが、ただ優秀なだけではなく、お互いに刺激し合い、繋がり合うことによって、上杜会は、画家としての彼らを支え、創作に励むことができる環境作りに寄与してきたのではないかと思いました。
長いスパンで上杜会を見てくると、メンバーたちは試行錯誤して制作し、相互に作品をチェックし合って、技術力、創作力を高める場として機能していたことがわかります。そもそも芸術など創作に関わる領域では、基本的なこと以外、学校で指導するのは難しいでしょう。それだけに学生たちにとっては刺激し合える環境が大きな意味を持ったのだと思います。
この展覧会に参加し、上杜会メンバーの個々の作品を鑑賞できただけではなく、創作環境に必要なものとしての繋がりの場の大切さを思い知らされました。興味深い視点からの企画でした。(2020/11/30 香取淳子)