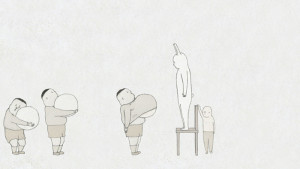■ジャン・デュパ(Jean Théodore Dupas)
東京都庭園美術館の展覧会「幻想絶佳:アール・デコと古典主義」でロベール・プゲオンと同じぐらい数多く作品が展示されていたのが、ジャン・デュパです。こちらはプゲオンとは違って、“1925 quand l’art déco séduit le monde”(1925年、アール・デコが世界を魅了するとき)でも作品が展示されていました。
1925年の国際博覧会で展示された”La Vigne et le Vin”(「ブドウとワイン」1925年制作)です。
これはボルドー館のために制作されたもので、まさに“1925 quand l’art déco séduit le monde”を象徴する作品です。入り口前のホールの壁に展示されていたそうですが、大きさが306×840という巨大な絵画ですから、人目を引いたでしょうし、観客を1925年当時の芸術世界に誘うには格好の導入部になったと思われます。
もちろん、ウィキペディアでもアール・デコの画家と記されています。
デュパは、ボルドー市立美術学校ではポール・カンザック、パリ国立美術学校ではガブリエル・フェリエの下で絵画を学び、1910年にローマ賞を受賞しました。
■国際博覧会ポスターの下絵:三美神が支える3本の柱
1925年現代装飾美術・産業美術国際博覧会のポスターの下絵として1924年に描かれたのがこの作品です。東京都庭園美術館の展覧会場で見ると、大きさが73×53の作品でありながら、特徴のある細長い顔の3人の女性と3本の柱がモチーフとして目立ち、縦長の構成が人目を引いていました。
三人の女性がそれぞれ柱のようなものを支えています。彼女たちの周囲を覆っているのはリンゴやブドウ、ナシなどの果物、あるいは色鮮やかな花々や葉です。地面には下草が生え、上方には青空が広がり、楽園を想像させます。
そして、右の柱のようなものには鮮やかな色で着彩された抽象的な文様が施され、裸体の女性が支えています。真ん中の柱には古代建築の屋根や柱などの部分がいくつかピックアップされて描かれ、肩を出した赤いドレスを着た女性が支えています。そして、左の柱には裸体をあしらったさまざまなレリーフが施され、黒いマントを羽織った女性が支えています。どうやらこの三本の柱のようなものに大きな意味が込められていそうです。
そこで、解説を見ると、この絵について以下のように記されています。
「三美神がそれぞれ柱を支えている。柱には右から、鮮やかな磯の抽象文様、中央は古代建築、左は上部にアジアの神殿のレリーフ、アフリカの彫刻のような大きな頭部の像、下部に花かごを頭に乗せるカリアティードが描かれる。これらは当時の装飾美術の源泉であるキュビスム、古典主義、オリエンタリズムを讃えているように読み取ることができる」
カリアティードとはギリシャ語で女人柱というのだそうです。古代ローマ以前から、梁や上部の水平部分を支える柱の代わりに、このような女性像が使われていました。
柱に描かれた三人の女性を三美神と捉えたところから、この絵の形而上学的解釈が始まっているのでしょう。三美神とはギリシャ神話に登場する三人の女神を指し、それぞれ美貌、魅力、創造力を司っているといわれています。あるいは、美、雅、芸術的霊感を司るともいわれるようです。それが、それぞれ特徴のある文様が彫り込まれた柱を持ち、ともに楽園のようなところで佇んでいる・・・。
そして、細密に描かれた柱の文様を読み解くと、さらに深い解釈が可能になるというわけです。まさに1925年国際博覧会の目的を立派に果たしたポスターの下絵といえます。アール・デコ博覧会の時代、多様な様式の美術が共存していました。そのような風潮をデュパは、自身が模索していた様式美を活かしながら見事に表現しているのです。
■寓意的解釈を迫るデュパのモチーフと様式
会場で展示されていたのが、「パリスの審判」、「国際博覧会ポスター下絵」、「イタリアの泉」、「赤い服の女」、「射手」、「エウロペの誘拐」等々でした。いずれも、古典的なモチーフを使い、様式的な表現で、観客に寓意的解釈を迫ります。モチーフや表現へのこだわりが観客にそのような思いを抱かせるのでしょう。ポスターや習作、大作の一部にその片鱗を見ることができます。
こちら→
http://www.mutualart.com/Artist/Jean-Theodore-Dupas/30D8D67A607CAE22/Artworks
一連の彼の美術作品を見てみると、見る者の気持ちを射抜く絵の力とはなんなのかと思わざるをえません。決して上手な絵だとは思わないのですが、なにか引っかかるのです。そして、記憶に残る・・・、不意に自分で物語を重ね合わせてしまう・・・、そのような力がデュパの作品にはあるのでしょう。100年も前の作品なのに不思議に気持ちが捉われてしまうのです。(2015/1/30 香取淳子)