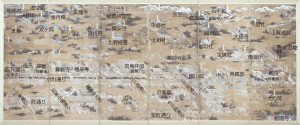■「京を描くー洛中洛外図の時代―」展
4月12日、久しぶりに京都に行って、「京を描くー洛中洛外図の時代―」展(2015年3月1日~4月12日)を見てきました。会場は京都文化博物館で、中京区三条高倉にあります。三条高倉といえば京都の中心市街です。そこからほど近い御池高倉に、かつて足利尊氏の邸宅がありました。
当時、武家は京内に邸宅を建てないという慣習があったようです。ところが、足利尊氏は北条氏を打ち破った功績によって後醍醐天皇から認められ、武家でありながら、京内に居を構えることができたのです。跡地には石標が残されています。日曜日だったせいか、周辺は観光客や買い物客で賑わっていました。この辺りは昔も今も京の中心、ヒトの集まる場所であることに変わりはないようです。
この展覧会では国立歴史民俗博物館所蔵のコレクションを中心に、63点の洛中洛外図屏風、関連資料として4点の参考図版が展示されていました。チラシの表面に使われていたのが歴博乙本(屏風六曲一双 紙本金地着色、国立歴史民俗博物館所蔵)の洛中洛外図屏風でした。
この作品は、歴博甲本(屏風六曲一双 紙本着色、国立歴史民俗博物館所蔵)、東博模本(屏風絵の写し十一幅 紙本淡彩、東京国立博物館所蔵)、上杉本(屏風六曲一双 紙本金地着色、米沢市上杉博物館所蔵)と同様、室町時代後期に描かれた洛中洛外図屏風の一つで、狩野派の画家によって描かれたといわれています。以上の4点が初期の洛中洛外図屏風で、戦国時代の諸相が捉えられているといわれています。
それでは、洛中洛外図屏風とはいったいどういう屏風なのでしょうか。
■初期の洛中洛外図屏風
洛中洛外図屏風を見るのは今回が初めてです。よくわからないことも多いので、各種資料を参考にしながら、鑑賞することにしました。まず、洛中洛外図とはどういうものなのか、京都市の案内を見てみることにしましょう。
こちら →https://www.city.kyoto.jp/somu/rekishi/fm/nenpyou/pdffile/toshi17.pdf
この案内にあるように、「洛中洛外図屏風」は京都の市街と郊外を鳥瞰し、そこから神社仏閣、内裏や公家の御殿、町屋や農家を描くことによって、人々の生活や風俗などを表したものです。
多くは六つ折れ(六曲)の屏風二つがセットになっていて、一双と呼ばれています。一双の屏風の片方を一隻と呼び、右側を右隻、左側を左隻といいます。滋賀県立美術館によると、六曲一双の屏風は以下のような作りになっています。右隻と左隻で違う画面を描き、対の関係になっているものが一般によく見られるようです。
こちら →http://f.hatena.ne.jp/shiga-kinbi/20110303164018
洛中洛外図屏風の場合、右隻に京都の東側、左隻に京都の西側が描かれました。
Wikipediaによると、初期の洛中洛外図は、「右隻に内裏を中心にした下京の町なみや、鴨川、祇園神社、東山方面の名所が描かれ、左隻には公方御所をはじめとする武家屋敷群や、船岡山、北野天満宮などの名所が描かれている。また、初期洛中洛外図屏風を向かって見ると、右隻では、上下が東西、左右が北南となる。一方左隻では、上下が西東、左右が南北となる」とされています。
どうやら、これが一つの形式となっていたようです。さらに、「右隻に春夏、左隻に秋冬の風物や行事が描かれている」とも記されています。
こうしてみると、初期の洛中洛外図屏風には一つの形式があり、その形式の中で絵師たちが京都の四季、神社仏閣、名所や御所、人々の生活や風俗、地形を描いていたことがわかります。洛外図屏風はいってみれば、当時の総合地図であり、図鑑であり、生活事典でもあったのです。
■なぜ作られたのか
洛中洛外図はなぜ作られたのでしょうか。
洛中洛外図屏風が出現した経緯について、カタログでは以下のように説明されています。
「応仁・文明の大乱が収束し、人々が京都再建に勤しんでいた十六世紀初頭の永正三年(1506年)十二月二十二日、越前の戦国武将、朝倉貞景の所望で「一双に京中を描く」屏風が作られたとの記録が現れる(『実隆公記』)。これが洛中洛外図に関する現存最古の記録である。幕府権力が衰微し、有力者が抗争を繰り広げたこの時期、京都を総合的に把握し絵に表そうとする最初の試みが戦国武将の下でなされたことは、この主題の生まれ持った性格を考える上で大変意義深い」
たしかに、戦後の混乱期に「京都を総合的に把握し絵に表そうとする」人物がいたことには驚かされます。しかも、それが戦国武将だったのです。一般に武士は文化知識層ではないと考えられています。それが、応仁の乱以降、戦国武士が京都に滞在するようになった結果、文芸に関わり、その保存や興隆にも貢献するようになったとされています。戦国武士と文芸に関する著書の多い米原正義氏によると、越前朝倉家はそのような文芸をたしなむ戦国武将の一人に数えられるといいます。
とりあえず、Wikipediaを見てみると、「甘露寺中納言来る、越前朝倉屏風を新調す、一双に京中を画く、土佐刑部大輔(光信)新図、尤も珍重の物なり、一見興有り」と、出典(『実隆公記』)の該当箇所が示されていました。
越前朝倉家が発注して絵師(土佐光信)に描かせた屏風を、実隆は甘露寺中納言から見せられたようです。それを見た実隆はとても珍しく貴重な屏風だと思い、興味をおぼえたと書いているのです。
屏風は元来、源氏物語絵巻のような故事、人物、事物、風景などをモチーフに描かれることが多かったようです。ですから、京都の地理や都市構造をモチーフにした屏風などそれまで見たこともなかったのでしょう、三条西実隆は意表を突かれ、大きな関心を寄せています。当時、第一級の文化人とされた彼がわざわざ「尤も珍重の物なり」と日記に書いたのです。京都を総合的に把握し、それを絵画の形式で表現したこの屏風絵はそれほど新奇で画期的なものでした。
このモチーフはやがて戦国武将の間で、大きな潜在需要を掘り起こしていきます。ですから、その後、幕末までの約350年間、洛中洛外図は描かれ続けたのです。現在、百数十点の存在が確認されているそうです。
■戦国武将による発注
注目すべきは、絵師にそのようなモチーフの屏風絵を依頼した越前朝倉家でしょう。越前朝倉家は南北朝時代に但馬朝倉家から分かれて越前に移り、後に戦国大名になりました。そして、この屏風を絵師に発注したのは9代目の朝倉貞景だといわれています(Wikipedia)。
『日本人名大辞典』によると、朝倉貞景(1473-1512)は、「越前の守護。一族の内紛を抑え、さらに加賀一向一揆の侵攻を撃退して朝倉家の越前支配を確立した」と記されています。優れた戦略家で、しかも統治能力にも長けていたようです。また、『朝日日本歴史人物事典』によると、以上の内容に加え、「『宣胤卿記』は、その画才が天皇の耳にも聞こえていたと伝えている」と記されています。朝倉貞景に画才があったというのです。画才のある武将が屏風絵を発注したというのも、また大変、興味深いことです。
この『宣胤卿記』は公家の中御門宣胤が綴った日記で、執筆期間は1480年から1522年に亘っています。戦国時代の公家の生活についての情報が豊富だといわれています。この日記からは、朝倉貞景が武将でありながら画才があると周囲に認識されており、天皇をはじめ公家たちから一目置かれていたことが示唆されているといえるでしょう。
戦国武将であった朝倉貞景はおそらく、花鳥風月を愛でるよりは統治や攻略に役立つ情報を好んだのでしょう。ですから、もともと画才のあった彼は、京の都にまつわるさまざまなモチーフをどのように取り上げ、どのように配置すべきかについても絵師に指示していた可能性があります。
そう考えると、納得がいきます。京都を総合的に把握し屏風絵を描くよう依頼されても、なんの指示もなければ、絵師は戸惑うだけで、絵筆を執ることさえ叶わなかったでしょう。これまで目にしたこともないモチーフです。描くよう命じられたとしても、絵師にしてみれば、ただ困惑するだけだったでしょう。それを一双の屏風として仕上げたのですから、絵師になんらかの助言があったと考える方が自然です。つまり、モチーフや構図のアイデアは発注者の朝倉貞景が提供し、絵師はそれを聞いて屏風絵を描く、という分業が考えられるのです。
残念ながら、この屏風は現存していません。たまたまこの屏風を見た三条西実隆が日記に発注者と絵師の名前を記録していました。1506年、16世紀初頭のことです。そして、当代一流の文化人であった実隆の感想から、このモチーフの斬新さが明らかになったのです。一方、同じく公家であった中御門宣胤の日記から、武将であった朝倉貞景に絵心があったこともわかりました。
こうしてみると、発端となった洛中洛外図は、公家とも交流のあった絵心のある戦国武将・朝倉貞景のアイデアから生み出されたといえそうです。詳細な地理、建物の配置や構造、人々の暮らし、四季折々の風俗、文化など、京都の総合的な情報を凝縮して一望できるのが、洛中洛外図屏風です。断片的に京都の佇まいを捉えた屏風はあっても、総合的に捉える試みはそれまでありませんでした。まさに戦国武将ならではの発想で、新しい美術表現の地平を切り開いたのです。
■地理情報、生活情報の宝庫
さきほど紹介した京都市の案内によると、初期の作品は室町後期の応仁・文明の乱後の復興期の諸相が描かれていたようです。この乱で京都の町は壊滅状態になり、その後の復興過程で市街地が上京と下京に分断されました。この二つの市街地は南北に通ずる中央の道路だけでつながっており、その道路が室町通りだったと考えられています。初期の洛中洛外図はこのような都の状況を反映するかのように、一隻を上京、もう一隻を下京中心に描かれていたのです。
この時期はおそらく、京都を総合的に把握する情報が求められていたのでしょう。とくにその必要性を感じていたのが都の統治を目指していた戦国武将だったと思われます。彼らは人々の生活、建物の配置、道路状況、等々、さまざまな情報を欲したと思いますが、もっとも手に入れたかったのは、京の都の地理情報だったと考えられます。
現存する最古の洛中洛外図屏風といわれる「歴博甲本」は、1520年代から30年代にかけて制作されたと考えられていますが、京都の地理が大変、詳しく描かれています。たとえば、歴博甲本の左隻はこのように描かれていました。
これを見ると、まさにgoogle mapも顔負けしそうなほどの立体地図です。主要な道路、神社仏閣、公家などの邸宅の位置が詳細に描かれています。統治のための戦略を練るには不可欠の情報であり、計画立案のための恰好の資料になったことでしょう。この図の文字はわかりやすく活字に置き換えられていますが、実際の文字は草体仮名で表示されています。
地理情報ばかりではありません。四季折々の景色や祭事が活写されており、総勢1426人の生活シーンがきめ細かく描かれています。たとえば、国立歴史民俗博物館は、「歴博甲本」で描かれた人物すべてをデータベース化しています。興味があれば、それぞれの人物像を一覧することもできますし、属性で検索することもできます。
こちら →
http://www.rekihaku.ac.jp/rakuchu-rakugai/DB/kohon_research/kohon_people_DB.php
公家であれ、武士であれ、町衆であれ、当時の人々がどのように暮らしていたか、これを見ると、一目でわかります。絵ですから、人々がどこで、どのような服装で、何をしていたのかが具体的に理解できるのです。当時の社会や生活、文化を把握するには第一級の資料といえるでしょう。
初期の洛中洛外図屏風としては、この歴博甲本以外に、東博模本、上杉本、歴博乙本の4点が現存します。いずれも戦国時代の様相が丁寧に描かれており、美術作品としてはもちろん、歴史、生活文化、社会、政治を把握する資料としても大きな価値があります。屏風絵にどのような意味が込められていたのか、興味は尽きることがありません。次回は上杉本を中心に見ていくことにしましょう。(2015/4/27 香取淳子)