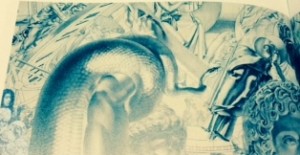■第18回受賞作品
第18回メディア芸術祭のアニメーション部門の応募作品数は、劇場アニメーション、テレビアニメーション、オリジナルビデオアニメーションの分野で60作品、短編アニメーションで371作品でした。圧倒的多数が短編アニメーションだったのです。
そのせいか受賞作品も、大賞(ロシア)、優秀賞(アルゼンチン、フランス)、新人賞(中国、韓国)等々が短編アニメーションで占められていました。高い芸術性と創造性が評価されたようですが、残念ながら、日本の短編作品は受賞しませんでした。受賞作品以外に審査委員会推薦作品も設けられています。
審査委員会推薦作品を見ても、24作品中16作品が短編アニメーションでした。受賞作品を含めると、21作品が高い評価を得たことになります。短編アニメーションの応募総数は371作品ですから、受賞比率は約5.9%です。
一方、劇場アニメーション等の領域は応募総数が60作品で、受賞作品が3作品、審査委員会推薦が8作品でしたから、合計で11作品、受賞比率は約18.3%になります。劇場アニメーション等の領域は応募総数こそ少ないものの、受賞比率は短編アニメーションに比べ約3倍も高いということになります。このような結果からは、劇場アニメーション等の領域への応募者は実績のある制作者が多いことが示唆されています。
ちなみに過去の受賞歴を見ると、「もののけ姫」(第1回)、「千と千尋の神隠し」(第5回)、「クレヨンしんちゃん」(第6回)、「時をかける少女」(第10回)、「魔法少女まどか☆マギカ」(第15回)といったように、錚々たる作品がアニメーション部門の大賞を受賞しています。
過去日本が大賞を受賞したのは劇場アニメーションかテレビアニメーションでした。第18回も日本は劇場アニメーション領域では2作品が優秀賞、1作品が新人賞を取っていますが、大賞は逃しました。興味深いことに、第17回、第18回とも日本はアニメーション部門の大賞を逃しているのです。
第17回は韓国系ベルギー人ユン監督(ベルギー名:Jung Henin)とフランスのドキュメンタリー映画監督ローラン・ボアローの共同監督による「はちみつ色のユン」でした。75分の作品です。
こちら →http://hachimitsu-jung.com/
そして、第18回はロシアの若手アニメーター、Anna Budanovaの作品「The Wound」でした。こちらは9分21秒の短編アニメーションです。
■「The Wound」
ロシアの26歳の若手アニメーター、Anna Budanovaが今回、大賞を受賞しました。なによりもまず鉛筆画の素朴で優しい画風が印象に残ります。
作品は全編、細部にまで神経の行き届いた味わい深い画風で展開されます。
こちら →https://vimeo.com/63658207
私はロシア語版でしか見ることができなかったのですが、柔らかいタッチの映像が味わい深く、その場の状況はもちろんのこと、登場人物たちの情感や主人公の深層心理までもよく理解することができたような気がしました。ワンカット、ワンカットの絵が素晴らしいのです。
まず、冒頭のシーンの映像構成に惹き付けられてしまいました。哀調を帯びたロシア音楽を背景に、壁に掛けられた写真が次々と映し出されていきます。過去、主人公と関わりのあった人々なのでしょう。髭を描き加えられたり、中には顔の上に×がつけられた写真もあります。そのヒトたちはかつて主人公に心の傷を負わせた人々なのかもしれません。
やがて太った老女が現れ、鏡を磨きはじめます。鏡の中のわが身をじっと見入っていたかと思うと、過去にタイムスリップしていきます。これが主人公です。
クリスマスの日。子どもたちが喜んではしゃぎまわる中、サンタクロースはプレゼントを次々と渡していきます。どういうわけか最後になるまで一人だけもらえなかった少女は、遠慮がちにサンタにプレゼントをねだります。
そのとき、少女は白い耳に真っ赤な鼻先をつけてウサギの恰好をしていました。だからでしょうか、サンタクロースは袋の中から一本のニンジンを取り出し、少女に渡したのです。少女は落胆と屈辱感に打ちのめされてしまいます。
それを見ていた男の子たちがはやし立て、少女に近づき、ゴムで装着した真っ赤な鼻先を勢いよく引っ張り、極限まで引っ張ったところで放しましました。反動で少女は顔面一体に強烈な痛みを覚えます。この時少女は精神的暴力と身体的暴力を同時に受けたのです。このシーンで作者は主人公の心の傷の原風景を抒情性豊かに描きます。
少女は泣きじゃくりながら、ウサギの衣装を脱ぎ捨て、帰宅し、ベッドの下に潜り込みます。しばらくして泣き止むと、意を決したかのように、傍にあった鉛筆で床に殴り描きを始めます。その顔は激しい憤怒に駆られています。描いた線はやがて形になり、毛むくじゃらの小さな生物になっていきます。この小さな生物が現れると途端に少女の表情は明るくなります。
これが主人公の生涯の友になるthe wound です。日常の風景の中で、主人公(現在は老女)とサブ主人公の登場のさせ方が実に巧みです。監督、脚本はAnna Budanova(アンナ・ブダノーヴァ)です。ここまでの1分23秒間で、物語の導入と登場人物の紹介、テーマ、等々が手際よく、しかも明確に提示されています。その後の展開は見てのお楽しみ・・・、ここで紹介するのはやめておきましょう。
■短編アニメーションの多様な可能性
第18回メディア芸術祭の短編アニメーションへの応募総数は371作品でした。そのうち受賞および審査委員会推薦作品に選ばれたのが21作品で、受賞比率は約5.9%でした。劇場アニメーション等の長編アニメーションに比べると、3分の1以下の受賞率です。この結果からは、実績の少ない人々が短編アニメーションに多数応募していることが推察されます。
廉価なパソコン、操作が簡単で高機能の編集ソフト等が出回っている現在、意欲さえあれば、以前よりはるかに容易にアニメーション制作に参入できるようになっているのです。それだけアニメーション制作をめざすクリエーターの裾野が広がっているといえるでしょう。制作環境がデジタル化するに伴い、アニメーションを見て楽しむだけではなく、自分でも作ってみようと思う層が増えてきているのです。若い世代にはとくに国境を越えて、短編アニメーションという領域が違和感なく、過不足なく自分を表現できる場として認識されつつあるのではないかという気がしています。
たとえば、今回の「The Wound」は、主人公の心の傷が毛むくじゃらの生物に変貌し、生涯それと共に生きていくというストーリーでした。おそらく作者自身の体験をベースに着想されたストーリーなのでしょう。クリスマスのシーン、スケート場でのシーンなど、細部が生き生きと描かれています。
「The Wound」では、心の傷の化身という一見、突拍子もない造形物が違和感なくストーリーに溶け込み、リアリティ豊かに表現されているのです。だからこそ、私たちは感情移入し、この作品の世界に浸ることができるのですが、それは、作者が丁寧に自分の体験を見つめ、それを昇華させてストーリーを紡ぎあげたからにほかなりません。
短編アニメーションの制作費は比較的安く、制作日数も比較的短くて済むので、制作の敷居は比較的低いといえます。実績がなくても、意欲さえあれば制作可能ですし、どのようなテーマも表現可能です。
劇場アニメーションやテレビアニメーションの場合、最初から観客動員数を視野に入れて構想を練り上げなければなりません。短編アニメーションにはその種の制約が少ないので、観客に媚びることなく、自由にテーマ設定ができますし、ストーリーにメリハリがなくても構いません。
短いので、ストーリーに起伏を持たせる必要もなければ、サブストーリーを設定する必要もありません。自分が表現しようと思ったことをそのまま素直に表現できるメリットがあると思います。それだけに、短編アニメーションには作者が抱え込んだ心の傷、あるいは忘れることのできない経験が反映されやすいといえるかもしれません。作者にとって忘れがたい心の原風景が作品として仕上げるための動機付けとして作用することもあるでしょう。
そういえば、第17回の大賞「はちみつ色のユン」は長編アニメーションでしたが、監督自身の体験に基づいたドキュメンタリータッチのアニメーションでした。短編ではありませんが、監督自身の思いのたけをぶつけたところにヒトの心を打つ作品ができあがったという気がします。商業ベースではなかなか制作できない類の作品です。
今回、短編アニメーションの受賞領域は、大賞1作品、優秀賞2作品、新人賞2作品でした。いずれも日本は受賞していません。商業ベースのアニメーションに馴染みすぎて、発想や展開がパターン化しているのではないかと懸念されます。とはいえ、審査委員会推薦作品には日本から7作品が選ばれていますから、多様な作品が生まれる土壌はまだ劣化していないのかもしれません。(2015/2/19 香取淳子)