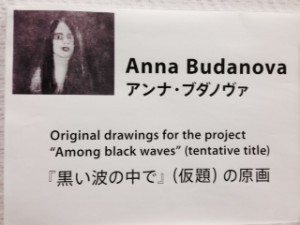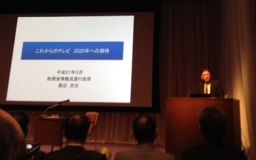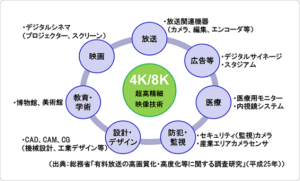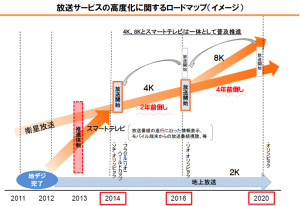■FACE展2015
「FACE展2015」は、損保ジャパン日本興亜美術館を会場に、2月21日から3月29日まで開催されていました。「VOCA展2015」に物足りない思いをしていた私は、その帰途、「FACE展2015」に立ち寄ってみたのです。FACE展もVOCA展と同様、参加するのは今回が初めてです。こちらはVOCA展とは違って公募形式で「年齢、所属を問わず、真に力がある作品」が募集されています。出品のための条件が課せられていなかったせいか、幅広い層から作品の応募があったようです。
出品数は748点にも及びました。前年、前々年よりも減少したといいますが、それでも相当な数です。応募作品はすべて作品本位で公平厳正に審査され、70点の入選作品が選定されました。入選倍率は10.7になります。さらに、その中から合議制で9点の受賞作品が選ばれました。モチーフ、マチエールとも多種多様で、それぞれに魅力があり、見応えがありました。私が強く印象づけられたのは、グランプリの宮里紘規氏の「WALL」と、優秀賞の和田和子氏の「ガーデン(木洩れ日)」でした。
受賞作品が展示されているコーナーに入った途端、目についたのが、宮里紘規氏の「WALL」と、和田和子氏の「ガーデン(木洩れ日)」だったのです。たまたまこの二作品は並べて展示されていましたが、見た瞬間に、その場をすぐには立ち去り難い思いに捉われました。いずれも内容に深みが感じられたからです。おそらくそのせいでしょう、表現者の深層に近づいてみたいという気持ちが沸々と湧き上がってきたのです。
今回は和田和子氏の作品を見ていくことにしましょう。
■和田和子氏の「ガーデン(木洩れ日)」
「ガーデン(木洩れ日)」(2014年制作)は、162×194㎝のキャンバスに油彩で写実的に描かれた作品です。色彩にもモチーフにも派手さはありません。もちろん、奇をてらったところもなければ、気負ったところもありません。色調は柔らかく、モチーフもごく自然に配置されています。どちらかといえば、地味で目立たないように見える作品です。ところが、そんな作品に私は一目で惹き付けられてしまったのです。
なぜ、そういう思いに捉われたのか、自分ながら不思議な気がして、しばらく絵の前に佇んでいました。
「木洩れ日」といえば、通常、木々の葉越しに陽光が差し込んでくる光景を指します。ですから、下から上を見上げる構図でなければ、その光景を捉えることはできないはずです。ところが、この絵は木の上から俯瞰する恰好で庭を捉えているのです・・・、と書いてきて、ふと、私が勝手に俯瞰だと思ってしまっただけなのではないかという気がしてきました。絵の構図が何だか変なのです。
■俯瞰とアイレベル、視点の交錯
改めてこの作品を見てみると、俯瞰にしては、木の幹が太すぎます。まるで巨木の幹のように太く描かれています。画面全体の4分の1ほどを占めているでしょうか、まさにこの絵の中心といえます。ですから、見る者の視線はまず、この幹に留まります。その太い幹から何本も枝が分かれて伸びていますが、そのうちの目立つ二本の枝はまるで女性の太腿から脛にかけての部分のように見えます。
付け根の太さといいその形態といい、とても肉感的で、シンクロナイズドスイミングの水中から浮き出た脚のようにも見えます。枝の付け根でしかないのですが、そこにかすかなエロティシズムが漂っていて、太い木の幹に表情を添えています。構図の不自然さから目を逸らす仕掛けのようにも思えます。不思議なことに、葉はまばらにしか描かれていません。
俯瞰すれば、垂直方向に樹木を捉えますから、木の上部の葉しか見えないはずです。ですから、葉がもっと茂っていなければならないし、幹や枝がこのようにはっきりと見えるはずはありません。さらにいえば、枝の伸びている方向が不自然です。よく見ると、幹の下には何本もの根が張り、巨木を支えています。ですから、この部分は明らかにアイレベルで捉えた構図なのです。
では、なぜ私はこの絵を俯瞰の構図と思ってしまったのでしょうか。
もう一度、この絵を見てみると、太い幹はやや左よりに対角線のように配置され、画面を左右に分断しています。左側にはオベリスクに絡まる白い花と葉、右側には水連が浮かぶ水桶、植木鉢やプランターなどが配置され、それぞれのモチーフは俯瞰で捉えられています。
しかも、太い幹の下から右上方に向けて、地面には木の影らしきものが伸びています。俯瞰でなければ捉えられません。そして、影の伸びた先には柵のないウッドデッキがあり、そこで女性が椅子に座り、図鑑を見ています。その女性の背中には葉影が落ちています。陽光が左上方から射していることが示されています。ウッドデッキにもその周辺の地面にも葉影が落ちています。ですから、この部分に関しては陽光が左上方から射し込んでいることになります。つまり左上方からの俯瞰図なのです。
このように見てくると、私が木の上から庭を俯瞰した絵と思ってしまったのは、絵の中心に描かれた大きな木以外のモチーフはすべて俯瞰で捉えられていたからだということがわかります。ところが、俯瞰の方向は一様ではなく、幹の右側が左上方からの俯瞰、左側が左斜め真上からの俯瞰といった具合に異なっています。たとえば、左側に配置されたオベリスクに絡まる一群の花は左斜め真上からの俯瞰です。
こうして見てくると、この絵には複数の視点が導入されていることがわかります。ところが、一見すると、庭を写実的に再現したようにしか見えません。大きな違和感を覚えさせることがないのです。ただ、複数の視点で捉えられたモチーフが一枚のキャンバスに収められていますので、見る者は、平面の絵を見ながらも、立体を見るときのような視線の動きをしてしまうのでしょう。まさに複数視点による視線誘導です。
これと似たような発想で絵を描いていた画家がいました。セザンヌです。
■セザンヌの構図
イタリア人の美術批評家にリオネルロ・ヴェントゥーリというヒトがいます。彼はセザンヌが描いた絵とその実景写真とを比較するという手法で、セザンヌの絵の構造を明らかにしました。(リオネルロ・ヴェントゥーリ著、辻茂訳、『美術批評史』、みすず書房、1971年)
たとえば彼は、セザンヌのサント・ヴィクトワール山を描いた作品とその実景写真を比較し、絵には「造形的なダイナミズム」があるのに、写真にはそれがなく、山のボリュームは弱々しいと書いています。モチーフを写実的に再現することが必ずしもモチーフの本質を捉えることにはならないといい、セザンヌの絵には意図的な作為が施されているというのです。
絵画と写真とを比較する手法でセザンヌを研究したのはリオネルロ・ヴェントゥーリだけではありませんでした。アメリカ人の美術評論家であり大学教師でもあったアール・ローランも、同様の手法でセザンヌの描いた絵についてさらに精緻な実証研究をしています。(アール・ローラン著、内田園生訳、『セザンヌの構図』、美術出版社、1972年)
彼は風景画から静物画までさまざまなセザンヌの絵を取り上げ、実証的に研究しました。私が和田氏の作品を見て、思い出したのは果物をモチーフにした作品です。果物はセザンヌが好んで描いたモチーフの一つです。
セザンヌに「果物籠のある静物」という絵があります。和田和子氏の「ガーデン(木洩れ日)」ほど大胆ではないですが、やはり複数の視点を絵の中に持ち込んで、モチーフを配置しています。セザンヌの作品も一見、ごく自然にモチーフを写実的に再現した作品に見えます。
ローランは画家でもあったのですが、セザンヌの「果物籠のある静物」について上記の手法で実証研究を行った結果、この絵には複数の視点が導入されていると指摘しました。個々のモチーフがどの視点から捉えられたかを図示したうえで、複数の視点による効果を明らかにしたのです。
たとえば、基準になる視点を設置してこの絵を見てみると、モチーフの形態から判断してその視点で捉えられるものとそうではないものがあるとし、この絵に別の視点が導入されていると指摘しました。同様にして、さらに別の視点が取り入れられていることを実証し、この絵には複数の視点が導入されていると指摘しました。その結果、この絵を見るヒトはまるで絵の周囲を回り込みながら見ているような気になるというのです。
ローランはこのように大変、興味深い指摘をしています。たしかに、この絵を見ていると、観客は絵の周囲を回り込みながら見ているような気になるのかもしれません。複数の視点が導入されたことによる効果です。
ですが、この絵を注意深く見るヒトはなによりもまず、どこか違和感を覚えていたはずです。ちょっと不思議な感覚とでもいえばいいのでしょうか。絵の吸引力ともなる「違和感」です。
「ガーデン(木洩れ日)」の構図に違和感を覚えたとき、私はふと、セザンヌの「果物籠のある静物」を思い出してしまったのです。
■複数視点と色彩の制御による視線誘導
「ガーデン(木洩れ日)」を見る者はまず、太い木の幹を見てから枝を見、見下ろすようにして、庭やウッドデッキで本を広げている女性を見ていくことになります。後姿の女性に辿り着いたところで、何か見落としたような気がして再び、木の幹に戻り、左下に配置されたオベリスクに絡まる広い花や葉を見ます。そして、もう一度、庭を見下ろして女性の背中に目を落とすと、今度は木洩れ日の下で本を読む幸せを共有していることに気づきます。モチーフの間を回り込んで見ていくうちに、このモチーフ(後姿の女性)に感情移入できているからでしょう。俯瞰しているにもかかわらず、木洩れ日の下にいる錯覚に陥ってしまいます。葉の影から洩れる陽光と爽やかな空気が感じられるのです。
そのように感じてしまうのはおそらく、太い幹から回り込むようにしてさまざまなモチーフを見、最終的にもう一つの中心モチーフ(後姿の女性)を見ていくよう見る者の視線の動きが誘導されているからでしょう。「セザンヌの構図」を踏まえて「ガーデン(木洩れ日)」を読み解いてみると、この絵には複数の視点が盛り込まれており、それによって、見る者が自然に視点移動し、作品世界に引き込まれていくことがわかります。
不思議なことに、これだけ多くのモチーフが視点の異なる中で配置されているにもかかわらず、雑然としておらず、むしろ、秩序ある静寂さえ感じられます。それはおそらく色彩が厳密にコントロールされているからでしょう。よく見ると、すべてのモチーフに色彩のコントロールが加えられています。緑色系、寒色系で統一されているのです。
太い幹の左下でかなりのボリュームを占めるオベリスクに絡まる花や葉さえ、すべて白で表現されています。暖色系はごくわずか、植物図鑑の一部、本の一部、パラソルの一部に使われているにすぎません。このように厳密に色数が制限されているからこそ、複雑な構成であっても自然な調和が生み出されているのでしょう。さらに淡いモスグリーンの葉が画面全体にほどよく放散されています。これもまた絵全体に統一感を生む効果があります。
■知的な絵画の魅力
こうして見てくると、この絵はきわめて複雑な構造で組み立てられていることがわかります。一見、写実的に描かれているように見えて、その実、複数視点といい、色彩戦略といい、多様な仕掛けが施されています。決して自然に描いた作品ではないのです。ひょっとしたら、自然に描かれたものではないからこそ、見る者はきわめて自然にこの作品世界の中を回遊し、「木洩れ日」(自然)を感じ取ることができるのかもしれません。絵画ならではの魅力です。
構図の不思議、視点の違和感を読み解こうとしているうちに、快い木洩れ日の下、図鑑を読んでいる女性に感情移入してしまっていることに気づきます。コントロールされた色彩のせいかもしれませんが、葉影から洩れる陽光すら感じられます。しばらく見入っているうちにいつしか、爽やかな気分になっているのです。それが作者の狙いだとしたら、見事というしかありません。作品の背後から透けて見える知性に惹かれます。(2015/4/10 香取淳子)