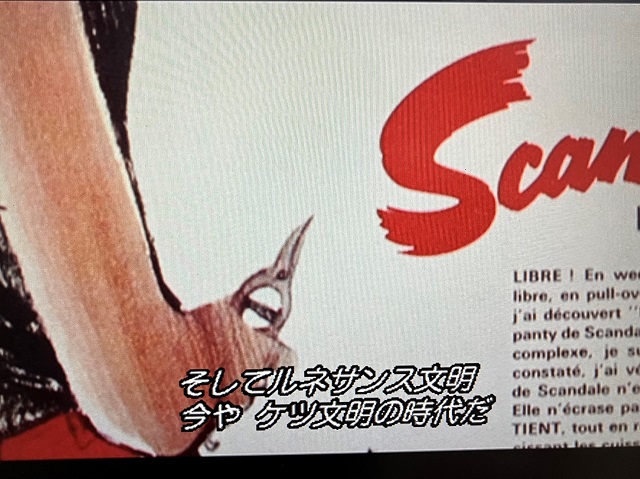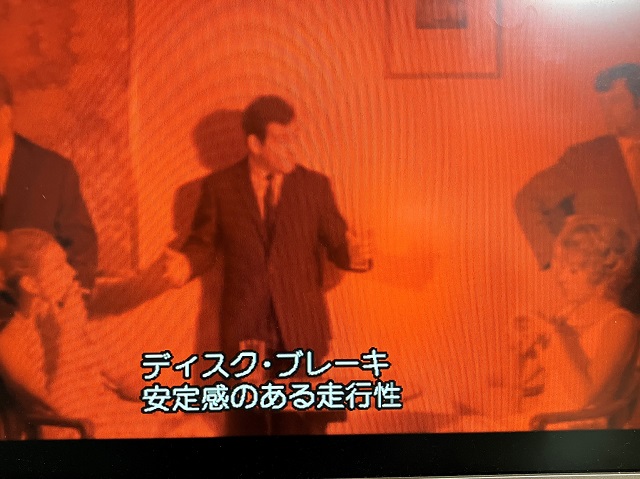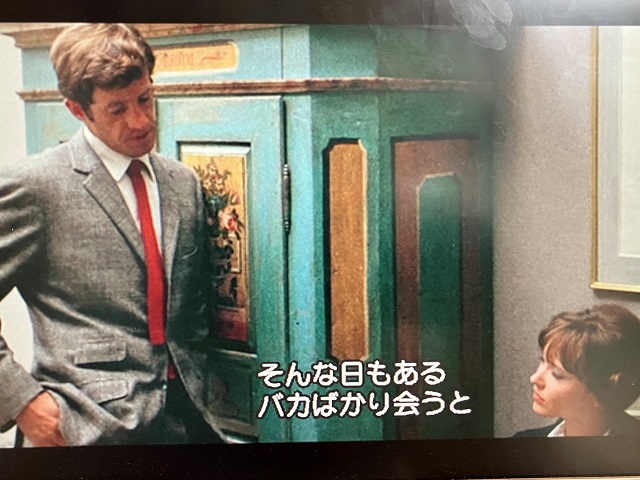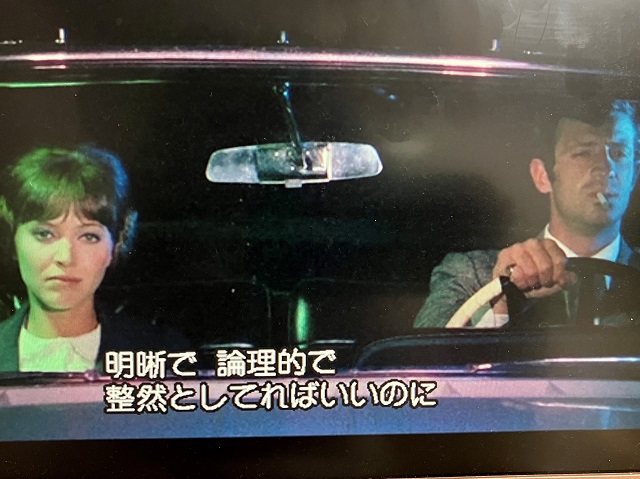前回からのシーンに引き続き、見ていくことにしましょう。
■マリアンヌとの逃避行
パーティから抜け出したフェルディナンは、マリアンヌを送り届け、そのまま、アパートに泊まってしまいます。一夜を共にした翌朝、フェルディナンは隣室で、首にハサミを突き刺されて血を流した男が、ベッドに倒れているのを発見します。
死体を見て驚く間もなく、フランクがアパートにやって来たので、仕方なく、彼を殴って倒し、二人は盗んだ車で逃亡します。
フェルディナンはただ、現実から逃避したかっただけでした。ところが、わけもわからないまま、犯罪に巻き込まれてしまったのです。逃げるしか道はなく、そして、犯罪を重ねるしか、逃げ切ることはできませんでした。
お金のない二人は、給油しても支払わずに逃げ、カフェに入ってはでっち上げの物語を語って小銭を稼ぎ、南へ南へと逃亡を続けます。
警察の目を欺き、首尾よく逃げおおすには、自分たちの痕跡を消す必要がありました。
郊外を走っている途中、二人はたまたま、大木にぶつかって自損事故で壊れた車を見つけました。近づいてみると、男女二人が死んでいました。かなり悲惨な事故です。
二人にとっては、ちょうどおあつらえ向きの事故でした。
フェルディナンとマリアンヌは事故状況を確認すると、その場に車を停め、ナンバープレートを外して燃やしてしまいます。事故で死んだように装い、自分たちの痕跡を消すためでした。
黒煙が立ち昇る中、二人は歩いて逃亡を続けます。平原を歩き、川を渡り、やがて、森の中に入っていきます。マリアンヌはぬいぐるみを持ち、フェルディナンはピエ・ニクレのコミック本を持ち歩いています。
二人とも言葉もなく疲れ切っている様子です。いつまでも歩き続けることはできないでしょう。そう思っていたら、次に、二人がガソリンスタンドで腰を下ろしているシーンになりました。
疲れた二人はここで、目ぼしい獲物がやって来るのを待ち構えているのです。逃亡を続けるには車が必要でした。
マリアンヌは道路に目を向け、獲物をチェックしているのに、フェルディナンはひたすら、コミック本を読み続けています。

(※『気狂いピエロ』、2017年、KADOKAWAより)
■ピエ・ニクレ(Les Pieds nickelés )
フェルディナンが読んでいるコミック本のタイトルは、ピエ・ニクレ(Les Pieds nickelés )で、このフランス語を直訳すると、ニッケルメッキの足ということになります。調べてみると、この「ピエ・ニクレ」は、フランス19世紀末の俗語では、「勤労意欲が長続きしない連中」という意味になるそうです。
「ピエ・ニクレ」は、ルイ・フルトン(Louis Forton、1879- 1934)が創作したコミックで、雑誌L’Épatantに連載されていました。鼻の尖ったクロキニョル、片目に眼帯を掛けたフィロシャール、あごひげのリブルダングの三人組を軸に展開されるピカレスクです。とても人気にあるコミックで、1934年にフルトンが亡くなると、別の漫画家が引き継ぎ、描き続けたそうです(※ https://note.com/lemmui/n/n4a5836edb54c)。
ユーモアたっぷりのピカレスクは、時代を越え、世代を越えて、人々の気持ちのはけ口として求められ、楽しまれてきたのでしょう。
掲載誌も同様でした。雑誌L’Épatantは1939年に廃刊になりましたが、その後も別の出版社に引き継がれ、このコミックは1908年から2015年まで続いたそうです。(※ https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Pieds_nickel%C3%A9s)
さて、ちょっと横道に逸れてしまいました。さっそく、先ほどのシーンに戻りましょう。
歩き疲れた二人は、車を盗むため、ガソリンスタンドでチャンスを狙っていました。ところが、チャンスが訪れても、フェルディナンはこのコミックから目を外しません。マリアンヌは「ピエロ、フォードよ」といい、「早くして、一人でやるわよ」と犯行を促しますが、「読んでから」と受け流し、動こうとしないのです。
そういえば、逃避行が始まって以来、フェルディナンはこのコミック本を持ち歩いていました。平穏な日常生活から突如、追われる立場になった彼には欠かせなかったのかもしれません。
このピカレスク・コミックは、ちょっとした悪事を働くための指南書のようでした。ブルジョワの生活から一転して犯罪者になってしまったフェルディナンにとっては不可欠でした。それまでの自分とは別の自分に気持ちを切り替えるために手放せなかったのでしょう。
再び、チャンスが訪れました。今度は、デラックスなオープンカーがガソリンスタントに乗り付けたのです。
恰好の獲物を見つけた彼らは、そっと給油スタンドに近づきます。運転していた男が給油をスタッフに依頼し、助手席にいた女性を伴ってカフェに向かうと、その隙に、マリアンヌは車に乗り込みます。
一方、フェルディナンは給油が終わるのを待って、車に乗り込みます。マリアンヌが持ち主の上着から抜き取ったお金でスタッフに支払い、そのまま乗り逃げします。
画面には、「何世紀もが嵐のごとく、消え去った」と字幕が表示されます。
嵐のような激動の日々が過ぎ、フェルディナンは次第に追い詰められていきます。絶望的な気持ちを表すかのようなセリフでした。
■死の匂い
助手席でマリアンヌが新聞を読み、二人の犯罪が報道されているのを知ります。フェルディナンに、奥さんが警官に「狂ったとしか思えません」と答えていたことを告げると、「女は捨てられると、すぐ悪く言う」とフェルディナンはつぶやきます。
そして、「なぜか、死の匂いを感じ始めてる」と言葉を継ぎます。
「後悔してるんでしょ」とマリアンヌ。
それには答えず、フェルディナンは「風景や木に死を感じる」といい、「女どもの顔や車にも」とつぶやき続けます。

(※ 前掲)
現実から逃避しようとして、マリアンヌに関わったフェルディナンは、新聞報道で突如、現実に引き戻されます。妻の言葉を聞いて、自分が置かれた状況を知り、絶望的な気分に襲われたのかもしれません。目にした風景や木、女性や子ども、車などの外界に、自身の気持ちを投影し、救いようのない思いに囚われていました。
ところが、マリアンヌは至って現実的に、自分たちの置かれた状況を認識しています。「一文無しで、どうするのよ」とフェルディナンを責め、「イタリアまでは無理」と不安感を顕わにします。マリアンヌとしては一刻も早く、フランス国外に出て、安心感を得たいのです。
それに対し、「行けるところまで、行く」と、フェルディナンは素っ気なく答えます。
「そこで何をするの?」とマリアンヌは尋ね、すぐに、「兄が見つかれば、お金をもらえるわ」、「そうすれば、ステキなホテルに泊まって、遊びましょ」と、彼女なりの解決策を口にします。
ところが、運転席のフェルディナンはそれには答えません。マリアンヌの言葉を耳にしながらも、何か別の事を考えているようです。
突如、後ろを振り返って、マリアンヌを嘲るように、「頭の中は遊びだけ」と言います。

(※ 前掲)
訝しく思ったマリアンヌが、「誰に言ったの?」と尋ねると、「観客さ」とフェルディナンは思い入れたっぷりに答えます。
マリアンヌは後ろを振り返って見ますが、もちろん、誰もいません。
「頭も狂ったのね」とマリアンヌ。気持ちの通じないフェルディナンに愛想が尽き果てたようです。「私は二度と恋なんてしないわ」とつぶやきます。
このシーンでは、二人の価値観、人生観の隔たりが明らかにされます。
■アンガージュマン(engagement)
興味深いのは、ゴダールがこのシーンで、観客を映画の展開に巻き込もうとしていたことでした。これまでは、ただ画面を観るだけだった観客を、ここで一気に、物語の展開に巻き込もうとしていたのです。
初めてこの映画を観た時、私はこのシーンをとても斬新だと思いました。というのも、ここにゴダールらしさを感じさせられたからでした。実存主義哲学の一端を見たような気がしたのです。
当時、フランス思想界が識者の間で注目を集めていました。サルトル(Jean-Paul Sartre, 1905 – 1980)はその中心人物の一人でした。
そのサルトルが提唱していたのが、「engagement」という概念です。「参加」と訳されますが、当時はもっぱら、政治的意味合いで使われていました。個人と社会とのかかわりが省察され、人間存在についての意義が論じられていました。
当時、サルトルを聞きかじっていた私は、社会的状況への参加を「engagement」と捉えていました。ところが、このシーンを見て、映画と観客の間に、「engagement」を組み込もうとするゴダールの意図を感じさせられたのです。
驚いたことに、ストーリーが進行する画面の中から、主人公が、画面の外側にいる観客に向かって、呼び掛けたのです。これは、一方的に流れる映画の展開に、いっとき、掉さすものであり、観客の意識を喚起するものでもありました。
それが当時の私の目には、とても斬新に思えたのです。
このシーンを見た時、私は、サルトルの「engagement」の概念を、この映画に持ち込もうとしているゴダールの試みに刺激されました。
観客にストーリーへの参加を促すことこそ、まさに、映画における「engagement」といえるものでしょう。このシーンは、ゴダールが作品と観客との間に、積極的な関わり合いを持ち込んだ仕掛けのように私には思えました。
そして、映画の存在意義を「engagement」の概念を介在させて見出そうとしているところに、当時のフランス思想界の影響を感じたのです。
ゴダールの知的嗅覚がいかに鋭いか、いかに思想の流行に敏感か、いかに強く、既存の映画セオリーから離れようとしていたかを感じざるをえませんでした。
さて、このシーンでは、享楽志向でリアリストのマリアンヌと、内省的でロマンティストのフェルディナンが対比されています。
何もこのシーンに限りません。ストーリーが展開するにつれ、一事が万事、二人の感性や価値観、人生観の大きな隔たりが際立つようになっていきます。
初めは、マリアンヌの外見や肉体に惹かれたフェルディナンでした。ところが、共に過ごす時間が長くと、徐々に、内面の隔たりの大きさが認識されていくようになったのです。
お金もなく、破天荒な逃避行を続けていく過程で、二人の感性、価値観、人生観、世界観の違いがことさらに際立っていきました。
決定的になったのが、海辺での原始的な生活でした。
■辿り着いた海
郊外を通り過ぎると、二人が乗った車はどんどん人里を離れていきます。
フェルディナンは、終に何かを悟ったかのように、「10分前は死を嗅いだが、今は逆」とつぶやきます。
海が見えてきたのです。
「見てごらん、海だ、波だ、空だ」と、晴れやかな顔つきを見せています。

(※ 前掲)
マリアンヌは甘えるように、フェルディナンにもたれかかっていますが、その表情はなんともいえず暗く、複雑です。
一方、フェルディナンは感極まったように、つぶやき続けます。
「人生は悲しくとも美しい」、
「突然、自由を感じ、思いのままにできる」
フェルディナンはどうやら、居場所を見つけたようです。
ところが、マリアンヌは、フェルディナンの心の底からのつぶやきを聞いても、ただ、「狂ってる」というだけです。
フェルディナンは、「行きつくとこまで、一直線に走るだけ」というなり、突如、ハンドルを切って、海にジャンプします。

(※ 前掲)
「地獄の季節」という字幕が画面に被ります。
■地獄の季節
『地獄の季節』(” Une saison en enfer”)は、フランスの詩人ランボー(Arthur Rimbaud, 1854-1891)の詩集のタイトルです。ランボーがポール・ヴェルレーヌ(Paul Marie Verlaine, 1884-1896)とともにロンドン、ブリュッセルに滞在していた期間(1873年4月から8月)に執筆されました。9編の散文詩から構成されています(※ Wikipedia 地獄の季節)。
それにしても、なぜ、このシーンに「地獄の季節」という字幕が挿入されたのでしょうか。
先ほどご紹介した解説によると、『地獄の季節』は、「異端」あるいは「黒人」から構想された詩集でした。つまり、社会に受け入れられず、馴染めず、周縁に置き去りにされた人々の観点から着想された詩集だったのです。
このことからは、ゴダールは、アウトサイダーとしてのフェルディナンに自身を重ね合わせ、その心情を表現しようとしていた可能性が考えられます。
アウトサイダーは、周囲からアブノーマルと思われ、「狂っている」の一言で片づけられがちです。非現実的なことを言うと、決まって、そのようにレッテル貼りをされ、非難されるのですが、フェルディナンもまた、逃避行の中で、マリアンヌから何度も「狂っている」と揶揄されていました。
「狂っている」というのが、どうやら、この映画のキーワードの一つだといえそうです。
それでは、ランボーの詩集『地獄の季節』と「狂っている」とが果たして、どのように関連しているのでしょうか。
試みに『ランボー全詩集』(Arthur Rimbaud、鈴木創士訳、河出文庫、2009年)から、「地獄の季節」を拾って読んでみました。
「地獄の季節」の9編の中には、「狂気」に関連すると思われる詩が2編ありました。「錯乱 I – 狂気の処女、地獄の夫 (Délires I – Vierge folle. L’époux infernal)」と、「錯乱 Ⅱ -言葉の錬金術(Délires II – Alchimie du verbe)」です。
このうち「錯乱 Ⅱ -言葉の錬金術」にフェルディナンの心情を表していると思われる散文詩がありました。
「ずっと前から、俺はあり得べきすべての風景を手に入れることができると自信満々で、現代の絵画と詩の名声など取るに足りないものだと思っていた。(中略)まずは習作だった。俺は沈黙や夜々を書き、俺は言い表せないものを書き留めていた。俺は眩暈を定着させたのだった」(※ 『ランボー全詩集』、前掲、p.47-48.)
念のため、ピックアップした箇所の原文を添えておきましょう。
「Depuis longtemps je me vantais de posséder tous les paysages possibles, et trouvais dérisoires les célébrités de la peinture et de la poésie moderne.(中略)
Ce fut d’abord une étude. J’écrivais des silences, des nuits, je notais l’inexprimable. Je fixais des vertiges.」
ランボーは、可能性のある風景はすべて手に入れることが出来ると思い込んでおり、現代の絵画や詩で有名なものは大したことはないと思っていたようです。そして、なによりも重要なのは、まず習作することだといい、沈黙や夜など、言葉で表現しきれないものを書き留めることによって、その高揚感を固定させたというのです。
このような解釈が合っているのかどうかわかりません。ただ、ランボーが現代の絵画や詩に見るべきものがないと思い、沈黙や夜など、言葉で表現しきれないものを書き留めていくことによって、眩暈にも似た高揚感を定着させることができたといっているところに、フェルディナンとの類似性を感じさせられました。
そして、フェルディナンは、海を見つけるのです。
「ついに、おお、幸福よ、おお、理性よ、俺は黒っぽい紺青を空から引っ剥がした、そして、生のままの光の黄金の火花となって、俺は生きた。喜びのあまり、俺はとんでもなくおどけて気違いじみた表現をとっていた」(※ 前掲、p.56.)
海を見つけたフェルディナンは、喜び勇んで、車ごと波間に突っ込んでしまいます。まさにランボーの詩のように、「喜びのあまり、とんでもなくおどけて気違いじみた」行動をとってしまったのです。
まさに、先ほどご紹介した、海に車ごとジャンプするシーンです。
■原始的な生活
車ごと海にジャンプした後、二人は浜辺で夜を過ごします。
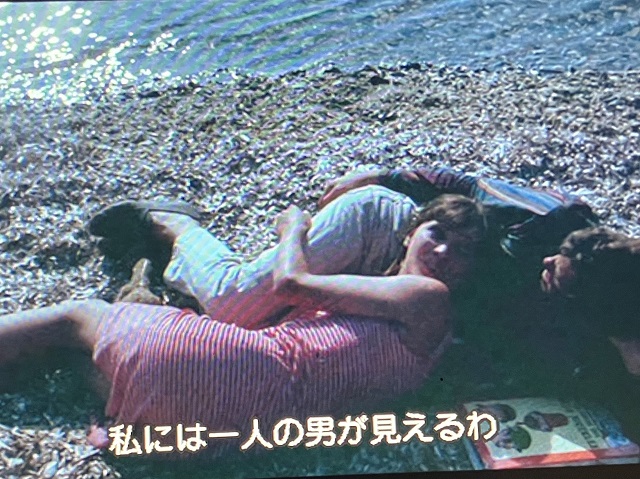
(※ 前掲)
「月がよく見えるね」とフェルディナンがいうと、マリアンヌは「私には一人の男が見えるわ」と答えます。このシーンでも、ロマンティストのフェルディナンと、リアリストのマリアンヌの違いが浮き彫りにされています。
二人の間に束の間、訪れた幸せのひと時でした。
島で原始的な生活が始まると、やがて、マリアンヌは退屈し始めます。「私に何ができるの」、「私は何をすればいいの」と海辺を歩きながら、繰り返します。人のいない生活、自然だけを相手に暮らす生活に耐えられないのです。
一方、フェルディナンは日記をつけはじめ、原始的な生活の中で得た着想をノートに記していきます。
「もう何も聞こえない、私は上昇する」、「私は幸福を見た、目の前で」、
「超自然的な激情で!」、「涙が流れ、しびれるほどに幸福で」、「鼓動は高鳴る」、といった具合に、フェルディナンは、次々と歓喜の心情をつぶやき、ノートに書きつけていきます。
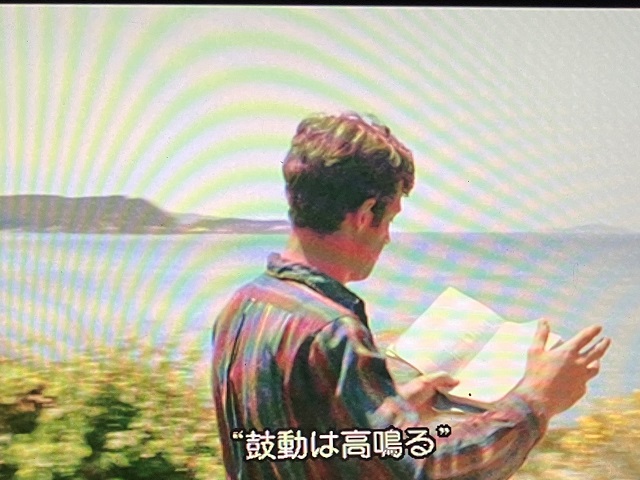
(※ 前掲)
所在なく浜辺を歩き続けるマリアンは、フェルディナンに近づくと、途端に、大きく声を張り上げます。
「静かに! 執筆中だ」と、フェルディナンは声を荒げます。
■創作の到達地点
海辺で原始的な生活をしながら、フェルディナンは本を読み、思いついたことをノートに書き綴っていきます。
「小説の構想を得たぞ」、「もう、人の生活は書かず」、
「人生そのものを、ただ、人生だけを書くつもりだ」とつぶやきます。
それが、フェルディナンが見つけた創作の到達地点でした。
そして、フェルディナンは観客に向かって、「人々の間には空間と」、「音と色彩がある」といいます。

(※ 前掲)
いかにも年季の入った高齢者の口ぶりで、フェルディナンは語っています。
ゴダールによれば、この時のフェルディナンの口ぶりは、俳優であり監督であったミシェル・シモン(Michel Simon, 1897-1975)の声色を真似たものだそうです(※ 前掲、『ゴダール全評論・全発言Ⅰ』、p.607-608.)。
そういわれてみると、高齢のミシェル・シモンの声色だったからこそ、その人生と見識の重みが、この短いフレーズに込められていたのかもしれません。
特徴のある声色がこのセリフに、人生そのものがもたらす情感を添えていたのです。
このシーンでフェルディナンは、「人の人生」ではなく、「人生そのもの」を書くのだといい、さらに、「人々の間には空間と、音と色彩」があるという認識を示しています。
つまり、人が生きてきた来歴を描くのではなく、人と人との間にあるもの、それも、音や色彩を含めた経験そのものを書くといっているのですが、このセリフを、老いたミシェル・シモンの声色で語らせることによって、ゴダールが抱いている世界観と、究極的で包括的な概念を表現することができていました。
ゴダールは、言語では言い表せないようなものまでも言語で捉えようとしていました。人と人との間にある空間や音、色彩など、言語化できず曖昧模糊としたものを、言語で包括的に把握しようとしていたのです。そのために、このシーン前後のセリフは敢えて脱文脈化しようとしていたような気がします。
その一方で、彼はノートに、「自然と向き合う人間」、「言語の描写力」と書きつけていました。創作は言葉によるものでなければならないという思いも強かったのでしょう。
こうしてみてくると、日々、向き合っている自然、あるいは外界を言葉によって認識し、言葉によって描写し、表現していくというのが、フェルディナンの創作の到達地点であり、また、ゴダールにとっての創作の到達地点でもあったといえます。
ゴダールは映画製作について、次のように語っています。
「書くということがすでに、映画をつくるということだった。というのも、書くことと撮ることの間には、量的な違いはあっても、質的な違いがあるわけじゃないからだ。(中略)ぼくにとっては、自分を表現する方法のすべてが互いに密接に結びついているわけだ。すべてがひとかたまりをなしているわけだ。そして問題は、自分に適した側からそのかたまりととりくむすべを知るということなんだ」(※ Jean-Luc Godard、奥村昭夫訳、『ゴダール全評論・全発言Ⅰ』p.490.、筑摩書房、1998年)
これは、初期の映画4本が製作された後、ゴダールがインタビューされた時に、答えたものです。
ここでゴダールは、「書くことがすでに映画をつくること」といい、「自分を表現する方法すべて互いに密接に結びついている」といっています。このようなゴダールの考えを知ると、画面の中でフェルディナンが言おうとしていたことの意味がわかるような気がしました。
それでは、引き続き、フェルディナンのつぶやきを聞いてみることにしましょう。
■キュビズムとの親和性
創作の到達地点に達したと思ったからか、フェルディナンはさらにつぶやき続け、「そこへ到達するのだ」、「ジョイスが試みたがー」、「我々はもっとよくなるはずなんだ」と語ります。
「ジョイスが試みたがー」というセリフを聞いて、ゴダールがこのシーンで何を言おうとしていたのかがわかるような気がしました。
ジョイス(James Augustine Aloysius Joyce、1882-1941)といえば、アイルランド出身の詩人であり、小説家です。『ユリシーズ』(Ulysses, 1922)、『フィネガンズ・ウェイク』(Finnegans Wake, 1939)といった代表作があります。
バージニア・ウルフなどとともに、ジョイスはモダニズムの作家として知られています。
そのジョイスが「試みた」ことを、ゴダールは、「我々ならもっとよくなるはず」とフェルディナンに語らせているのです。つまり、言葉の紡ぎ手であるジョイスは文学の領域で実験的方法を試みたが、それは、映画製作者である「我々」なら、もっとうまくできるはずだというのです。
ジョイスが試みた手法とは一体、どういうものなのでしょうか。
木ノ内敏久氏は、ジョイスの作品はキュビズムと共通性があるとし、次のような共通点を挙げています。
すなわち、①時空の概念の変容、②断片・素材の寄せ集めから統一的なイメージをつくるコラージュ、③過去の芸術様式の取入れ、です。
これらの共通性に基づき、「外の空間は遠近法に基づいた単なる幾何学的媒体ではなくなり、自己認識や経験という内なる精神の働きとつながって、時間と空間の関係が新しく組み直される。現実世界が知的操作により再構成される過程が双方に認められるのである」と総括しています(※ 木ノ内敏久、「ジェイムズ・ジョイスと美学」『ソシオサイエンス』Vol.15. pp.77-92. 2009年3月)。
つまり、外界は単なる客体ではなく、主体との精神的なつながりの下、知的操作が加えられ、再構成されるという認識でした。これが、モダニズムといわれる潮流の一側面です。
モダニズムは20世紀前半に終焉を迎えたリアリズムの後に発生した芸術活動ですが、キュビズムの絵画であれ、ジョイスが試みた文学であれ、創作に際しては、認識の多様性あるいは意識の流れが重視されていました。
『気狂いピエロ』が製作された60年代半ば、ゴダールはそのモダニズムを踏まえ、さらなる表現を模索していました。
■脱文脈の構造
モダニズムを経たゴダールが、伝統的な語りの方法を採ることはありませんでした。映像と音声で線的な構造の下、物語を紡いでいくという手法は、もはや商業映画でしか見られなくなっていたのです。
『気狂いピエロ』の後半で、ゴダールは、主人公フェルディナンが日記をつけるという設定にしていました。フェルディナンが内省的な思いを日記に記すとともに、つぶやくという語りの形式です。
内省的なものであれ、抽象的なものであれ、彼の言葉には人を引き付ける力がありました。そのつぶやきによって、観客は彼の内面を読み、意識の流れを追い、シーンの断片から透けて見えるゴダールの世界観、人生観を把握することができたのです。
ゴダールはまさに、語りの脱文脈化を図っていたといえるでしょう。
脈絡のないストーリー展開、意表を突く人物の登場などにも、脱文脈化の意図が見受けられます。もちろん、背景にも、脱文脈化された小道具が使われていました。
たとえば、後に、マリアンヌが小人をハサミで殺すことを暗示したシーンでは、背後の壁にキュビズムの画家・ピカソの絵が飾られていたのです。

(※ 前掲)
観客は、小人とマリアンヌがどういう関係なのか、ストーリー展開のなかで小人がどういう役割を占めているのか、皆目、わからないまま、画面を見ています。否応なく画面に参加させられているわけですが、この脈絡のなさが作品に奇妙な厚みをもたらしていました。
ゴダールはこのように、後半から一気に脱文脈化を進めています。多方向に断片化し、ディテールだけが印象に残る仕掛けの中で、線的構造の下では捉えられない現実を表現したいたのです。
フェルディナンが発した数々の言葉には、ゴダールの思いが色濃く反映されていました。そこには、当時のフランス思想界、西洋芸術の動向、文学の潮流などが、断片的に散りばめられており、まるでゴダールがフェルディナンに憑依しているかのようでした。
ゴダールは次のように語っています。
「プロデューサーたちに言わせれば、ゴダールに映画を撮らせると、ジョイスだとか形而上学だとか絵画だとか、自分の好きなことを語ろうとする、でもその映画にはいつも商業的側面が含まれることになるはず」(※ 前掲、『ゴダール全評論・全発言Ⅰ』、p.508.)
『気狂いピエロ』はフランスとイタリアの合作映画で、制作費は50万ドルかかっていました。日本円に換算すると、当時は1ドルが360円でしたから、約1億8千万円もかかっていたのです。ところが、制作費を回収しきれず、ゴダールにいわせれば、「経済的には失敗作」でした(※ 『ゴダール映画史』、前掲、p.331.)。
脱文脈化を追求しすぎた結果といえるのかもしれません。
■ヌーヴェルヴァーグとして評価
『気狂いピエロ』はフランスとイタリアの合作映画でした。それだけに、もしベルモンドが主演しなければ、製作許可すら取れなかった可能性もありました。ベルモンドはゴダールの前作『勝手にしやがれ』に出演し、一躍、有名スターになっていました。
『勝手にしやがれ』は、ゴダールが1959年に、ベルモンド(Jean-Paul Belmondo, 1933-2021)とジーン・セバーグ(Jean Seberg, 1938-1979)を起用して製作した作品です。これがヌーヴェルヴァーグの代表作として大ヒットしていました。それに伴い、個性的な俳優ベルモンドがスポットライトを浴びていたのです。
それまでゴダールが製作した作品の中で、『勝手にしやがれ』ほど、商業的価値が高いものはありませんでした。この映画の商業的成功とベルモンドの起用は、イタリア側プロデューサーを説得するには十分な材料でした。
ところが、『気狂いピエロ』で、ゴダールはさらに独自色を強めました。シナリオがあっても無いのも同然で、その場で即興的に演出することが多かったのです。すべては撮影の段階で創り出されるというのがゴダールの映画製作のやり方でしたが、それがさらに徹底されたのです。
俳優が対応しきれないのも無理はありません。
実際、出演を快諾したベルモンドでさえ、『気狂いピエロ』の撮影中に、「これは映画じゃない」とゴダールにいったことがあったそうです。さらに、この映画のイタリア側のプロデューサーも、「これは映画じゃない」といい、イタリアでは公開しなかったといいます(※『ゴダール映画史』、前掲、pp.330-331.)。
ちなみに、ベルモンドはその後、ゴダールが出演依頼をしても承諾していません。それほど、『気狂いピエロ』に出演したことを後悔していたのかもしれません。当時、これは映画の概念から外れた映画だったのです。
もっとも、一部の批評家あるいは識者からはその斬新性が評価されていました。1965年には、先行上映したヴェネツィア映画祭で新進批評家賞、そして、英国映画協会賞を受賞し、ヴェネツィア国際映画祭では金獅子賞にノミネートされました。その翌年の1966年、カイエ・デュ・シネマ最優秀作品賞受賞を受賞しています(※ https://www.imdb.com/name/nm0000419/awards)。
この作品でゴダールは経済的には失敗したかもしれませんが、ヌーヴェルヴァーグの映画監督として世界に名を馳せたのです。
ゴダールは次のように語っています。
「ぼくらには金のかかる映画はつくることができない。テレビにかかわることもできない。だから、ぼくは、自分が今いる場所について、労働について、家族について語りながら、金のかかる映画とかテレビとかに少しも劣らないほどおもしろい映画をつくろうと努めている。ぼくは自分がよく知らない場所については語ろうとしない。あるいは語る場合は、その場所に、ぼくが今いる場所を通過させることにしている」(※ 『ゴダール全評論・全発言Ⅱ』、前掲、p.170.)
ゴダールのいうように、製作費をかけられないという制約が、ヌーヴェルヴァーグを生み出したのでしょう。即興演出、同時録音、ロケを中心とした撮影といったゴダール独特の手法は、確かに製作費節減になりました。だからといって作品の質が落ちたかといえばそうではなく、作品に瑞々しさや生々しさを添える効果が見られました。
『気狂いピエロ』は当時、世界の知識層の話題を集め、今に至るまで語り継がれてきました。
今回、改めてDVDでこの作品を観ましたが、当時、感じた斬新さに少しも陰りがなかったことが驚きでした。半世紀上も前に製作された作品ですが、脱文脈し、画面に観客を参加させようとする仕掛けが興味深く、古臭さを感じさせられることはありませんでした。
むしろゴダールが採った映画製作の手法は、デジタル化によって線的構造が無効になりつつある現代社会との親和性が高いように思えました(2023/2/18 香取淳子)。