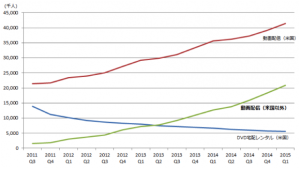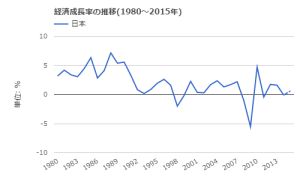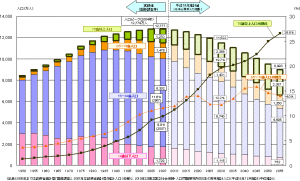■上野の森美術館大賞
報告が遅くなってしまいました。
2016年5月5日、第34回上野の森美術館大賞展(4月27日~5月8日)に行ってきました。祝日だったので上野公園は家族連れでにぎわっていましたが、この展覧会は会期も終わりに近づいていたせいか、それほど混み合っておらず、ゆっくりと作品を鑑賞することができました。
今回、全国から712名、1011点の作品が応募されたそうです。その中からまず、164点が入選作品として選ばれ、次いで、一次賞候補が29点、賞候補が13点、最終的に受賞したのが5点でした。8名の審査員による厳正な審査の結果です。
日本の美術界を担う可能性のある作家として受賞したのは、大賞1名、優秀賞4名の計5名、いずれも23歳から33歳までの若手画家でした。
大賞が井上舞氏の『メカ盆栽~流れるカタチ~』(日本画)、優秀賞で彫刻の森美術館賞が菅澤薫氏の『赤い蜘蛛の巣』(油彩)、優秀賞でフジテレビ賞が粂原愛氏の『反芻する情景』(日本画)、優秀賞でニッポン放送賞が成田淑恵氏の『Voice』(油彩、アクリル)、優秀賞で産経新聞社賞が櫻井あすみ氏の『fragments』(日本画)でした。プロフィールを見ると、1983年から1993年生まれですから、21世紀に入ってから創作活動を始めた画家たちです。
上野の森美術館の館長は、本展カタログの冒頭で、「“明日をひらく絵画”を掲げてきた本展にふさわしい、とりわけ若い作家の5点が入賞作品に選ばれました」と書いています。
公募要項を見ると、「日本画・油絵・水彩画・アクリル画・版画などの素材の違いや、具象・ 抽象にかかわらず、既成の美術団体の枠を越え、21 世紀にふさわしい清新ではつらつとした絵画作品を公募します」と記されています。
こちら →http://www.ueno-mori.org/exhibitions/main/taisho/boshuyoko.pdf
最終審査では、この展覧会の「明日をひらく」という主旨の下、「21世紀にふさわしい清新ではつらつとした絵画作品」という観点が重視されたのでしょう。たしかに、どの受賞作品にも激動する21世紀社会の片鱗が描出されており、見応えがありました。
■『メカ盆栽~流れるカタチ~』
受賞作品の中でもっとも印象に残ったのは、大賞を受賞した井上舞氏の作品、『メカ盆栽~流れるカタチ~』でした。
受賞した5作品は隣り合って展示されていたのですが、私はこの作品にもっとも心惹かれました。一枚の絵の中に21世紀日本の諸相が的確に捉えられ、その特徴が見事に表現されていると思ったからです。モチーフの取り上げ方、構図、色彩の配置など、いたるところに熟慮の跡がうかがえます。一目見て美しく、しかも、観客を考えこませる奥深さがあるのです。感動してしまいました。
モチーフはマツの木の盆栽です。枝ぶりや幹の肌、植木鉢からはみ出しそうになった根の形状から、このマツが古木であることがわかります。幹の肌の一部は枯れて白くなり、裂け目がいくつも入っています。しかも、それが下方に長く垂れ下がり、その先の方まで白くなっていますから、このマツの木が相当長い年月、生きながらえてきたこともわかります。
枝の重みでマツの木は折れ曲がり、下方に長く、複雑に湾曲しながら伸びています。白い枝は下に垂れるにつれ、細くなっていき、着地した後、再び、上方に伸びようとしています。この個所はとくにしなやかで、したたかな生命力を感じさせられます。
細い枝先には小さな松葉がついています。ところどころ緑の松葉が配されているせいか、長く垂れ下がった白い枝はまるで険しい山肌を流れ落ちていく水のようにも見えます。枯れた枝の白さは画面に奥行きを与えるだけではなく、水の流れを感じさせるリアルな動きを生み出しているのです。山水画では水そのものが生命の根源とされています。ですから、水の流れを思わせるこのマツの盆栽の色彩や形状からは、風雅な山水画さえ連想されます。
さて、植木鉢の中で異彩を放っているのが、マツの木の根元です。大きく膨らみ、植木鉢からはみ出しそうになっています。よく見ると、枯れたマツの白い枝に絡まるようにして金属製の導管、あるいはゴム管のようなものが見えます。大きく裂けた根元に入り込んで、まるで枯れた白い枝を支えるかのように配されています。パッと見ただけでは気にならなかったのですが、よく見ていくと、この金属製の導管が気になってきます。
■機材や工具との調和
手掛かりを求めてカタログを見ると、井上舞氏はこの絵について、次のように記しています。
*****
私は、もともとエンジンやモーターなどの機械、工場を見るのが好きで、この作品のタイトル「メカ盆栽」は大学1回生の頃の総合基礎実技という共通課題で作った立体作品をきっかけに、「平面で描いてみたいな」という思いから生まれました。
*****
(第34回上野の森美術館大賞展カタログ、p.10より)
井上氏が「エンジンやモーターなどの機械を見るのが好き」だと知って、なるほどと合点しました。金属製の導管や工具の部品のようなものがとてもリアルに描かれているのに、絵として違和感があるわけではなく、ごく自然に盆栽のモチーフに溶け込んでいるのです。導管や工具のカタチや色彩に詳しくなければ、これほどまでに盆栽に調和させることはできなかったでしょう。自然と人工物が一体化し、21世紀ならではのモノのカタチが創り出されているのです。おかげでこの作品に深みがでたように思います。
一方、植木鉢を置いたスタンドは、脚部こそはっきりと描かれていますが、台座部分はあいまいに処理されています。そのせいでこの作品は、日本の国旗のように見える植木鉢の赤い丸の模様、横に広がる緑色の松葉、さらには、自在な曲線を描く白い枝ぶりといった要素がひときわ目立つ構成になっています。つまり、マツの葉姿、枝ぶり、鉢、それぞれをたっぷり鑑賞できる構成になっているのです。なにより、枯れた白い枝によって強調されたさまざまな曲線がこの絵に生き生きとした動きを添えていることに私は惹かれました。
マツの盆栽といえば、日本文化の象徴の一つであり、また、高齢者文化の一つといえるでしょう。それをメインのモチーフにしながら、井上氏はさり気なく、枯れた白い枝のほぼすべてに金属製の導管や工具を絡ませています。ですから、この盆栽が、金属製の導管や工具に支えられてようやく、その生命を維持しているように見えますし、高齢化が進む一方で、機械的処理に依存せざるをえなくなった21世紀の日本社会を象徴しているようにも見えます。
■流動化
先ほど述べましたように、この作品では、植木鉢を載せたスタンドの台座部分とその周辺をぼかして描かれています。その結果、盆栽はしっかりと観客の目に印象づけることができますが、植木鉢は宙に浮いて見えます。そのことによって、この盆栽自体がまるで居場所を失って漂流しているように見えます。カタチが流れているのです。そういえば、この作品のタイトルは、『メカ盆栽~流れるカタチ~』でした。
「流れる」という概念もまた、グローバル化の進行に伴い、漂流しはじめた日本文化を象徴しているといえます。デジタル技術によってグローバル化が加速され、ヒト、モノ、情報の流動化が進んでいます。まるでこの絵のように、すべてがその存在基盤を失いつつあります。このような現代社会の様相を考えると、『メカ盆栽~流れるカタチ~』の現代的価値がよくわかります。
盆栽をモチーフに、高齢化し、機械的処理の浸透した21世紀の日本社会を見事に浮き彫りにする一方で、「流れる」要素を取り込んだ構図から、流動化し、漂流しはじめた現代社会を端的に切り取っています。観客からさまざまな思いを引き出す力を持った作品だと思いました。
その他の受賞作品もどれもレベルが高く、見応えがありました。いずれも現代社会に仕組まれた歪みが端的に捉えられ、訴求力のある絵画作品として仕上げられているところに特徴があると思いました。
■『栗の眼差し』
入選作品の中にも見るべき作品がいくつもありました。とくに印象づけられたのが、近藤オリガ氏の『栗の眼差し』です。
この作品を見ると、まず、濃密な画面に惹きつけられてしまいます。描かれたモチーフの意味よりも、キャンバスの上に油絵具で表現された絵画空間そのものに引き込まれてしまうのです。描き方自体が異彩を放っていたからでしょう。画面全体からなんともいえない清らかな静けさが漂ってくるのが印象的です。
こちら →
(162×130㎝、油彩。カタログをうまく撮影できませんでした。実際はもっと透明感のある色彩で、とても迫力があります)
モチーフは、栗のトゲの部分と割った殻の中に入れ込まれた目玉です。モチーフそれぞれは誰もが知っているものですが、なんとも奇妙な取り合わせです。とはいえ、別に違和感はなく、見ているうちにいつの間にか、日常の空間を超え、はるか遠くに誘い寄せられていくような気持になっていくのが不思議です。
なぜ、このモチーフが選ばれたのかわかりませんし、画面にどのような意味が込められているのもわかりません。この絵の意味もわからないのに、なぜか引き込まれてしまうのです。
まず、精緻な筆遣いと深い色調がきわだっています。まるで超高感度カメラのように精巧にモチーフを写し出しているように見えながらも、実は、ヒトの目を通してしか見えない形や色、トーンが創り出されているのです。密度が高く、独特の美しさを湛えた絵画空間が生み出されています。よく見ると、必ずしもリアルではないのですが、フィクショナルなリアリティがあります。おそらく、それが、観客の気持ちを捉える要素の一つなのでしょう。
たとえば、トゲの描き方を見てみましょう。左側のトゲはまるで毛皮のような密度と柔らかさがあります。ところが、下方のトゲにはしっかりとした強さとしなやかさが添えられています。支えるだけの強度が必要だからでしょうか、一つ一つが大きく、力強く描かれているのです。そして、右側のトゲは逆光の中でその存在感が弱められながらも、トゲ本来の堅さと鋭さが表現されています。トゲの描き方ひとつとってみても、このように、場所ごとに、トゲの色、質感、明るさ、彩度などが微妙に異なって描き込まれているのです。しかも、それぞれが接している背景の色味と見事に調和しており、フィクショナルなリアリティが生み出されています。
■フィクショナルなリアリティ
それにしても、なぜ、栗のトゲと眼玉がモチーフなのでしょうか。カタログを見ても、説明文は載せられていませんでした。勝手な推測をするしかありません。まず、栗を考えてみることにしましょう。
そもそも栗の実は、無数のトゲで覆われた堅い殻の中に入っており、何重にも保護され、外部から守られています。
栗の実は一つの殻の中にだいたい2~3個入っているといわれています。まるで家族のように、身を寄せ合って、一つの殻の中に入っているのです。ちなみに、栗は、「純潔」の象徴とされているようです。
こちら →http://www.catholictradition.org/Saints/signs4.htm
無数のトゲで覆われた堅い殻の中に、実は大切にしまいこまれています。このような状態では誰からも傷つけられることはありません。厳重な保護下に置かれているからこそ、「純潔」の象徴とされているのでしょう。
上の写真で実際の栗のトゲを見てから、この作品を見ると、この栗のトゲがいかに現実とは異なって描かれているかがわかるでしょう。ところが、高感度カメラで捉えたかのようなリアリティがあります。現実とは異なっているのに、栗のトゲがいかにも細密に描かれているように見えるのです。それはおそらく、この作品にフィクショナルなリアリティがあるからでしょう。そして、リアルに見えて、実はリアルではないからこそ、二つとない美しさが表現されるのかもしれません。近藤オリガ氏の手にかかれば、なんの変哲もない栗のトゲがこのように優雅でしなやかな美しさを見せるようになることがわかります。
■モチーフとしての「眼差し」
さて、この作品では密集したトゲで覆われた殻の中に、栗の実ではなく、グリーンの目玉が入っています。トゲで覆われた栗の殻の中にどういうわけか、大きな目玉が描かれているのです。こちらは吸い込まれるようなグリーンの色合いで、透明感があります。思慮深さを思わせる、透明感のある奥深さです。
目は直接、外部に接していますから、身体部位の中では弱く、繊細な器官の一つです。しかも、「見る」という重要な役割を担っていますから、厳重に保護されなければならないのは確かです。ですから、この目玉が、トゲで覆われた堅い殻の中に入れられているのに違和感はないのですが、なぜ、この取り合わせでモチーフが選ばれたのでしょうか。近藤オリガ氏はこのモチーフを描くことによって、何を語ろうとしたのでしょうか。
タイトルしか読み解く手がかりはありませんが、そのタイトルは、『栗の眼差し』です。これは「gaze of chestnut」なのでしょうか、それとも、「eyes of chestnut」なのでしょうか。「chestnut eyes」なら、文字通り、栗色の目のことですが、この作品の目は濃いグリーンです。とすれば、この絵のモチーフはやはり、「gaze of chestnut」なのでしょう。堅い栗のトゲと殻で守られた「濃いグリーンの目」が何かを見ている・・・、その何かを見ている「眼差し」に意味があるのかもしれません。
そこで、「green eyes」が何を意味しているのか、調べてみると、「green-eyed monster」という語から派生して、この語には「嫉妬の目」という意味があるようです。とすれば、この作品の栗のトゲは外部から目を守るというより、むき出しになっているグリーンの目(嫉妬の感情)を外部に見せないように防いでいるということになるのでしょうか。
ひょっとしたら、この作品にそのような象徴的な意味は込められていないのかもしれません。Wikipediaによると、グリーンの目を持つヒトは、「南ヨーロッパや東欧や中東、中央アジアにも多少見られるが大半は北ヨーロッパに集中している」そうです。だとすれば、東欧出身の近藤オリガ氏にとって「グリーンの目」は見慣れた目なのでしょう。いずれにしても、この絵を見ていると想像力がさまざまに刺激されます。
■現代社会を切り取る視角
第34回上野の森美術館大賞展では、見応えのある作品が数多くみられました。その中で私がもっとも心惹かれたのは、大賞の『メカ盆栽~流れるカタチ~』と入賞作品の『栗の眼差し』でした。いずれもとても印象深い作品です。
絵画には、観客がその意味を読み解くことができるように思える作品もあれば、そうではない作品もあります。今回、たまたま、その両極端の作品二つを取り上げることになりました。井上舞氏の作品は、過去、現在を踏まえ、未来を見通す力に溢れた作品でした。21世紀の現代社会を切り取る視角が明確に示されていたからこそ、そう思えたのでしょう。
一方、近藤オリガ氏の作品は、手掛かりが少なく、その意味を読み解くことができませんでした。そのせいか、どこか気になるものが残ります。絵を見て感動すれば、なぜ感動したのか、観客はその理由を求め、半ば条件反射的に作品を読み解こうとします。
観客は、絵画を納得できる恰好で読み解くことができ、個々の解釈の体系に収めることができてようやく安心するのでしょう。絵を見たときに感動し、作品の意味が理解できてはじめて、観客は満足するといっていいのかもしれません。
もっとも、理解できるモチーフを使いながら、その意味がわからない作品もまた、21世紀の現代社会の深層から生み出されたものだといっていいのかもしれません。21世紀の現代社会の中では、大量の情報が氾濫しています。ともすれば、モノや事柄はステレオタイプ的な意味が付与されがちですし、思考のプロセスも簡略化されがちです。
その結果、人々の理解の幅が狭まり、多様性が失われがちになっています。それだけに今後ますます、ステレオタイプ的な解釈が許されず、複雑な思考回路を経て制作された絵画を鑑賞することの重要性が増していくのかもしれません。(2016/5/22 香取淳子)