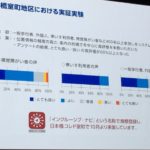■子どもの日の入間川
ゴールデンウィークだというのに、街角は人影もまばらで、閑散としています。ちょっと前まではスーパーでよく見かけていた子どもの姿も、入店規制されるようになったせいか、最近はほとんど見かけなくなりました。誰もが家に引きこもっているのでしょうか。
それでも、スーパーではショウブが売られていました。子どもの日が近づくと、必ず、店頭に並ぶ季節商品です。入口付近に置かれているのを見かけると、わたしは、半ば条件反射的に、手を伸ばしてしまいます。
手にした途端に、鼻を衝くのが、ちょっとクセのあるショウブの匂いです。他では経験したことのない、あの独特の香りに誘われるように、私の脳裏に、実家のヒノキの浴槽に浮かべられたショウブの葉が蘇ります。
毎年、子どもの日になると、母はショウブを湯船に入れ、子どもたちを入浴させていました。ショウブ湯に浸かると、年中、健康でいられると言いながら、長いショウブの葉を湯に浮かべるのです。
子どものころの私は、ショウブの匂いがあまり好きではありませんでした。ところが、母が毎年、子どもの日になると、決まってショウブ湯を使わせるので、いつしか、当然と思うようになってしまいました。
母は年中行事を大切にする人でした。子どもの日に、ショウブ湯や粽、柏餅を欠かすことはありませんでした。ショウブにしても、粽や柏の葉にしても、どれも香りの強い植物です。とくに独特の香りを放つのがショウブでした。
スーパーでショウブを見かけると、つい、買い求めてしまうのは、おそらく、ショウブが放つあの独特の香りのせいでしょう。あの香りがトリガーとなって、過ぎ去った子どもの日を再び、甦らせ、息づかせてくれるのです。
5月5日、入間川遊歩道を訪れてみました。
並木の緑は、わずか数日のうちに、いっそう濃くなっていました。時が駆け足で過ぎ去っていったのをこの目で確認しているようでした。この季節は葉の色や形、大きさが激しく変化します。可視化されているだけに、いっそう、時の過ぎるのが速いように思えるのでしょう。
■シャガ
入間川遊歩道を歩いていると、路辺に小さな菓子箱が置いてありました。
菓子箱の中には、引き抜いたばかりの草のようなものがいくつも入っています。そういえば、以前、ここには、スイセンの球根が置かれていたような気がします。
足を止めて、改めて見てみると、「どうぞご自由に シャガ」と書かれた紙札が添えられています。この草のようなものは、おそらく、「シャガ」という植物なのでしょう。
すぐさま、スマホで検索してみると、アヤメ科の植物で、多年草だと説明されており、花弁の写真が掲載されていました。
模様入りの見事な花弁です。ただの草がこんなに綺麗な花を咲かせるようになるのでしょうか・・・。だとすれば、きっと、この辺に生えているはずだと思い、周辺を探してみました。
道路に降りてみると、土手にスマホで見たのと似たような花が咲いているのを見つけました。
こちらは白ではなく、青紫ですが、ひらひらした花弁の形状が似ています。近づいてみることにしましょう。
こうしてみると、遠目には似ているように見えましたが、近づいて見比べてみると、なんだか少し違うような気がします。花の形状や模様が明らかに異なっています。シャガは模様入りと白の花弁が交互に組み合わされていましたが、こちらはそうではなく、縦に繋がって花が咲いています。しかも、シャガにはあった黄色と後の細かい斑点模様が、こちらにはないのです。
ひょっとしたら、別の花かもしれません。気にしないで歩き進めることにしました。
■川辺で遊ぶ子ども
川の方から子どもの声が聞こえてきました。見ると、河川敷には子どもや大人が数人、何やらのぞき込んでいます。川面に彼らの影が映り込み、のどかな光景が見られました。
その近くに、青い小さなテントのようなものが見えます。どうやら、傍らで大人が座り込んでいるようです。ひょっとしたら、テントの中で子どもが休んでいるのかもしれません。
新型コロナウイルスのせいで、外出自粛が続いています。学校は休校になり、図書館、遊園地、公園も閉鎖です。いま、子どもたちの行き場はどこにもないのです。だからといって、いつまでも家に閉じ困っているわけにもいきません。親は思案の末、子どもの日ぐらいは・・・、という思いで、河原に家族で繰り出してきたのでしょう。
河川敷には、のびやかな子どもたちの声に交じって、大人の声が響いていました。
少し歩くと、川の中に入っている子どもがいました。周囲に保護者のような大人はいませんから、おそらく、地元の子どもたちなのでしょう。
それぞれ網のようなものを持ち、夢中になって、川面を覗いています。小魚でも獲っているのでしょうか。
しばらく佇んで、子どもたちの姿を見ていると、桜木の葉を通して快い風がさぁーと吹いてきます。それがなんともいえず爽やかで、久しぶりに、気持ちが和んでいくような気がしました。
のどかな光景が目の前に広がっており、気持ちが癒されました。
■ショウブの葉が連想させる刀身
遊歩道に目を転じると、柔らかな陽光が、桜木の幹や枝の陰影を、路面にくっきりと刻み込んでいるのに気づきました。
木々の隙間から漏れた陽射しはそのまま伸びて、道路脇の草むらを柔らかく照らし出しています。まるでそこだけスポットライトを浴びたかのように、すらっと伸びた葉の形状が鮮やかに、浮き彫りにされていました。
普段なら、きっと見過ごしてしまっていたでしょう。ところが、この時ばかりは、足を止めずにはいられませんでした。何の変哲もない草むらが陽光を浴びて、ひときわ輝いていたのです。まるで見てほしいといわんばかりでした。
長く伸びた陽射しが、ありふれた光景を非日常の世界に変貌させていました。際立っていたのが、手前に群生している草です。一本、一本、根本から明るく照らし出されており、まるで剣のような鋭利さを見せています。
周囲の草むらに沈み込み、存在感もなく群生していた葉が、陽光に照らされた途端に、主役になりました。まるでスポットライトを浴びているかのように、その葉の長さと形状がくっきりと浮き立ち、刀身のようでした。
近づいてみると、先日、スーパーで買い求めたショウブとそっくりでした。背が高く、葉が剣のような形状をしています。手で触れてみると、しっかりとした厚みがあり、まさしく、先日、浴槽に浮かべたショウブと同じ感触でした。
刀身のような葉を見ていると、なぜ5月の節句を男の子の節句としたのかがわかるような気がしてきました。
ショウブ(菖蒲)の形状は刀身を連想させるばかりか、ショウブは「尚武」(武道)と発音が同じです。
慶應大学教授の許曼麗氏は、「菖蒲」の読み方について、次のように説明しています。
「萬葉集には菖蒲を詠んだ歌が十三首ある。ところが、この菖蒲について、古代の歌人たちは「あやめ」と混同していたようである。萬葉歌においては、表記は「昌蒲」、「菖蒲」、「安世女(売)具佐(左)」など様々であるが、いずれも、アヤメ、又はアヤメグサと読ませている。菖蒲(草)を詠んだ歌も、すべてアヤメ(グサ)と読ませている」(※ 「和歌が語る端午の様相」『慶應義塾大学商学部創立五十周年記念日吉論文集』、pp.97-108. 2007年)
古来、菖蒲はアヤメと呼ばれてきたと許氏はいいます。それが、鎌倉時代になって、ショウブと呼ばれるようになったそうなのです。次のように記しています。
「鎌倉時代になり、菖蒲は「アヤメ」ではなく、「ショウブ」すなわち、尚武という意味が加えられ、伝来の歳時行事と渾然一体となり、現代生活の中、我々もよく知っている単語の節句の形を成したのである」
古来、「アヤメ」と呼ばれてきた菖蒲が、鎌倉時代になってから、尚武という意味を付加するため、「ショウブ」になったと指摘しています。武家社会の価値観を反映し、「菖蒲」の呼称に変化が生じたというのです。5月5日を男の子の節句として武者人形を飾る風習もこれで理解できました。
そもそも端午の節句は、中国から伝来した生活行事でした。
許氏は、「五月は悪い月である。そのため、禁忌が多い」とし、「五色の糸で香袋を縫っては体に付けたり、粽を食べたり、雄黄酒を額に塗ったりする。または艾草で人形(艾人)を、菖蒲で蒲剣を作って家の扉に飾る」と記しています(※ 前掲)。
日本では五月の節句は子どもの日、あるいは男の子の節句とされていますが、中国では五月は忌月とされており、端午節には避邪除災の行事が集中しているようです。中国から伝来してきた生活文化も、長い年月を経るうちに、日本社会に合うようアレンジされてきたのでしょう。
ショウブは古来、薬効があるとされてきた植物の一つでした。そのせいか、ショウブ湯に入るという風習はいまなお、続いています。中国から伝来してきた行事のうち、健康志向のものは日本の生活文化として根付いているといえるのかもしれません。
■マムシに注意!
遊歩道をさらに歩いていくと、巨大な桜木の下に、妙な立て看板がありました。
「マムシに注意!」と大きな赤い字で書かれています。これを見た途端、こんなところにマムシが出るのかと驚いてしまいました。マムシの名前は知っていますが、私はこれまで、一度も見たことはありません。
それだけにこの看板にはちょっとした違和感を覚えてしまったのですが、桜木の下で生い茂る草むらを見ているうちに、ひょっとしたら、本当にマムシが出るのかもしれないと思えてきました。
というのも、江戸東京博物館で開催された「江戸と北京~18世紀の都市と暮らし~」という展覧会で見た、子どもの腹かけに蛇の絵が描かれていたことを思い出したからでした。
この展覧会を鑑賞したのは2017年4月8日でしたが、いまだに印象に残っています。特に印象に残っているのが、子どもの腹かけでした。(※ http://katori-atsuko.com/?s=%E6%B1%9F%E6%88%B8%E3%80%80%E5%8C%97%E4%BA%AC)
中国では端午の節句になると、「五毒肚兜」といわれる腹かけを子どもたちに着用させ、健康を祈願するといいます。腹かけには「五毒」とされる「ヘビ、サソリ、クモ、ヤモリ、蛙」が図案化され、刺繍されています。
「五毒」がわかりやすくデザインされた腹かけをネットで見つけましたので、ご紹介しておきましょう。
なぜ、端午の節句にこのような図案の腹かけを子どもに着用させるのか、私は不思議でなりませんでした。さっそく、百度で調べてみました。すると、概略、次のような説明が出ていました。
5月になると、ヘビ、サソリをはじめとする害虫が草むらから出てきます。子どもたちもまた、陽気になった戸外で遊ぶようになります。ですから、子どもたちが害虫から危害を加えられる危険性が高くなります。そこで、中国では、子どもや親に害虫に気をつけるよう、警告するために、あのような図案の腹かけをさせる風習が生まれたというのです。
「マムシに注意!」という立て看板を見て、ふと、江戸博物館で見た腹かけを思い出し、中国の生活文化の実用性、実利性を感じました。
中国では端午の節句になると、子どもに「五毒肚兜」の腹かけを着用させる一方で、ショウブ湯に入れて、健康を祈願してきました。日本では端午の節句には武者人形を飾り、鯉のぼりを立て、ショウブ湯に入ります。中国の年中行事のうち、ショウブ湯を今に残る生活文化として取り入れてきたのです。ショウブには薬効があることが知られていたからでしょう。
ショウブが薬草として重宝されていたことは、和歌にも表現されています。
■歌に詠まれた薬猟
許曼麗氏は、「端午」という言葉の初出は、『続日本紀』の仁明天皇承和6年(839年)5月5日の項で、「是端午之節也、天皇御武徳殿、観騎射」と書かれていることを紹介しています。また、それより228年も前の推古天皇19年(611年)5月5日に、「十九年夏五月五日薬猟於菟田野、取鶏鳴時集于藤原池上以会明乃往之・・・」(『日本書紀』)の記述があるとし、端午にまつわる行事はそれ以前に中国から日本に伝わっていたと指摘しています(※ 前掲)。
端午の節句はすでに万葉の時代には中国から伝来しており、関連行事も行われていたそうです。興味深いのは、5月5日に薬猟という行事が行われ、鹿茸や薬草を採っていたということです。時代が下るにつれ、形式的なものになり、騎射や競走馬に変わっていったようですが、薬草を採ることが宮中の行事になっていたとは、私には驚きでした。
薬猟に関し、許氏は、次のような大友家持の歌を紹介しています。
「かきつはた 衣に摺り付け ますらおの きそひ狩りする 月は来にけり」
(杜若 衣に摺り付け 丈夫の競い狩りする 月は来にけり)
これは、『万葉集』に収録された歌ですが、許氏は、「杜若で染め上がった艶やかな服を着て、五月の競狩りに赴く古代人の姿が浮き出ている」と解釈しています。
堂々とした立派な男性が端午の節句には杜若で染めた服を着て、薬猟に出かける時季が来たと詠っているのですが、私はこの句の中で、なぜ、「杜若」が使われているのかが気になりました。薬猟を歌に詠むとすれば、「杜若」ではなく、薬草の「菖蒲」ではないのかと思ったからでした。
「菖蒲」には薬効があるとされ、端午の節句に薬猟をするのはそのためだといわれていました。
そこで、杜若と菖蒲の関係がどうなのか、調べてみることにしました。
■杜若か、菖蒲か、アヤメか
語源由来辞典を引いてみると、杜若は、「花汁を摺って衣に染めるための染料にしていたところから、カキツケハナ(掻付花)カキツケバタ(書付花)の説が通説になっている」と説明されています。
杜若は語源からいっても、染料としての役割が重視されていたといっていいでしょう。
念のため、Wikipediaを見ると、杜若はアヤメ科の植物で、湿地に群生すると説明されています。写真が掲載されていましたので、ご紹介しておきましょう。
これが杜若です。中心の花弁は直立し、周辺の花弁は垂れています。その組み合わせが興味深く、独特の美しさを生み出していました。
入間川の土手にも、これと似たような形状と色彩の花が群生していました。

(図をクリックすると、拡大します)
近づいてみると、遠目には似ているように見えましたが、こうして見比べてみると、直立している花弁の形状が異っているように思えます。
Wikipediaで調べてみると、これと似たような花が見つかりました。
花菖蒲と書かれています。
確かに、よく似ています。入間川の土手で咲いていたのは盛りを過ぎていますが、直立した花弁の丸みや花弁のひらひらした様子が、この花菖蒲にそっくりです。
そういえば、花菖蒲はアヤメともいわれます。
そこで、Wikipediaを見ると、次のように説明されていました。
アヤメの多くが山野の草地に自生しており、他のアヤメ属の種であるハナショウブやカキツバタのように湿地に生えることは、まれである。葉は直立し、高さ40-60cm程度。5月頃に径8cmほどの紺色の花を1-3個付ける。外花被片(前面に垂れ下がった花びら)には網目模様があるのが特徴で、本種の和名の元になる。花茎は分岐しない。北海道から九州まで分布する。
また、次のようにも説明されています。
古くは「あやめ」の名はサトイモ科のショウブ(アヤメグサ)を指した語で、現在のアヤメは「はなあやめ」と呼ばれた。アヤメ類の総称として、厳密なアヤメ以外の種別にあたる、ハナショウブやカキツバタを、アヤメと呼称する習慣が一般的に広まっている(※ Wikipediaより)
こうしてみると、アヤメ、杜若、花菖蒲はいずれも、アヤメと呼称されていることがわかります。似たような葉や花の形状から、遠目には見分けがつきにくいからでしょう。
Wikipediaのアヤメの項に、その見かけ方が表にまとめられています(※ https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%A4%E3%83%A1)。
これを見ると、大きな違いといえば、アヤメや杜若は、花の色数が少ないのに対し、花菖蒲はさまざまな色があるということです。
土手にはさまざまな色の花が咲いていましたが、おそらく花菖蒲なのでしょう。
■種類の豊富な花菖蒲
再び、道路に降りて、土手を見てみましょう。遊歩道からやや下がったところにピンク系の花が群生しています。
背後に桜の巨木が見えます。桜の木を中心に、辺り一帯の草花が集落を形成しているかのようでした。
中でも気になるのは、彩り豊かな花菖蒲です。入間川沿いの土手には、複雑な形状をしたさまざまな花菖蒲が咲いていました。いずれも背は高く、葉は先ほど見たショウブのように、刀身のような形状をしています。
印象に残ったものをいくつかご紹介していきましょう。
まず、直立しているピンクの花弁に赤紫の垂れた花弁、この色合わせが面白く、見とれてしまいました。群生しています。
近づいてみると、こんなふうです。
まるでアヤメのように斑紋があります。何度見ても、やはり、花菖蒲かアヤメか、見分けが付きません。黄色の斑紋があるせいか、この花からは豪華な印象を受けます。
白と濃い赤紫の取り合わせが素晴らしい花も群生していました。
どこかしら気高さがあります。
近づいてみると、ここにもやはり、黄色の斑紋が見えます。
背が高く、草むらにすっくと立った姿が際立っています。
見渡すと、直立した青の花弁に垂れた紫の花弁という取り合わせの花もありました。
こちらも群生しています。
近づいてみると、華麗な佇まいが印象的です。
黄色というより黄土色の斑紋が大きく、そこだけまるで金色の文様が付いているかのようでした。これもやはり成熟しており、豪華な雰囲気を漂わせています。
花菖蒲はなんと種類が豊富なのでしょう。
これまでご紹介したのは主に、二色で構成された花でした。クリーム色、一色で存在感を放っている花もありました。
直立した花弁が丸みを帯びており、遠目からはバラのように見えました。柔らかな色合いが優しさを感じさせます。手前に見える葉も背が高く、形を崩さず、刀身のようにしっかりと立っていました。
さまざまな花菖蒲が咲き乱れている土手は、まるで個性を競う展示場のようでした。どの花も背が高く、花弁の色や形状に存在感があって、惹きつけられます。花菖蒲の形状や色彩や文様は多様で、魅力に満ち溢れていました。
■5月の節句に、ショウブの薬効を思う
許氏は、「杜若は菖蒲(あやめ)と非常に類似した植物である。しかし、菖蒲と同じように辟邪(悪魔を追い払う)の効果があると思われたのか否かは定かではない」と記しています(※ 前掲)。
古来、ショウブは薬草として認知され、生活に取り入れられてきました。その後、時代が下るにつれ、美しい花を咲かせる花菖蒲に人々の関心が移っていきました。隠れた薬効よりも、見た目の美しさが価値を持つようになったからでしょう。
ショウブはサトイモ科の多年草の植物で、滅多に花を咲かせることはなく、「アヤメ」や「花菖蒲」とは明らかに異なるといわれています。特に地下茎には芳香があり、薬効があるとされています。中国ではその芳香が邪気を払い、長寿の源泉になると考えられてきたそうです。
日本に伝わってきた当初はそのようなところに価値が置かれ、薬猟といった行事にも取り入れられていたようです。ところが、そのような行事はやがて形骸化し、今ではせいぜい、子どもの日にショウブ湯に入るぐらいになってしまっています。
いつごろからか、薬草を生活に取り入れ、健康を維持していく生活習慣が廃れてしまったように思えます。縦断的な生活文化を伝える担い手がいなくなり、横断的なマスメディア主導の生活文化が中心になっていったせいでしょう。
そんな今、新型コロナウイルスに世界中が翻弄されています。
食糧の確保、防疫対策がどれほど大切なことか。様々に行動を規制され、経済的に追い詰められたいま、ようやく、縦断的に生成されてきた生活文化の価値を思い知らされているような気がします。(2020/5/12 香取淳子)