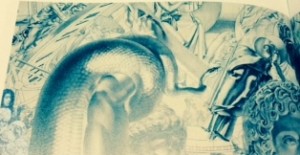■「都美セレクション新鋭美術家2015」
東京都美術館でいま、「都美セレクション新鋭美術家2015」(2015年2月19日~3月15日)が開催されています。これは、2014年5月に開催された「公募団体ベストセレクション美術2014」展から審査を経て新鋭美術家5名を選抜し、連立個展の形式で行われる展覧会です。
2015年2月21日、この展覧会に行ってきました。
こちら →http://www.tobikan.jp/exhibition/h26_newwave.html
「新鋭美術家2015」に作品が展示されたのは、瀬島匠(洋画)、高島圭史(日本画)、高松和樹(洋画)、田丸稔(彫刻)、山田彩加(版画)の5人です。2014年5月に開催された「公募団体ベストセレクション美術2014」展での審査を経て、選抜されました。まさに旬の作家たちです。
東京都美術館では、芸術活動の活性化と鑑賞体験の深化の場としての機能を果たすため、全国の公募団体と連携した展覧会を2012年から開始しています。第3回目の2014年は全国の美術公募団体の中から選抜した27団体から151人の作品163点が展示されました。
まことに贅沢な展覧会といわざるをえませんが、この中から選抜された5名の作品が「新鋭美術家2015」で展示されているのです。いま、表現の極致に挑んでいる作家たちの仕事ぶりを見ることができる最高の展覧会だといえるでしょう。実際に会場に出向いてみると、どの作品にもすぐには立ち去り難い魅力を覚えてしまいましたが、今回は瀬島匠氏と高島圭史氏の作品を取り上げることにしましょう。
■瀬島匠氏の作品
チラシの表紙を飾っているのが瀬島氏の「RUNNER2014」です。無彩色ですが、圧倒的な迫力を持つ作品です。
これが、今回の展示のきっかけとなった「公募団体ベストセレクション美術2014」で選抜された作品です。会場でこの絵を見ると、荒々しい海の前に立って、そびえ立つ黒い頑強な構造物を見ているような気になってしまいます。重く垂れ込めた曇天の下、海が荒れ始めています。黒い構造物の下、岸壁の手前で波が白い波頭を際立たせています。嵐が来る寸前の不穏な空気がひしひしと伝わってくるのです。
実際、左下の突起物はまるで本物の鉄を張り付けたように、赤く錆びていて浮き上がって見えました。そして、上空は木炭か鉛筆で描かれているのでしょうか、重くどんよりとしているのですが、重力は感じません。それに反し、波頭は強く、荒々しく、いまにも大きく波立ってこちらに襲い掛かってきそうです。重力があり、波の力がすべてこの波頭に結集されているような力が表現されているのです。
近づいてみると、白い絵の具が極端に厚く塗り込められていました。だから、波がますます荒くなっていくと感じてしまうのでしょう、人間などはるかに及ばない自然の猛威がしっかりと表現されていたのです。
■無彩色の七色
瀬島氏はほとんど無彩色で自然の力と巨大な構造物を描いていきます。海さえも無彩色で表現されていますが、そこには波頭の立つ荒々しい海が眼前に迫ってくるような迫力があります。おそらく見る側が色を感じているからでしょう。これを瀬島氏は「無彩色の七色」という表現をします。無彩色で描かれていても、眼をつぶったときに色が出てくるというのです。そして、想像する色味に共鳴できるかどうかが大切だといいます。
この絵は300×300のサイズで、油彩、透明水彩、GLボンド、錆び止め油性塗料、コールタール、木炭、鉛筆が使われています。
■RUNNER
新作も同様です。モチーフは変わりません。今回、瀬島氏は作品を4点出品していますが、タイトルはいずれも「RUNNER」です。それにそれぞれ制作年の2013、2014、2015が付けられているだけです。
これが最新作の「RUNNER 2015」です。2015年2月10日に制作が完了したそうですから、展示の9日前にようやく形になったというわけです。スケールの大きな作品を手掛けるだけあって、この一件からも瀬島氏の豪放磊落さを垣間見ることができそうです。絵の前に立っているのが作者の瀬島氏です。これを見ると、どれほどこの絵が大きいか、一目でわかると思いますが、320×600サイズの作品です。やはり、油彩、透明水彩、GLボンド、錆び止め油性塗料、コールタール、木炭、鉛筆が使われています。
1988年以降、瀬島氏は「RUNNER」というタイトルで海と構造物を描いた作品を制作し続けています。瀬戸内海育ちだと聞くとなんとなく納得してしまいます。画家だった父が造船所で働いていたせいで、幼い頃の彼の持ち物には必ずロゴを入れてくれていたそうです。だから、瀬島氏は作品にロゴが入っていないと締りがないと感じるそうです。そういえば、どの作品にも一番目立つところにさり気なく、「RUNNER」というロゴが入っています。荒々しい自然と人工の構造物をモチーフに表現活動を展開する彼はまさに美術界の新進気鋭のランナーなのです。
■高島圭史氏の作品
瀬島匠氏の隣のコーナーで展示されていたのが高島圭史氏の作品です。ふっと誘い込まれるように見入ってしまったのが、「旅に出た庭師」です。今回、展示されるきっかけとなった「公募団体ベストセレクション美術2014」で選抜された作品です。
不思議な絵でした。さまざまなものが描かれているのですが、どこから見ていいのか、迷ってしまうのです。ちょうど一人旅に出て初めての駅に降り立ったときの気分です。周囲のものすべてに神経を張り巡らせ、行くべき先を決めるための情報を収集しようとする、あのときの好奇心と不安に満ちた不思議な感覚がこの絵を見ていると覚醒されるのです。
通常は光が当たっているところが中心で、そこにヒトは眼を向けてしまいます。ところが、この絵には光が当たっていないところにもさまざまな情報が込められているので、落ち着かないのです。一方、色調は柔らかく穏やかで、見れば見るほど深い味わいがあります。多様な緑色につい引き込まれ、見入ってしまいます。この絵は和紙に岩絵の具を使って描かれました。サイズは100×100です。
■光の諸相
高島氏のこの種の絵の構造がよくわかるのが、2013年に制作された「つぎはぎの製図」でしょう。これは描かれているモチーフがそれぞれ具体的なものなので「旅に出た庭師」よりもわかりやすいです。この絵も和紙に岩絵の具を使って描かれており、サイズは170×215です。
この絵の場合も光が当たっているところにすぐ眼が向いてしまうのですが、そこに配置されているのは製図台の脚やイスのようなものであまり意味があるように思えません。手前に配置されたものも同様、雑多な文房具類です。
よく見ていくと、左奥に眼鏡をかけた人物がいることに気づきます。ようやく尋ね人を探し当てたときのように、観客はその人物を手掛かりに絵を読み解こうとします。そうすると、不思議なことに、これまで意味がないように見えていた文房具や地球儀、模型、ポットなどが途端に生き生きとその存在を主張しはじめるのです。
高島氏はカタログに寄せた文章の中で以下のように書いています。
「光やそれによって生まれる明るさは、私たちが物を見ることに欠かすことができません。同じように絵を描く時も、画面の中の形や色、表面の質感などを十分に観るためには、部屋が明るくないといけません」
そして、次のように結論づけます。
「現在の私にとって、絵と光は密接に関係しています。その関係を基にして、絵の中で光を重要な要素として扱いながら、モチーフの構成によって、光のいろいろな様相を表わすことが、私の制作上の課題です」
高島氏は、観客が絵を見ていく動線を光によって誘導しようとしているのです。改めて彼の作品を見てみると、たしかに光の当たっているところにまず目を向けてしまいます。それが意味もないようなものであれば、次に、他に意味のありそうなものを無意識のうちに探し出そうとします。
高島氏は会場で、「一番見てもらいたいところは最後か最後から2番目ぐらいに見てもらえるように設定している」といい、「主人公に辿り着くまで時間がかかるようにしたい」とも説明しています。
一枚の絵を観客がどう見ていくか、弧を描くようにその動線を考えるのだそうです。そして、文房具であれ地球儀であれ、絵に取り上げるモチーフはどんなものでも一つ一つドローイングし、それを大きな下絵に当てはめ、モチーフの配置に留意しながら、光をどう当てると良く見えるようになるか、光を当てないところをどうするかをよく考え、パズルのように組み合わせていくのだそうです。当然のことながら、絵を描く前の準備に時間がかかります。そのような地道な作業が堆積し、絵の深みになっているのではないかと思います。高島氏の作品にはどれもすぐには立ち去り難い、不思議な魅力がありました。
■色と光の諸相
今回は「新鋭美術家2015」展で見た瀬島匠氏と高島圭史氏の作品を取り上げ、気鋭の美術家たちがいま何を試行し、模索しているのかを見てきました。瀬島氏は無彩色で描いた絵から観客に色味を想像してもらうプロセスを重視していました。観客が眼を閉じたときに思い浮かべる色、それはおそらく瀬島氏の制作技法に誘導され、見えてく色なのでしょう。一口に黒といっても、瀬島氏は重く垂れ込める雲は鉛筆や木炭で描いていましたし、巨大な構造物にはコールタールを塗りつけていました。材料の違いによって質感の違いが生み出され、グラデーションが生み出され、そういうものが一体となって、観客が眼を閉じたときに、着色されているように見えてくるのではないかと思います。
一方、高島氏はモチーフの構成によって光のさまざまな様相を表現しようとしていました。モチーフをどのように配置するか、さらには、それぞれのモチーフにどのように光を当てるか、あるいは、光から遮断するか、巨大な下絵の上で模索するときがおそらく高島氏の創造的行為のもっとも重要な段階なのでしょう。高島氏が工夫して編み出したのは、もっとも見てもらいたいところに観客が辿り着くまでの距離をできるだけ長くしていくという技法でした。光に着目して個々のモチーフが配置され、全体が構造的に構成されているのですが、微妙な光の効果を最大限にするため、着色にも細心の工夫が凝らされていました。
お二人とも色と光の諸相を見つめ、表現の幅と深みを積極果敢に追求しておられました。創造者としてのその挑戦的な姿勢に心打たれてしまいます。お二人の創作活動には今後も注目していきたいと思います。(2015/2/22 香取淳子)