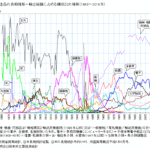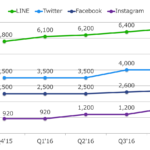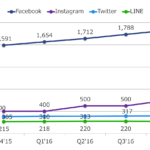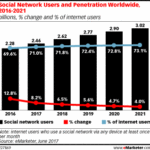■今年、やり残したこと
2017年12月30日、今年もいよいよ終わろうとしているというのに、なんだか気持ちが落ち着きません。何かやり残したことがあるような気がして仕方がないのです。ああでもないこうでもないと思いを巡らせているうちに、ようやく思い当たりました。秩父神社にお参りできなかったことが気になっていたのです。
さっそく、レッドアロー号に乗って、秩父に向かいました。晴れ上がった青空の下、冬の装いをした秩父の山並みが広がっています。車窓からは、雪の溜まった窪地も見えます。実は秩父に来るのはこれで二度目でした。前回、来たのは今月2日の夕方、秩父夜祭を見るためでした。
■夜祭の人混み
12月2日から3日にかけて、秩父夜祭が開催されました。この夜祭では花火が打ち上げられるということを知って、酔狂にも、行ってみることにしたのでした。
私は知らなかったのですが、実は、秩父夜祭は、2016年12月1日、「秩父祭の屋台行事と神楽」を含む『山・鉾・屋台行事』33件が、ユネスコ無形文化遺産に登録されています。西武秩父線は一時、廃線すら話題に上ったこともあったのですが、ユネスコ登録以来、一躍、注目を集めるようになったようです。
こちら →http://www.city.chichibu.lg.jp/6694.html
ユネスコに登録されたことを知って、私も秩父に行ってみようと思いました。このとき、私が乗ったレッドアロー号の車両では、乗客の半数は外国人でした。それも、一目で外国人とわかるヒトたちです。ユネスコに登録されてから、秩父は首都圏内の観光地として注目を浴び始めているのでしょうか、そんな気がするぐらいでした。
秩父駅に降りても大変な人混みでした。
もちろん、秩父神社に向かう道路も、ヒトで溢れかえっていました。
立錐の余地もないほどです。身動きのとれないほどの混みように、これ以上進むのは無理ではないかという思いが強くなっていきました。山車が狭い道をふさぐようにして、神社を目指して集まってきています。それに合わせるように、人々もまた、各方面から押し寄せてきます。満員電車のような混みように、ついには、秩父神社を目の前にしながら、先に進むことを断念してしまいました。
そうはいっても、人混みに逆らって、西武秩父駅に戻るのも大変でした。そこで、メイン通りから横町に入り、混雑を避けながら、戻っていくことにしたのですが、途中、珍しいお店を見ました。
どうやら、この辺り一帯はかつて絹織物で栄えたようでした。そのことを知らせる標識もあります。「買継商通り(出張所横丁)」という標識があり、簡単な説明文が刻まれています。当時は交通が不便で、近郷の織物工場が製品を置き、取り引きをするため、出張所を作っていたと書かれています。この出張所横丁は一年中、賑わっていたようです。
再び、メイン通りに戻ってみると、神社に向かう山車に出会いました。夜なので、よく見えませんが、精巧な彫り物が添えられた、とても立派な山車でした。
ようやく、西武秩父駅まで戻ってきました。一休みしようと思ったのですが、駅に隣接したフードコートもまた、大勢の人々が列を作っていました。座ることもできません。これではどうしようもないと思い、iPhoneで調べてみると、ひとつ手前の横瀬駅から歩いて行ける距離に、武甲温泉があることがわかりました。
■武甲温泉
一休みするため、武甲温泉に行くことにしました。秩父で花火が打ち上げられる頃になるまで、温泉に入っていようと思ったのです。横瀬駅を降りて、武甲温泉に向かう道は人通りも少なく、清冽な空気に包まれていました。
暗闇の中に満月が静かな光を投げかけています。幻想的な雰囲気の中、下っていくと、暗闇の中、ぼおっと明るく照らされたところがあり、それが武甲温泉でした。
温泉には地元の人が数人いるぐらいでした。露天風呂には人の気配もありません。ゆっくりと身を沈め、夜空を眺めると、左手に満月、右手に花火が見えました。秩父で打ち上げられた花火がここでも見られたのです。秩父夜祭は豪快な花火で有名です。それが空を恰好の舞台に、次々と打ち上げられ、静かな闇の中に華やかさを作りだしていました。
横瀬駅で秩父行きの電車を待っていると、夜空に大きく、花火が打ち上げられているのが見えました。暗闇の中、ゆっくりフェードインしてきたかと思うと、たちまちフェードアウトしてしまう花火を見ていると、いつになく、心が大きく揺さぶられました。冬の夜空に華麗に花開いた花火に、「つかの間の美」あるいは、「滅びの美」を感じてしまったからでした。
そんなわけで、秩父夜祭を十分に堪能することはできませんでしたし、肝心の秩父神社にもお参りできませんでした。それが晦日の朝、気になって落ち着かない気分になっていた原因でした。
さて、秩父の夜祭については、さまざまな映像がネット上にアップされているので、ご紹介しておきましょう。
こちら →https://navi.city.chichibu.lg.jp/p_festival/1030/
■晦日の秩父
晦日、レッドアロー号に乗って、再び、秩父を訪れました。夜祭の際、お参りすることができなかった秩父神社に行くためでした。乗った車両は今回、日本人ばかりでしたし、空席もあります。西武秩父駅に降りても、ヒトは少なく、ちょっと待つと、行き交うヒトが途絶える瞬間もありました。
おそらく、これが平常の姿なのでしょう。駅に隣接するみやげ物店やフードコートも混みあっていません。
秩父神社もまた、訪れているヒトの数が適度で、落ち着きがありました。
境内に入ると、二本の垂れ幕が翻っていました。秩父神社は2015年に鎮座2100年を迎え、2016年にはユネスコ世界遺産に登録されるといったお祝い事が続きました。それを記念するための垂れ幕がいまだに掛けられているのです。お祝い事が重なったことへの喜びがひしひしと伝わってきます。
さて、秩父神社は「北辰の梟」が有名なのだそうです。
本殿北側に彫刻された梟は「北辰の梟」と名付けられており、身体は正面を向き、顔は正反対を向いて描かれているのが特徴なのだそうです。写真を撮ってみましたが、肝心の梟が小さくてよく見えません。木の葉や鳥にまぎれるように小さく、中央に彫られているのが梟です。
この「北辰の梟」にちなんで、以下のような説明がされているサイトを見つけました。興味深いので、ご紹介しておきましょう。毎年、受験生が多数、お参りに来るそうです。
こちら →https://www.hokushin-t.jp/hukurou.html
そもそも、秩父神社は、八意思兼命の十世の子孫である知知父彦命が創建したといわれています。
こちら →http://www.chichibu-jinja.or.jp/saijin/index.htm
八意思兼命は政治、学問、工業、海運の祖神です。受験生が数多くお参りにくるものも、ひょっとしたら、「北辰の梟」のせいばかりではないのかもしれません。秩父神社の祖神が、学問を奨励し、工業あるいは産業を振興し、交通を切り拓いていくことを旨としているなら、積極果敢な精神こそ、その真髄です。受験生ばかりでなく、起業者、創造者もまた、お参りに来てもいいでしょう。
秩父神社を出ると、すぐ前の店の屋根の看板に「和同開珎」が掲げられていました。ここはかつて純度の高い銅が生産されていた土地のようです。
■再訪した秩父で見たもの
今回は昼間、訪れたせいで、前回は気づかなかった街の古い建物に印象付けられました。今では見かけることもない煙草店がありました。角が丸くかたどられ、大きな紋章が目立つ3階建ての建物です。
少し進んでみると、煙草店の表示が見えます。
医院もまた、今では滅多に見ることもできない風雅な建物でした。
そうかと思えば、2階に縁台のついた、時代を感じさせる建物もあります。
こちらは印刷店でした。
石畳の街の両側に経つ建物から、往時の街の営みが感じられます。山深い秩父の街の繁栄が建物を通して、今に蘇ってきたようです。
秩父神社を左に曲がって歩いて行くと、これまた時代を感じさせる建物がありました。
こちらは酒造店でした。中に入ると、特産のお酒が並んでいました。ボトルにしてもラベルにしても手作り感が面白く、赤ワインと梅酒、酒粕を買いました。
伝統を生かしながら、21世紀の現代社会に訴求できるものは何か、この秩父の街で見たような気がします。郷愁を感じさせるとともに、時代を超えて静かに輝く身体性とでもいえるものが、街の随所に見受けられたのです。
西武秩父に隣接して、土産物店やフードコート、そればかりではなく、温泉も設置されていました。
この温泉は泉質もよく、さまざまな湯を楽しむことができるよう配慮されていました。湯に浸かっていると、次第に気持ちもほぐれてきます。便利で機能的で、都会生活者にはぴったりの温泉でした。
晦日の朝、落ち着かない気分を払拭するため、秩父神社にお参りをしてきました。ついでに、秩父の街を散策し、温泉に入って、ようやく気分がおさまり、2017年の終わりを迎えることができました。来年も、いい年でありますように。(2017/12/31 香取淳子)