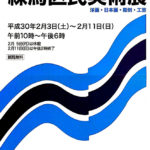■「練馬アニメカーニバル2018」の開催
2018年10月20日から21日の11:00から18:00、練馬駅北口で「練馬アニメカーニバル2018」が開催されました。土曜日、立ち寄ってみたのですが、意外に人数が少なく、驚きました。アニメイベントの開催地ならどこも若いヒトが溢れかえっているのかと思っていたのですが、どうやらそうでもなく、会場では若者より親子連れの方が目立っていました。若者向けアニメキャラクターを使った看板がちょっと場違いに思えたほどでした。
とはいえ、会場でもらったパンフレットを見ると、とても充実した内容で、アニメや漫画を端的に知りたいと思う者にとっては恰好のコンテンツが用意されていました。とくに、「練馬にいた!アニメの巨人たち LIVE高畑勲完読編」や「“アニメはネットで見る“のが常識に?! ネット配信はアニメビジネスに変革をもたらしたか」などのトークショーやシンポジウムが、私には興味深く思えました。
こちら →https://animation-nerima.jp/event/carnival/
アニメそのものはもちろんのこと、よしもとアニメ芸人のライブ、イベント関連のアニメ作品の上映、アニメ制作体験のワークショップなども用意されていました。練馬駅は大江戸線、西武池袋線、有楽町線を利用できますから、アクセスになんら問題はありません。それなのになぜ、ヒトが集まっていないのか、私には不思議でなりませんでした。
なぜ私がそんなふうに思ったかというと、2週間ほど前に徳島で見かけたアニメイベントとつい、比較してしまったからでした。
■「マチ★アソビvol.21」
実は、徳島国際美術館に出かける予定で、10月6日から7日にかけて徳島に宿泊しました。その1か月ほど前に旅程を決めて、ホテルを予約しようとしたのですが、どういうわけか、希望したホテルは予約できませんでした。予約で満杯だというのです。ところが、徳島に着いてみると、街はいたって静かでほとんど人通りはありません。なぜ、どのホテルも予約客でいっぱいだったのか、理解できませんでした
10月7日午前中、眉山ロープウェイに乗って山頂まで登ってみようと思い、阿波踊り会館に行きました。そこでようやく、ホテルの予約が取れなかった理由がわかりました。山頂でアニメイベントがあるというのです。山頂までのエレベーター前には若者が大勢並び、周辺の部屋や階段にまで溢れかえっていました。12時から眉山山頂で「FateHF×AbemaTVスペシャル」が開催されるので、全国各地からやってきた若者たちが列を作っていたのでした。
こちら →https://news.nifty.com/article/entame/showbizd/12246-105812/
山頂のステージでは、コスプレあり、キャラクターやアイドルの登場ありといった具合に、若者たちが今を楽しむ空間が創り出されていたのです。山頂ではこのようなイベントが行われ、街中では各所でアニメ上映会が行われていました。
こちら →http://www.machiasobi.com/passrull.html
徳島では町おこしの一環として、毎年この時期にアニメイベントが開催されており、大勢の若者たちを全国から集めるパワーを発揮していたのです。
こちら →http://www.machiasobi.com/
「マチ★アソビvol.21」の今年の開催期間は、2018年9月から10月8日まででした。私が大塚国際美術館に行く予定でたまたま徳島を訪れたのが、このアニメイベントの開催日だったというわけでした。おかげで図らずも、徳島でのアニメイベントの集客状況を見ることができました。
徳島と比較すると、今回の練馬アニメイベントはあまりにも参加者数が少なく、そして活気がなく、驚いてしまったのです。アニメ発祥の地といわれ、アニメ会社も多数ある練馬で開催されたアニメイベントなのになぜ、参加者が少なかったのか。しかも、若者が圧倒的に少なかったのか。私には理解できませんでした。
先ほどご紹介したように、練馬アニメカーニバルのプログラムはとてもよく出来ていました。アニメを俯瞰し、把握しようとすればこちらのイベントの方がはるかに充実しており、参考になると私は思いました。とくに素晴らしかったのが、氷川竜介氏と原口正宏氏のトークショーでした。
■氷川竜介氏×原口正宏氏、高畑勲監督を語る
これは、2018年4月5日に82歳で亡くなった高畑勲監督について、明治大学特任教授の氷川竜介氏とアニメ史研究家の原口正宏氏が語り合うというコーナーです。私は途中から参加したのですが、ジョークを交えて両者の対話を聞きながら、専門家ならではの蘊蓄を楽しむことができました。その一端をご紹介しましょう。
司会者から、高畑勲監督の作品で印象に残るのはと問われ、氷川氏は「じゃりん子チエ」(1981年公開)を挙げ、原口氏は「パンダコパンダ」(1972年公開)を挙げました。
◆じゃりん子チエ
こちら →http://www.futabasha.com/chie/
「じゃりん子チエ」を挙げた氷川氏は、高畑監督は原作に忠実にアニメ作品を制作していたといいます。原作をいったんバラバラに解体して本質を掴んでから再構成するかたこそ、面白くてやがて悲しいトーンができあがるというのです。たとえば、人間にとって本当の孤独とは何かという哲学的なテーマも、高畑監督の手にかかれば、穏やかなユーモアの中で味わい深く表現されていくというわけです。
◆パンダコパンダ
こちら →http://www.pandakopanda.jp/
一方、「パンダコパンダ」を挙げた原口氏は、この作品の脚本は宮崎駿が手掛けたが、演出は高畑監督が担当しており、高畑監督の本質がこの作品にまぎれもなく現れているといいます。すなわち、日常生活を丁寧に切り取って描き、それを物語の展開の過程に挟み込んでいくという手法です。この手法を採るからこそ、ペシミスティックなものを土台にしても、観客と共有できるものが生み出されると説明します。
高畑勲監督について、両者は異口同音にそのペシミスティックな姿勢を特徴として挙げています。調べてみると、確かにその要素はありました。たとえば、高畑監督は「母をたずねて三千里」についてのインタビューに答え、以下のように述べています。
「ハイジの次に作った「母をたずねて三千里」の主人公マルコは、自分の無力さにいらだつ少年です。つらい状況に遭うと、「僕は呪われているんだ!」と叫ぶ。視聴者には「かわいげのない生意気な子」と映るだろうけれど、それでいい。一緒に作った宮さん(宮崎駿監督)は、主人公が旅の先々でトラブルを解決し、一宿一飯の恩義を果たす股旅ものをやりたかったのだろうが、僕は惨めな話がよかった。靴が壊れ、生爪がはがれるといった、目を背けたくなるエピソードもあえて入れた」
(「朝日新聞」2013年12月9日付夕刊)
この記事を読むと、高畑監督が単なるストーリー展開の面白さだけではなく、登場人物をしっかりと支えるリアリティを求めていたことがわかります。実際、辛いエピソードがストーリーの中に組み込まれると、人物像に陰影が生み出され、笑いに深みが加わります。だからこそ、氷川氏が指摘するように、「面白くてやがて悲しい」気持ちになってしまうのでしょう。日常生活の一端に辛い要素を付加する高畑監督の手法こそが、大人の鑑賞にも耐えられるアニメ作品に仕立て上げているのかもしれません。
■高畑監督の功績
高畑監督の手掛ける作品は次々とヒットしました。
もちろん、それらの作品が制作されたのがシリアスなものを求める時代であったことも影響しているでしょう。作品が世に受け入れられるには時代の風潮が深く関わってきます。「パンダコパンダ」は1972年、「アルプスの少女ハイジ」は1974年、「母をたずねて三千里」は1976年、いずれも70年代に放送開始されています。人々がまだシリアスなものを求めていた時代でした。
原口氏は、高畑勲監督は時代の風潮はどうであれ、子供に何を提供するかという観点からアニメ作品を制作すべきだと思っていたといいます。子供に今、何が不足しているのか。子供に向けて何を作るか、提供するか。そして、何よりもまず、教育、道徳、説教臭さを離れ、子供自体が生き生きと心を解放できるような作品を創るべきだと考えていたというのです。
見るだけで子供が幸せになれる作品、長い年月を経ても子供たちに親しまれる作品、高畑監督はそのような作品を創ろうとしていたと原口氏はいいます。
原口氏は、東映時代にTVアニメを一通り経験し、さまざまに試行錯誤した結果、高畑監督は独自の手法を見出したといいます。つまり、描こうとするものを客観的に捉えるとともに、プロセスを省略せずに見せる、それも、愚直なまでに丸ごと見せるという手法です。
丸ごと見せることによって、観客をエピソードの細部に立ち会わせ、時間と経験を共有させることができます。細部を省略せず、丁寧に描くことによって、物語に時間の厚みを創り出し、観客が共感できる素地を作っていくのです。このような高畑監督の演出手法が、日本アニメに奥行きと風格を与えたといってもいいでしょう。高畑監督が演出した「アルプスの少女ハイジ」はその後の日本アニメに大きな影響を与えたといわれています。
一方、氷川氏は、高畑監督は日本アニメの巨人だといいます。たとえば、空気は観客にどうやって実感させることができるか、見えないものをあるように見せるにはどうすればいいか。極めて難しい課題です。感情も同様、外から見えないものは表現するのは非常に難しい。それを高畑監督はしっかりと可視化し、実感できるように表現しているといいます。
空気のある世界はヒトやものが生きている世界でもあります。高畑監督はシーン毎に細部を丁寧に積み重ねていくことによって、空気を感じさせ、見えない領域を観客に感じさせることができます。そして、日常性を画面に入れ込み、リアリズムに徹することで、登場人物の存在に説得力を持たせているのです。
■アニメイベントの集客力と訴求力
10月7日に徳島のアニメイベント、そして、10月20日に練馬のアニメイベントに遭遇しました。いずれも通りすがりに偶然、見かけました。驚いたのは集客力の違いでした。徳島のアニメイベントは町おこしの一環として開催されており、会場には全国各地から若者たちが馳せ参じていました。閑散とした街並みでは、若者の姿だけが目立つ不思議な光景を何度も目にしました。
イベントが行われる眉山山頂行のエレベーターに乗ろうとしても、混雑して乗り切れず、手持無沙汰だった私は物産コーナーに向かって、徳島の特産品を買いました。ところが、そこで見かけたのはもっぱら親子連れか高齢者で、若者は見かけませんでした。ひょっとしたら、混み合って身動きのできないほど多くの若者が集っていても、地元の物産にはあまりお金を落としていなかったのかもしれません。
一方、練馬のアニメイベントには親子連れがもっぱらで、若者の姿はあまりなく、意外なほどでした。プログラムはとてもよく出来ていたのに盛り上がりに欠けていたのは、参加者数が少なかったからでしょう。そうはいっても、参加したトークショーは内容が充実しており、聴き応えがありました・・・、と書いてきて、ふと気づきました。
練馬のアニメイベントで参加者が予想外に少なかったのは、若者に向けた参加型プログラムがなかったからではないかと思ったのです。
アニメ制作ワークショップのような参加型のプログラムも用意されていましたが、ここでは親子連れが目立っていました。混んでいると思っていた上映会もグッズ販売も参加者が少なく、活気がありませんでした。イベントには付き物のお祭りの要素が欠けていたのです。それはおそらく、徳島のアニメイベントで見かけたような若者を対象にした参加型プログラムが用意されていなかったからでしょう。参加者の気持ちを弾ませる賑わいを生み出せなかったことが、集客力の弱さに結び付いたのではないかと思いました。
もちろん、開催場所の状況も影響しているでしょう。徳島では眉山の頂上でイベントが開催されていました。大音量をあげ、参加者が打ち興じられる異空間が用意されていたのです。一方の練馬では開催場所が駅前広場とビル内だったので、大音量をあげることはできず、大人数も収容できませんでした。アニメイベントを通して日常空間から脱することができなかったのです。
通りすがりに立ち寄ったとはいえ、私にとっては練馬イベントでのトークショー魅力的でした。日本アニメの作品や監督に詳しく、深い分析ができるヒトが登壇者として招待されていたのです。聞き始めるとたちまち引き込まれ、気が付くと、夢中でメモを取っていました。練馬のアニメイベントは集客力こそ弱かったですが、訴求力は強く、参加者の心に残るものは大きかったと思います。(2018/10/28 香取淳子)