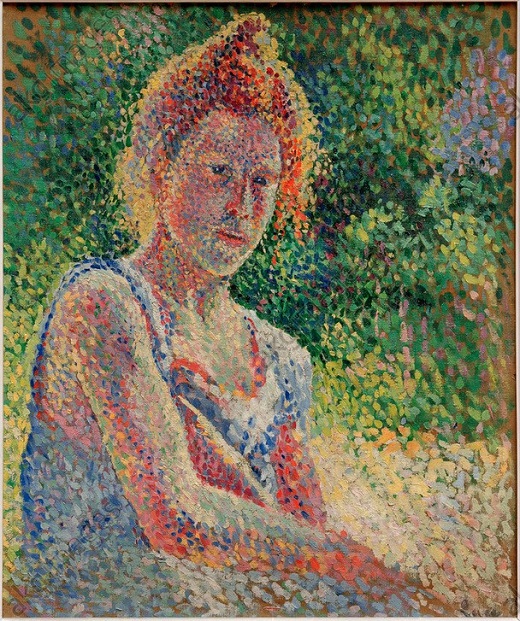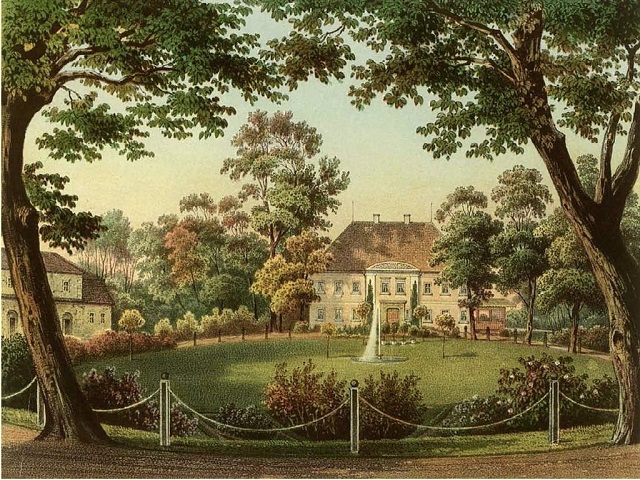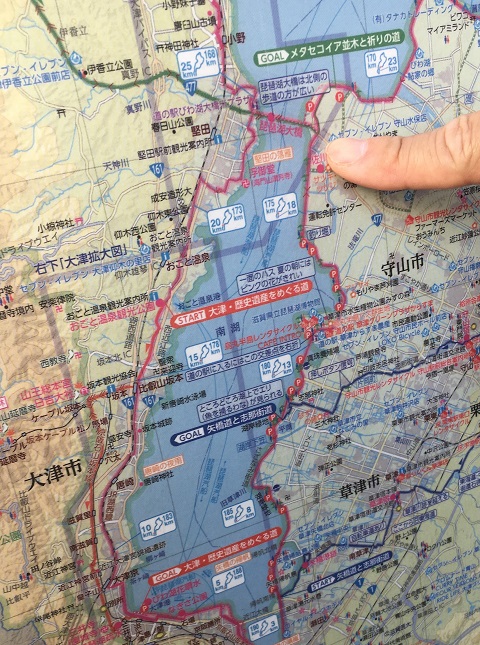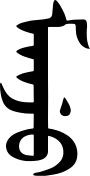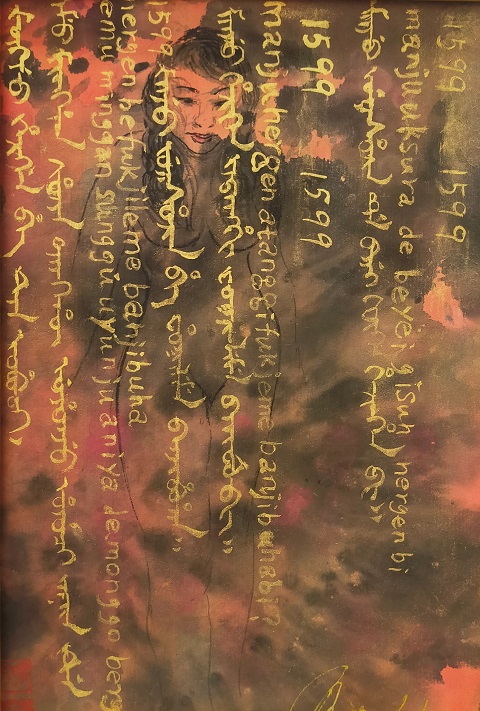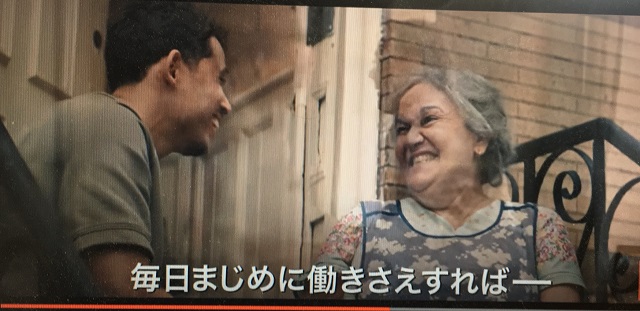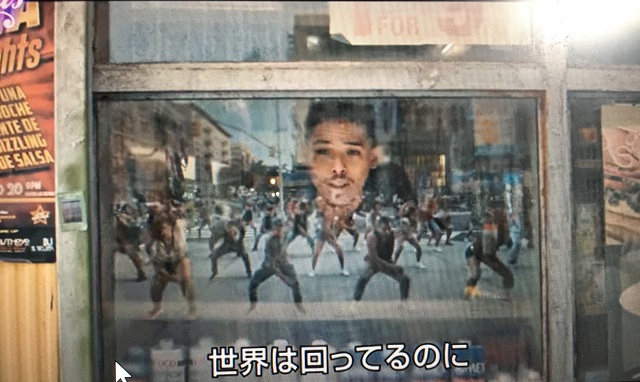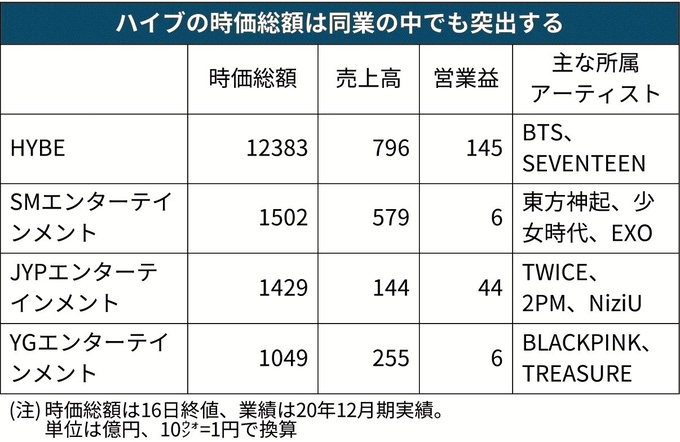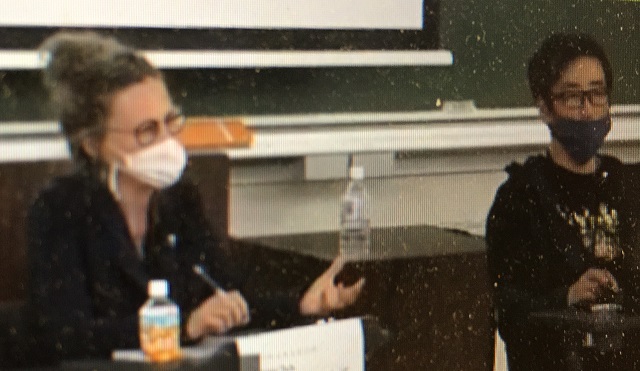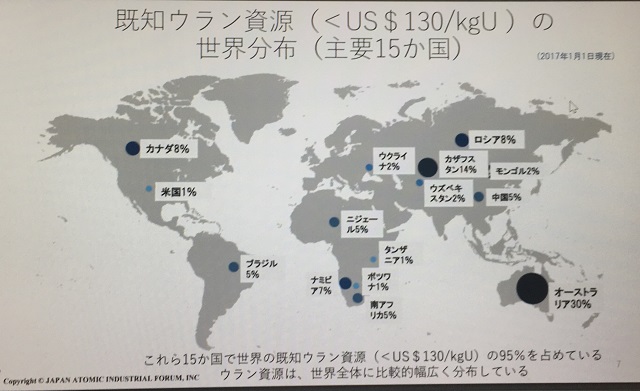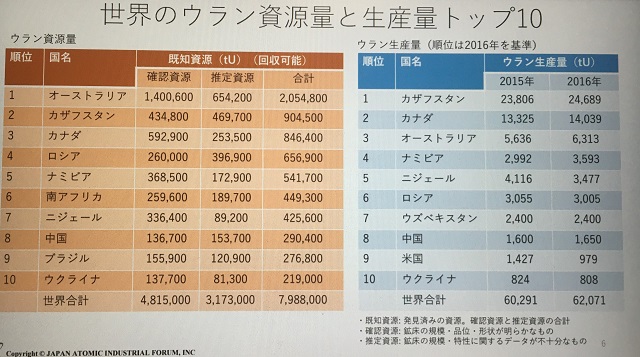■カロリュス・デュランの下で学ぶ
リュスは木版画職人としての修業を終えると、木版工房で働きながら、画塾に通ったり、著名な画家のアトリエに出入りしたりし、独自に絵画を学んでいました。
1876年になると、肖像画家カロリュス・デュラン(Carolus-Duran, 1837-1917)の下で学び始めます。当時、デュランは、パリの上流階級の人々を数多く描き、肖像画家として人気がありました。すでに数々の賞を受賞し、画家としても教育者としても評価されていました。1904年にはレジオンドヌール勲章を受勲するほどの大御所でした。
そのデュランに師事し、リュスは油彩画の手ほどきを受けるようになります。きっかけとなったのはアカデミー・シュイスでした。そこで教えていたデュランと出会い、無給の学生として彼のアトリエに受け入れられることになったのです。(※ https://ago.ca/agoinsider/unconventional-impressionist)
デュランは若い頃、スペインに旅し、ベラスケス(Diego Rodríguez de Silva y Velázquez, 1599-1660)の作品から強く影響を受けたといわれています。
■ベラスケスの肖像画
ベラスケスは17世紀のスペインを代表する画家です。国王フェリペ4世に気に入られ、宮廷画家として長年、国王や王女、宮廷の人々の肖像画を描いてきました。彼が、王女マルガリータ・テレーサを描いた一連の作品の一つに、《白い服の王女マルガリータ・テレーサの肖像(La infanta Margarita)》(1656年)があります。

(油彩、カンヴァス、105×88㎝、1656年、ウィーン美術史美術館)
スペイン国王フェリペ4世の長女、マルガリータ・テレーサが5歳の時の肖像画です。ぷっと膨らんだ頬、緊張した口元、白く透き通るような肌、なんと愛くるしいのでしょう。やや不安げで、可憐な表情が生き生きと描き出されています。綺麗に梳かしつけられた金髪もまだ薄く、柔らかく、この時、マルガリータがわずか5歳でしかないことを思い起こさせてくれます。
ところが、身に纏っているドレスには、銀糸で模様が刺繍された光沢のある布地が使われています。そして、首回り、襟、胸元、袖などには、金と黒の刺繍が施されており、人目を引きます。さらには、腰幅を広く見せるため、異様なほど大きなペチコーまで着用しています。
まだ年端もいかない幼児なのに、成人女性と同じようなスタイルの衣装を着用しているのです。
胸やラグランスリーブの端、袖口にはオレンジ色の花飾りが付けられています。おそらく、可愛らしさを演出するためでしょう。子供らしさを感じさせる要素はそれだけですが、この豪華な服を着せられたマルガリータは健気にも、姿勢正しくポーズを取っています。
ひょっとしたら彼女はこの窮屈さを、王室に生まれた者の定めとして、我慢しなければならないものの一つとして、幼いながらも、受け入れていたのでしょうか。
いま見れば、この衣装があまりにも豪華で、堅苦しく、儀式的なので、違和感を覚えてしまいますが、おそらく、これが当時のスペイン宮廷の様式だったのでしょう。
王家の肖像画には、富みと権力を所有する者の証として、権威と威厳が備わっていなければなりませんでした。たとえ幼いマルガリータが対象だとしても、ベラスケスはそのための設定を避けることはできなかったのでしょう。
ベラスケスが手掛けた肖像画には、権威、威厳、豪華、華麗、上品といった要素がふんだんに盛り込まれていました。写真技術がまだ発明されていなかった時代、肖像画こそが個人や家族のステイタスシンボルとして機能していたからでした。
実際、肖像画は個人を確認する証明書としても、個人や家族の歴史を記録するアーカイブとしても有効でした。
興味深いエピソードがあります。
マルガリータが、神聖ローマ皇帝レオポルト1世と結婚する前のことです。それ以前から両者の婚姻は既定路線だったのですが、マルガリータが適齢期になると、スペイン宮廷はベラスケスに描かせた子供の頃の肖像画をいくつか、レオポルト1世に送ったそうです。遠路はるばる会いに行く危険を避けて、肖像画で代用したのです。(※ https://www.habsburger.net/en/chapter/leopold-i-marriage-and-family)
このエピソードからは、肖像画が、本人の確認あるいは、本人のアーカイブも兼ねて機能していたことがわかります。それだけに、肖像画に写実性は不可欠でした。
ベラスケスはそのための油絵技法を長年にわたって錬磨し続けてきたのです。それを後世のマネやデュランが高く評価し、影響されました。
それでは、ベラスケスの影響を受けたとされるデュランが、どのような肖像画を描いていたのか、見ていくことにしましょう。
■デュランの肖像画
肖像画の中でも、「母と子」は重要な画題の一つでした。家族愛、家族の絆の象徴であり、上流階級にとっては、一族の繁栄を示すもの、あるいは、富の継承を示唆するものでもあったからです。デュランも、母と子の肖像画を描いています。
たとえば、《母と子(フェドー夫人と子供たち)》(Mother and Children (Madame Feydeau and Her Children), という作品があります。
●《母と子(フェドー夫人と子供たち)》(1897年)
この作品では、フェドー夫人とその子供たちが描かれています。当時、人気のあった劇作家、ジョルジュ・フェドー(Georges Feydeau, 1862-1921)の妻とその子供たちがモデルです。

(油彩、カンヴァス、190.5×127.8㎝、1897年、国立西洋美術館)
二人の子供を抱きかかえたフェドー夫人が静かにこちらを見つめています。豪華な黒い衣装とネックレス、大きく開いた胸元に飾られた赤い花が彼女を引き立てています。華やかで上品、いかにも上流階級の女性といった面持ちです。
膝に寄りかかって母を見上げている男の子は、白い襟飾りのついた黒の正装をしています。その横顔と白い襟以外は、母の黒いドレスに溶け込み、一体化しています。男の子の肩にそっと置かれた母の手に、慈愛が感じられます。
一方、女の子は光沢のあるベージュ色の衣装を身につけています。襟元には同系色の凝った刺繍が施されており、なんとも豪華なドレスです。これも正装なのでしょう。左手に大きな淡い橙色のバラを持ち、右手を母の膝に置いて、寄りかかるように立っています。母の左手と女の子の右手が触れ合っており、二人の愛情が通い合っているのが感じられます。
もっとも、女の子の表情はぎこちなく、やや不自然に見えます。この絵のためにポーズを取っているからでしょうか、緊張している様子が感じられます。この作品が日常的な光景を捉えたものではなく、輝かしい瞬間を記録に残そうとする意図の下に、描かれているからでしょう。
確かに、この作品は家族の肖像画としては完璧でした。
画面からはまず、家族の絆、愛が感じられます。そして、上品、安定、厳粛さのようなものも感じられます。依頼者が肖像画に求めたであろうものが、過不足なく盛り込まれているのです。
母と子供たちの配置、色彩バランスなどを考え、じっくりと時間をかけて構想されたのでしょう。だからこそ、画家が企図した通りのメッセージが画面からは伝わってくるのです。この作品を見ていると、デュランが肖像画家として人気を博していた理由がわかるような気がします。
それでは、構図と色彩の面から、この作品を見ていくことにしましょう。
●人物の配置と構図
まず、母と子供たちとの関係を、所作の面からみていきましょう。
男の子は母の膝に身を置き、上目遣いに見上げています。母の手は男の子の背に置かれており、互いの信頼と愛が感じられます。一方、女の子は母を見ているわけではありませんが、身体をぴったりと母に寄せ、傍に立っています。手の甲を母の手に触れ、緊張感をやわらげている様子が見て取れます。
所作の面から、母と子供たちとの関係を見ると、男の子も女の子も母に身を寄せ、安心感を得ている様子です。一方、母は、左右の手を使って、安心させるように、子供たちの身体に触れています。保護し、保護される関係が母と子供たちの所作から描き出されています。
次に、配置の面から母と子の関係を見てみましょう。
この作品を見て、まず目に入ってくるのは、やや首を傾げた母の顔です。その母を頂点に、寄りかかる男の子の姿勢が、母の身体の傾きに呼応しています。母の頭と男の子の頭を繋ぐラインは、ちょうど、画面の右上から左下に走る対角線と重なり、母を頂点とする三角形の斜辺になっています。
一方、女の子はすっくと立ち、頭を母の方にやや傾けています。その姿勢は、背筋を伸ばしながらも、頭だけを右に傾けた母の姿勢に呼応しています。こうして母と女の子は近づき、二人の頭を繋ぐラインは、肩まで伸びる髪の毛、膨らみのあるパフスリーブへと続き、これもまた、母を頂点とする三角形の斜辺になっています。
これら二つの斜辺をつなぐと、三角形になります。わかりやすく赤線で図示すると、次のようになります。

こうしてみると、改めて、この3人の頭が母を頂点とする三角形になるよう配置されていることがわかります。しかも、ほぼ正三角形です。もっとも安定感のある構図が導入されているのです。
さらに、母の頭を頂点に、男の子の頭が底辺の左底角、女の子の頭が右斜辺の真ん中に位置づけられています。女の子の方が年上で、男の子が年下であるという序列まで示されているのです。
そして、母と子供たちは、互いに顔を近づけるような姿勢で描かれており、母と子の親密さが表現されています。それぞれの顔の傾き、あるいは視線の方向から、相互の愛情と信頼が表されていることがわかります。
それでは、色彩の面から、何を読み取ることができるのでしょうか。
●色彩
床と背景を覆っているのは、焦げ茶色をベースとしたベルベットのような風合いの生地に見えます。画面の半分以上がこの色彩とテクスチャで占められているので、上品で、しかも、落ち着いた印象があります。
さらに、母と男の子は黒の正装、女の子は光沢のある、やや明るいベージュ色の正装をしています。背景色を除くと、黒の面積が大きく、それ以外は光沢のあるベージュ色です。そのせいか、画面全体に厳粛さと威厳、上品さと落ち着きが醸し出されています。
ベージュ色のドレスに目を向けると、女の子が手にした淡い橙色のバラの花が、不自然なほど下方に描かれているのが気になります。しかも、この花が大きすぎるのです。否応なく、観客の目は下方に誘導されます。
そうすると、バラの花弁がいくつか、その下の床に散っているのに気づきます。こうして、さり気なく豪華さが演出され、しかも、画面にちょっとした動きが生み出されているのです。
そこから見上げた位置に赤いバラが描かれ、大きく開いた母の胸元を飾っています。女の子のドレスに置かれたバラからはやや斜めのライン上にあります。二つの花はそれぞれの衣装を引き立て、彼女たちの存在感を高めています。
さらに、これら二つの花を結んだラインは、母と娘の頭を結んだラインと並行しています。それぞれのラインを水色で図示すると、次のようになります。

こうしてみると、二つの花を結ぶラインは、母と娘の髪の毛を結ぶラインとほぼ2倍の長さで、平行に描かれていることがわかります。しかも、その起点はいずれも、母と息子の頭を結ぶ左上から右下への対角線上にあります。
二つのラインは、母と娘の親密さを示すとともに、二人の関係を支える構造的なラインとしても機能しているのです。
こうしてみてくると、いずれのラインも母と子供たちを巡る、保護―非保護の関係が示されており、強い家族の絆が表現されていることがわかります。
興味深いのは、男の子が黒い服を着て、母のドレスの中に溶け込んでいるのに対し、女の子はベージュ色のドレスを着て、黒い服の母とは分離した存在であることが示されていることです。
この色遣いには、母と男の子の関係、母と女の子の関係が示されているように見えます。年少で、いまだに母に依存している男の子に対し、年長で、母から自立しはじめている時期の女の子という、依存関係の強弱が示されているようにみえます。
もっとも、母と娘が身につけている花に着目すれば、別の側面が見えてきます。
その母の胸元を飾っている赤い花が情熱を示すとすれば、女の子が手にしたごく淡い橙色の花は穏やかな従順さを示しています。つまり、デュランは、たとえ色彩で分離されていても、母は情熱を持って娘を庇護し、娘は従順に母に従うという母と娘の関係を、構図と色彩から表現していると考えられるのです。
こうしてみてくると、デュランが、構図の面からも色彩の面からも明確なコンセプトの下、この母と子供たちの関係を表現していたことがわかります。
デュランは、厳粛さ、上品さ、豊かさ、華麗さなどの要素を組み込んだ上で、家族の愛、家族の絆を画面に描き出していたのです。依頼者はおそらく、この作品の出来栄えに納得し、感謝したに違いありません。
この作品を見ていると、肖像画家としてのデュランの人気が定着していった理由がよくわかります。
宮廷画家ベラスケスからデュランが得たものの一つは、写実性を踏まえた上で、依頼者が求める理念、あるいは概念を画面に組み込むことでした。
■デュランの肖像画に見るベラスケスの影響
写実的で、しかも、筆触の妙を効かせたベラスケスの油彩画技法は、当時、マネ(Édouard Manet, 1832-1883)から、高く評価されていました。近代美術の父といわれるマネが、「画家の中の画家」だと絶賛していたのです。
ベラスケスを高く評価し、その影響を受けていたのは、マネばかりではありませんでした。デュランもまた、ベラスケスの影響を強く受け、写実的で古典的な肖像画を数多く描いてきました。
とくに、上流階級の人々を描くことでは定評がありました。リュスが育った環境では、決して出会うことのない人々でした。彼らは当然、庶民とは服装も違えば、所作も異なります。
デュランが参考にしたのは、ベラスケスの肖像画でした。宮廷画家として活躍したベラスケスの諸作品から、服装や調度品、所作などを参考にしたのです。
たとえば、《ウィリアム・アスター夫人(Mrs. William Astor)》(油彩、カンヴァス、212.1×107.3㎝、メトロポリタン美術館)という作品があります。デュランが1890年に描いたもので、この時の衣装とポーズは17世紀の肖像画家ベラスケスを参考にしたと記されています。(※ https://www.metmuseum.org/art/collection/search/435849)
実際、デュランの肖像画をいくつか見てみましたが、モデルはいずれも正装をし、ポーズを決めた姿勢で描かれていました。おそらく、宮廷画家ベラスケスを参考に肖像画を描いていたからでしょう。どの画面からも、華麗で厳か、富みと繁栄を感じさせる要素が強く、醸し出されていました。
デュランが描く肖像画を見ていると、肖像画が社会的ステイタスを示す価値を持っていた時代の名残が感じられます。
デュランが肖像画家として人気を博するようになったのは1868年以降です。先ほどのメトロポリタン美術館の説明では、1890年には肖像画家として絶頂期を極めていたとされています。その30年弱の間、フランスは大きな社会変動に見舞われています。
とくに、1871年3月26日から5月28日にかけてのパリ・コミューンは画家たちにとっても大きな出来事でした。ところが、そのパリ・コミューンを経てもなお、上流階級にとっては肖像画が必要だったのです。
さて、人気のある肖像画家として活躍していた1876年、デュランは一風変わった肖像画を描いています。自分の母親を描いた作品です。
デュランの肖像画をいくつも見てきましたが、この肖像画は異質でした。
■デュラン、母親の肖像画を描く
肖像画家デュランにしては珍しく、モデルを見たまま、ありのままに描いています。
●《母の肖像》(Portrait de ma mère)1876年
1876年、ちょうどリュスがデュランのアトリエで学び始めた年、デュランは母親を描いています。作品タイトルは、《母の肖像》(Portrait de ma mère)です。

(油彩、カンヴァス、サイズ不詳、1876年、オルセー美術館がサントクロワ美術館に寄託)
暗い背景の中から顔面だけが浮き出るように、高齢女性が描かれています。静かで穏やかに観客を見つめています。その透徹した視線には高邁な精神が感じられます。
悟りの境地に達しているからでしょうか。何事にも動じることなく、凛とした姿勢で、老いと孤独に、静かに向き合う高齢女性の姿が心に残ります。
さっと描いたように見える中に、端的に対象の本質が捉えられていました。冷静な観察力が強く感じられる作品です。
おそらく、コンセプトを練り上げることもなく、時間もかけずに制作したのでしょう。カンヴァスに向かったデュランが、老いた母親を美化しようとせず、ありのままに描いていたことがわかります。
ありのままとはいっても、髪の毛や帽子、首回りで結ばれたリボンなどの描き方を見ると、決して写実的に描かれているとはいえません。どちらかといえば、雑なのです。ところが、不思議なことに、むしろその方が、リアルに捉えられた視線と口元の表情が強調されて見えます。
描き方に粗と密の部分を創り出すことによって、老いた母親の本質を冷静に捉え、含蓄のある作品に仕上がっているのです。
キュレーターのアニー・スコッツ-デヴァンブレシー(Annie Scottez- De Wambrechies)は、人生の荒波を超えて生きてきた母親の個性がしっかりと描かれているとデュランの表現力を評価しています。ジェリコー(Théodore Géricault, 1791-1824)やマネ(Édouard Manet, 1832-1883)と並ぶ表現力の持ち主だといっているのです。(※https://www.latribunedelart.com/carolus-duran-une-superbe-sensation-d-art-un-poeme-de-labeur)
リュスは1876年、デュランのアトリエで働くようになります。そこで、デュランが手掛けるさまざまな肖像画を目にしてきました。それらの肖像画を見て、感じること、考えさせられること、多々あったと思いますが、リュスがもっとも刺激を受けたのが、《母の肖像》でした。
■リュス、おばさんの肖像画を描く
デュランの《母の肖像》の制作過程をつぶさに見てきたリュスは、1980年、おばさんの肖像画を描きました。デュランと同様の画法で描いたといわれています。(※ “Léo Gausson Maximilien Luce,Pionniers du néo-impressionnisme”, Silvana, 2019)
《オクタヴィアおばさんの肖像》は、リュスがデュランから何を学んだのかを示唆する重要な作品といえます。
●《オクタヴィアおばさんの肖像》(1880年)
デュランが《母の肖像》を描いたのと同様の画法で描いたとされるのが、リュスの《オクタヴィアおばさんの肖像》です。

(油彩、カンヴァス、77.9×66.7㎝、1880年、ホテル・デュー美術館所蔵)
高齢女性が両手を前で組み、こちらを見ています。老いてはいますが、肌艶がよく、とても元気そうです。顔の表情がリアルに表現されています。
額に刻まれた深い皺、眉間から鼻先までの鼻梁の肉付き、鼻翼から伸びるほうれい線、すぼめた口元など、老化によって起きる顔面の変化が的確に捉えられています。
図録では、リュスが光と影に留意して顔面の表情をリアルに描いたのは、デュランが母親の肖像を描いた時に使ったのと同じ手法を取ったからだと書かれています。(※ “Léo Gausson Maximilien Luce,Pionniers du néo-impressionnisme”, p.14. Silvana, 2019)
果たして、そうでしょうか。
確かに、この作品では、光が当たったところと影になった部分とが丁寧に描き分けられ、眉間の縦皺、額に波打つ横皺、目の下のたるみなどがとても写実的に描かれています。
顔面の骨格を踏まえ、鼻先、たるんだ頬の縁、目の下や目尻などにわずかながら赤味が添えられています。老いに伴う皮膚の変化が的確に表現されているのです。
光と影、明と暗を使い分けて、顔の質感、量感を表現しているところには、ルネサンス以来の写実性が感じられます。つまり、この作品には、デュランが影響を受けたといわれるベラスケスに繋がる写実性が見受けられるのです。
実際、この作品を見ていると、オクタヴィア小母さんを目の前にしているかのような錯覚に襲われます。それほど、リアルに、生き生きと描かれています。
とはいえ、デュランの《母の肖像》と比べると、何かが足りないのです。それが一体、何なのか、二つの作品を比較してみる必要があるでしょう。(2021/12/29 香取淳子)