前回みてきたように、明治新政府の喫緊の課題として、不平等条約改正協議のため、関係諸国との交渉をしなければなりませんでした。廃藩置県を断行すると、早々に、岩倉具視を全権大使として使節団を編成し、課題解決に向けて動き出したのです。
一方、ほぼ同時期に、ウィーン万博への参加打診があり、明治政府は初めて参加することを決定しました。
岩倉使節団の訪欧米も、ウィーン万博への初参加も、明治政府がはじめて現地に出向き、列強と渡り合う機会となります。
そこで、今回は、使節団の参加メンバーから何が見えてくるか、ウィーン万博にへの初参加を明治政府は同見て居たのかを考えてみることにしたいと思います。
■岩倉使節団の編成
1871年7月14日、明治政府は廃藩置県を断行しました。それまで300弱あった藩を廃止し、地方統治を明治政府管轄下の府と県に一元化したのです。
さらに、7月29日には太政官制を発布し、太政官に正院(国家意思決定機関)・左院(議法機関)・右院(行政機関)の3院を設置して、その下に各省を置き、中央集権体制の基礎を固めました。
着々と中央集権体制を整備していく中、喫緊に取り組まなければならない課題がまだ残っていました。一つは、不平等条約改正協議の期限延長を交渉すること、もう一つは、近代国家としての内実を整えること、等々です。1872年5月には条約改正協議の期限が切れることになっていたのです。
これらの課題を解決するには、海外に使節を派遣して、関係諸国と交渉するとともに、現地を視察してくる必要がありました。
そこで、結成されたのが、岩倉具視を特命全権大使とする遣欧米使節団です。
全権大使が岩倉具視、副使に、参議の木戸孝允、大蔵卿大久保利通、工部大輔伊藤博文、外務少輔山口尚芳が選ばれました。いずれも明治政府の要員です。
こちら →
(※ 左から木戸孝允、山口尚芳、岩倉具視、伊藤博文、大久保利通、クリックすると図が拡大します)
彼らの出身と職位は、岩倉が公家で右大臣、木戸が長州で参議、大久保が薩摩で大蔵卿、伊藤が長州で工部大輔、山口が肥前で外務少輔でした。維新を断行した勢力で構成されていることがわかります。
この写真は1872年12月、サンフランシスコ到着直後に撮影されたものだそうです(※https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Iwakura_mission.jpg)。
この時、岩倉が47歳、木戸孝允が39歳、山口尚芳が33歳、伊藤博文が31歳、大久保利通が42歳でした。彼らの表情には、新体制を背負って立つ気概が感じられます。
岩倉具視は公家の正装をし、副使の4人はシルクハットを持ち、洋式の正装をしています。単なる視察ではなく、条約改正協議に関する交渉が主な目的でしたから、正装が必要だったのでしょう。山口と伊藤はブラックタイをしていますから、現地で調達したのかもしれません。ブラックタイは、19世紀英米のフォーマルなドレスコードです。
彼らはその後、諸機関や諸施設を見学した後、22日にサンフランシスコを発っています。
使節団の旅程を見ると、サンフランシスコには12月6日に着いています。歓迎会が相継いだそうですから、その間隙を縫って、記念写真を撮影したのでしょう。
■旅程と使節団メンバー
一行は1871年11月12日に横浜港を発ち、まず、アメリカ、次いで、イギリス、フランス、オランダ、ドイツ、デンマーク、スウェーデン、イタリアを訪問し、スエズ運河を経由し、マラッカ海峡を通過して香港、上海に立ち寄り、1873年9月13日に横浜港に着きました。なんと1年10カ月にも及ぶ長旅でした。
出発時の使節団は、随行員を含め46名でした。それに、女性を含めた留学生が43名と随行員18名が加わり、総勢107名にも及びました。
年齢構成は、40代8名、30代17名、20代17名、10代2名でした。20代、30代を中心に編成されていました。次代を担う若者層に期待し、中心メンバーに据えていることがわかります。
使節団メンバーの出身を見ると、最も多いのが幕臣で13名、次いで肥前藩の8名、長州藩5名、土佐藩4名、公家3名、薩摩藩2名、後は、九つの府や県から1名ずつといった内訳です。興味深いことに、幕臣と肥前藩(佐賀藩)出身者が多いのです。
■なぜ、幕臣と肥前出身者が多いのか?
使節団に、なぜ、幕臣と肥前藩出身者が多いのか、不思議に思ったのですが、その職務内容を見ると、外務を担当する者が多くみられたので、なんとなく納得しました。海外での業務遂行に支障をきたさないような人選が行われたのでしょう。それにはなんといっても語学力が不可欠です。
たとえば、副使として参加していた山口尚芳は、肥前藩出身の外務少輔です。外務少輔とは、外国との交流や貿易、監督に関して外務卿を補佐し、必要に応じて、外務卿や外務大輔の代理を務める役職です。
使節団の渡航の主な目的が、条約改正協議の予備交渉ですから、外務の専門家は不可欠です。外務少輔以外にも、外務少丞、外務少記、外務大録、外務大記などの職名がついたメンバーが参加していました。
山口尚芳(1839-1894)は、幼い頃から優秀だったので、将来を期待されていたそうです。やがて、佐賀藩主・鍋島直正の命令で長崎に遊学するようになります。そこで、オランダ語や蘭学を学び、フルベッキが来日して、長崎英語伝習所で教えるようになると、英語を学び、藩に戻ってからは翻訳方練兵掛として勤務していました。
山口尚芳はオランダ語と英語が堪能だったのです。
これはほんの一例ですが、岩倉使節団に肥前藩出身者が多かったのは、外国語が堪能だったからだと考えられます。鎖国時代に唯一、海外に開かれていた長崎に近く、海外の文化や語学に触れる機会、学ぶ機会に恵まれていました。近代化への志向性も高く、使節団メンバーとしての適性があると判断されたのでしょう。
一方、幕臣出身者は、外務要員もいますが、租税、検査、教育、兵学、造船など、国家を支えるさまざまな業務を担当していることが注目されます。明治新政府は、優秀なテクノクラートとして幕臣を高く評価していたことがわかります。新しい国家体制の中に組み込み、活用しようとしていたのです。
46名の布陣をみると、岩倉使節団のメンバーは、それぞれの領域で、近代国家の構築に寄与できるような人材が選ばれていたことがわかります。優秀な若い人材を欧米で実地見学させ、現地でさまざまな経験を積ませたうえで、帰国後は、新国家建設のために能力を発揮してもらおうという算段です。
ちなみに、使節団が帰国した後、『特命全権大使米欧回覧実記』を刊行したのは、肥前藩出身の久米邦武でした。出発時の肩書きは権少外史です。権少外史とは、太政官正院の書記官で、位階は正七位です(※ https://coin-walk.site/J069.htm#TOP、明治4年7月制定)。
久米邦武(1839-1931)もまた、優秀な人材でした。肥前藩士久米邦郷の三男として佐賀城下で生まれ、藩校である弘道館で学んだ後、江戸の昌平坂学問所で学びました。弘道館での成績は首席を通し、藩主鍋島直大(1846-1921)に論語の御前講義を行っています。
漢籍の素養は、『特命全権大使米欧回覧実記』の執筆に活かされました。簡潔で要を得た表現はいまなお評価が高く、貴重な史的資料として重視されています。
こうしてみてくると、肥前藩がさまざまな人材を輩出していたことがわかります。
鎖国していた江戸時代、長崎出島は唯一、海外に開かれた日本の窓口でした。肥前藩は、長崎出島に近いという点で、地理的優位性がありました。当然のことながら、藩主は、蘭学や洋学、オランダ語や英語の重要性をいち早く、認識していましたし、世界情勢にも通じていました。そして、藩内の近代化にも早くから取り組んでいました。
■幼い頃に留学
岩倉使節団の副使であった山口尚芳は、まだ8歳だった子息の俊太郎(1863-1923)を従者として帯同し、尚芳が帰国した後も、俊太郎はそのままイギリスに留学させています。
幼い頃に海外に出たせいか、俊太郎は語学の習得は早かったようで、次のように説明されています。
「回覧中、尚芳が大隈重信に書き送った書簡中にも、幼い俊太郎が時にはすでに自ら通訳をかって出るなど、その語学習熟の速さに驚嘆した様子が記されている。津田梅子など、幼くして使節団に同行した留学生は多くいたが、なかでも彼は、一行中で「神童」と称されるほどの怜悧さを持ち合わせていたという」
(※ https://www.city.takeo.lg.jp/rekisi/jinbutu/text/syuntarou.html)
9年後に帰国しましたが、彼の英語はもはやイギリス人とまったく変わらないほどだったそうです。1887年に東京帝国大学工科を卒業した後、再び米国に留学し、鉄道運輸や土木工学などの研究を積み、帰国後は鉄道事業に貢献しました。
先ほどいいましたが、岩倉使節団には女子留学生が5名、加わっていました。もっとも幼いのが津田梅子です。1864年12月31日生まれですから、出発時点ではまだ満6歳でした。山口俊太郎より2歳も年下だったのです。
こちら →
(※ Wikipedia。クリックすると図が拡大します)
右から2番目、白い服を着た女の子が津田梅子(1864-1971)です。佐倉藩士として生まれ、幕臣であった津田家に婿入りした津田仙と初子夫妻の次女として生まれました。津田仙は、梅子が誕生した時、江戸幕府に出仕して外国奉行支配通弁(通訳官)を務めていましたが、梅子が3歳の頃、幕府派遣使節の随員として福沢諭吉らと渡米しています。
幕末に幕府がアメリカに使節を派遣したと聞くと、違和感を覚えますが、1867年、幕府はアメリカに注文した軍艦を受け取りに行くため、幕府使節団(使節主席・小野友五郎、江戸幕府の軍艦受取委員会)をアメリカに派遣しました。
この時、随行団のメンバーとして加わったのが、通訳を担当する福澤諭吉や津田仙でした。
1867年1月23日、幕府使節団は、郵便船「コロラド号」に乗って横浜港を出港しました。このコロラド号は、オーディン号や咸臨丸より船の規模が大きく、装備も設備も十分だったようで、福沢諭吉は、「とても快適な航海で、22日目にサンフランシスコに無事に着いた」と、「福翁自伝」に記しています(※ Wikipedia)。
福沢諭吉は、幕府の命を受けて何度か欧米を訪れています。1859年には幕府海軍の軍艦「咸臨丸」に乗ってアメリカに行き、1861年には英軍艦「オーディン号」に乗ってヨーロッパに行きました。そして、1867年は軍艦ではなく、郵便船の「コロラド号」で渡米したのですが、その性能、装備、設備は素晴らしく、技術力の一切合切に驚嘆したというのです。
福沢諭吉は早くから、これから学ぶべきは、もはやオランダ語ではなく、英語だと察知していました。欧米での現地経験、あるいは書物等を通して、そのような見解を得ていたのでしょう。津田仙は福沢諭吉から、米英が優勢だという認識を聞いていたのかもしれません。
さて、1871年10月、開拓次官の黒田清隆が正院に伺い出て、開拓使による女子留学生のアメリカ派遣事業を実現させました。女子にも教育の機会を与えようという思いからでした。それを知った津田仙は、梅子を応募させました。実は、姉の琴子(1862-1911)を応募させようとしたのですが、拒否したので、断念していました。ところが、それを聞いた梅子はが自分から、アメリカに行きたい、といったので応募させ、留学が実現したのでした。
■帰国後の梅子の人生
明治政府が募集した官費女子留学生は、留学期間が10年で、旅費・学費・生活費は全額政府が負担し、さらに奨学金として毎年800ドルを支給するという破格の条件でした。ところが、応募したのは、旧幕府側士族の少女5名だけでした。年齢は、14歳が2名、11歳、8歳、6歳がそれぞれ1名です(※ Wikipedia)。
彼女たちはそれぞれ、大きな希望を抱いて渡航したはずですが、留学を終え、帰国しても何も職は用意されていませんでした。開拓使の黒田清隆が敢えて女子のために門戸を開いたというのに、帰国してみれば、奮闘して身につけた能力を活かす場はなかったのです。
そもそも、官費女子留学生を所管していた開拓使は、1882年2月に廃止されており、梅子が帰国した際、その管轄は文部省に引き継がれていました。11年間の留学を終えて帰国しても、官職が用意されることはありませんでした。
失意に暮れる梅子にも、1885年9月、転機が訪れます。岩倉使節団で一緒だった伊藤博文の推薦で、学習院女学部から独立して設立された華族女学校の英語教師の職に就くこととなったのです。華族女学校教授補は、宮内省御用掛、奏任官に准じた扱いでした。そして、1886年11月には華族女学校教授となり、同校の女性教師のうち、高等官に列するのは学監と梅子だけでした。
梅子は華族女学校で3年余り教えましたが、上流階級的気風には馴染めなかったようで、1889年7月、再び、アメリカに留学します。
今度は、ブリンマー大学で生物学を専攻し、梅子は留学3年目の1891年から1892年の冬に、「蛙の発生」に関する顕著な研究成果を挙げています。研究成果は、指導教官であるトーマス・ハント・モーガン博士(1933年 ノーベル生理学・医学賞)により、博士と梅子の2名を共同執筆者とする論文「蛙の卵の定位」( “The Orientation of the Frog’s Egg”)にまとめられ、1894年にイギリスの学術雑誌 Quarterly Journal of Microscopic Science, vol. 35.に掲載されました。梅子は、欧米の学術雑誌に論文が掲載された最初の日本人女性となったのです(※ Wikipedia)。
自身の経験を踏まえ、女子教育の場の必要性を感じた梅子は、やがて学校の設立を構想するようになりました。アメリカからの資金援助もあり、1900年7月、東京府知事に設立申請を出して認可を受け、9月14日、「女子英学塾」を開校しました。
女子英学塾は、華族と平民との区別のない女子教育を目指していました。それまでの良妻賢母をモットーとする女子教育とは違って、進歩的で自由でありながら、レベルの高い授業が評判となっていたようです。
6歳でアメリカに渡った梅子が、留学生活11年を経て帰国後、さまざまな経験をして、再び、渡米し研鑽した後、創り上げた理想の英語塾であり、自由な精神を育む学びの場でした。
やがて梅子は亡くなりますが、その死から4年が過ぎた1933年、梅子を記念して校名が「津田英学塾」に改められました。その後、戦後の学制改革を経て「津田塾大学」となり、梅子の女子教育への思いは、今に至るまで継承されています。
こうしてみてくると、岩倉使節団は、参加メンバーの活動を通して、日本に少しずつ、変化をもたらしてくれていることがわかります。津田梅子が行ったのは、女性に対する自由平等な英語教育の機会の提供でした。
■列強と渡り合うための武器
興味深いことに、激動の時代を経験し、欧米との間に、技術的、文化的、制度的な落差があることを感じた人々は、教育を重視し、塾あるいは学校の設立に向かっています。
たとえば、福沢諭吉(1835-1901)は1858年に開設した蘭学塾を、1868年に慶応義塾をと名付け、以後、教育活動に専念しました。そして、大隈重信(1838-1922)は1882年、政治学と経済学の融合を志向した政治経済学の構築を目指し、東京専門学校を設立しています。
福沢諭吉は漢籍を学んだ後、長崎に遊学してオランダ通辞からオランダ語を学び、次に江戸に赴き、幕府の通辞から英語を学んでいます。ほとんど独学に近い形でオランダ語と英語を学んでいるのです。
一方、肥前藩出身の大隈重信は藩校で漢籍を学び、アメリカ人宣教師チャニング・ムーア・ウイリアムズ(Channing Moore Williams、1829 – 1910)の私塾で英語を学び、後に、致遠館で教えていたオランダ出身の宣教師グイド・フルベッキ(Guido Herman Fridolin Verbeck、1830 – 1898)から英語を学んでいます。
彼らは、外国語を習得したからこそ広がった視野の中で、日本の将来を考え、日本の運営を考えてきました。学び方の違いはあっても、それぞれ、実際に英語を駆使し、教育や情報収集、海外との交渉に役立てています。
福沢は、1868年に蘭学塾を慶応義塾として以来、官職に就かず、教育活動に専念しました。欧米の書物を翻訳して新しい技術や文化、思想の紹介をしています。さらには、アジアや世界の中の日本の位置づけについての自身の見解を綴って、激動期の指針となるようなメッセージを発信しています。
他方、大隈は、浦上四番崩れ(隠れキリシタンの弾圧事件)について、各国政府との交渉が行われていた1868年、イギリス公使パークスとの交渉で手腕を発揮し、この問題を一時的に解決させました。これを契機に、大隈は政府内で頭角を現すことになりましたが、この交渉の成功は、ウィリアムズとフルベッキから学んだ英学とキリスト教の知識の恩恵であったとされています(※ Wikipedia)。
大隈は、各国との難しい交渉の場で、英語を駆使して、問題を解決していたのです。英語力ばかりではなく、キリスト教文化あるいは、欧米の社会についての知識があったからこそ、それらの問題を解決に導くことができたのでしょう。その後、海外との交渉で、大隈は不可欠の存在となりました。
福沢は、海外の情報や文化を翻訳し、紹介して、当時の日本人の眼を見開かせました。さらに、激動下の日本認識について広い視野から見解を述べることによって、当時の日本人を啓蒙していました。それに対し、大隈は、実際に外国要人との交渉の場で、その力量を発揮しました。
いずれも当時の日本社会に大きく寄与しています。改めて、列強と渡り合うための武器とは何かということを考えさせられます。意思疎通のための語学の重要性ばかりではなく、背景理解のための、社会や文化についての知識や洞察の重要性が認識されます。
ちょうどその頃、肥前出身の佐野常民は、博覧会事務局副総裁として、どうすべきか模索していました。ウィーン万博に出品するにあたって、何をすれば、日本のためになるのか、考えていました。
■ウィーン万国博覧会
ウィーン万国博覧会は、1873年5月1日から11月1日にかけてオーストリア・ウィーンのプラータ公園で開催されました。
こちら →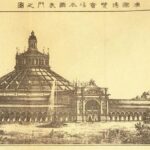
(※ https://www.ndl.go.jp/exposition/s1/1873.html、クリックすると図が拡大します)
上記の図は、博覧会場本館の表門です。
日本のパビリオンは中国の隣で、メインパビリオンのほぼ東端にありました。この主会場以外に、機械、農業、美術など個別の展示館が建設されていました。
ウィーン万博は明治政府がはじめて公式に出品した博覧会でした。30カ国が参加し、参加者は725万人でした。7万点以上が出品されましたが、イギリス、フランス、アメリカからは革新的な発明品、作品、製品が出品されておらず、目新しさに欠けたそうです。
一方、インドや中国、日本からは、珍しくて優れた工芸品が出品されており、参加者の評判がよかったそうです。特に日本については、初めての参加だったせいか、ジャポニスムが巻き起こったといわれています(※ https://www.ndl.go.jp/exposition/s1/1873.html)
明治政府はウィーン万博初参加のために、入念に準備していたようです。
博覧会事務局副総裁の佐野常民は、ウィーン万博に参加するにあたって、目的を5項目定め、1872年6月に明治政府に提出しています。開催の約1年前のことです。
5項目いずれも興味深いので、ちょっと長いのですが、引用しておきましょう。
①日本国内で生産される上質な物産と製品を収集・展示し、日本国が豊穣な国土を持ち、優秀な製品を生産できるということを海外諸国に対してアピールする。
②海外各国の展示品と最先端の技術を詳細に調査し、その技術を学び、日本へ持ち帰ることによって日本の技術水準を高める。
③国内の物産を収集することにより、学芸の進歩のために不可欠である博物館の建設を計画する。
④日本国内の上質な物産と製品が海外諸国の耳目を集め、輸出産業の充実につながるようにする。
⑤海外諸国の出展品の原価と販売価格を調査することにより、海外諸国が求めている品々を把握し、貿易の際の基礎資料とする。
(※ https://www.ndl.go.jp/exposition/s1/1873-4.html)
言い換えれば、①製品や作品を通して日本を世界にアピールする、②海外の製品と最先端技術を把握し、日本製品に取り入れる、③国内の製品や作品を展示できる博物館を作り、製品や作品の進展につなげる、④日本の良質な製品を世界に広く知ってもらい、輸出振興につなげる、⑤海外の出品製品の原価と販売価格を調べ、海外が何を求めているかを把握し、対応できるようにする、等々。
万博を商品の展示場とみなし、海外の市場調査をし、日本製品の強みは何かを把握しようとしていたことがわかります。
実際、ウィーン万博についてはかなり入念に準備していたようです。
こちら → https://www.atpress.ne.jp/releases/168733/att_168733_1.pdf
この中には、実際に出品された製品や作品が載せられています。
有田焼の大きな花瓶や人形、金属製の灯篭、装飾メアシャムパイプなど、精緻な細工の工芸品が多数、出品されていました。このような工芸品なら、現地の人々を惹きつけ、日本ブームが起こるのも当然だと思わせられます。
1873年ウィーン万博に出品されたという磁器の絵皿を見つけました。染付花籠文の絵柄が印象的です。
こちら →
(※ Wikimedia、クリックすると図が拡大します)
花と花瓶がとても繊細なタッチで描かれています。青の濃淡だけでモチーフがきめ細かく表現されているせいか、花びらや葉、茎、それぞれ固有の色彩を感じさせられます。落ち着いた上品な設えの中に、活き活きとした華やぎがあります。
■岩倉使節団の訪欧米とウィーン万博への初参加に何をみるか。
岩倉使節団一行は、ウィーン万博会期中の1873年6月3日にウィーンに到着し、5日に岩倉、伊藤、山口が会場を訪れています。以後、4日間にわたって博覧会を見学し、6月18日に、一行はウィーンを発っています。
会場の賑わいを肌で感じたことでしょうし、日本の工芸品や製品が人気を博していることも見かけたことでしょう。言葉が違えば、風俗習慣も違う異国の地で、日本の工芸品や製品が話題を集めていることに発奮したに違いありません。
不平等条約改正協議のための事前交渉のための訪欧米でしたが、実際に交渉はうまくいきませんでした。ただ、各地の状況を視察することができ、世界がどのような方向で動いているのかがわかったことは大きな収穫だったでしょう。
とくに、万博は商品の展示場でもあり、次元を別にした各国の争いの場でもあることを察知したかもしれません。
列強が日本に開国を迫り、仕方なく、日本は社会変革を起こし、列強に対抗できる国家へと変貌しつつありました。岩倉使節団のメンバー、あるいはウィーン万博関係者が行っていることは近代化への一環でした。彼らは欧米各地で、いったい何を見たのでしょうか。翻って、これまでの日本をどう見たのでしょうか。
(2023/7/31 香取淳子)